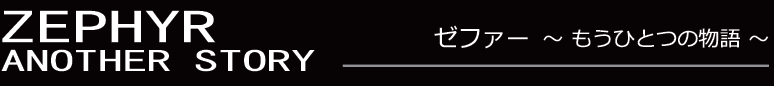1
『アルバイト求む』
なんという無愛想な貼り紙だろうか、と紗与里(さより)は思った。
時給も書いてなければ、業務内容も書いていない。
しかもよくよく見れば、貼り紙は新聞広告のチラシの裏の白い面に、マジックで文字を書きなぐっているだけだ。
「せめて、応談とか書こうよ」と、思わずつぶやく。
こんなものを見て、求人に応じる人間がいるのだろうか。
怪しい。
怪しすぎる。
これがもし、まっとうなビルのショーウインドゥに貼られているとかいうのなら別かもしれない。しかし、見るからに怪しそうな外見の建物だった。
両サイドには背の高いビルが建っている、その狭間に肩をすぼめるようにして佇んでいる、古ぼけた木造の二階建てだった。
もう少し手入れして外観をきれいにすれば、もしかするとロッジ風の喫茶店とか、スナックとか、そんなお店に格上げできるかもしれない。
しかし、現状はどう見ても、時代に取り残されて風化しつつある、ただの小屋だった。
「α占術研究所」という看板が、入り口の横に掲げられている。
奥を覗きこもうとするが、カットされている硝子が木枠にはめ込まれていて、よく見えなかった。
ノブを捻るまで、三回くらい、やめて引き返そうと思った。
が、結局手を伸ばした最大の理由は、友人の樹子(じゅこ)の強力な推薦があったからだった。
ガン! いきなりドアが開き、ちょうどその瞬間に前のめりになっていた紗与里の額を打ち付けた。
「いっ」そこでひと呼吸吸い込んだ。「いった――ッ!」
ドアの向こうから出てきた男は、額を抑えて悲鳴を上げている紗与里に冷ややかな眼差しを当て、「これは失礼」と言った。
そして出てくると、ドアに貼っていた『アルバイト求む』の紙を剥がした。
「あ、え……」
痛みがいっぺんに引っ込んだ。
「あの、アルバイト、決まったんですか」
「決まったよ」と、男は言った。「採用した」
「そ、そうなんですかっ……」
落胆と不安が襲ってきた。不安というのは、何よりも切実な生活の不安だった。
「さあ、入って」
「え?」
「エクセルくらい使えるよね」
「あ、ああ、はい、まあ。MOSの資格持ってます」
「上出来。じゃ、君の席はそこね。で、とりあえず、これをあいうえお順に入力して、顧客リストを作ってくれないかな」
どさっと分厚いファイルが4冊くらい、机の上に置かれた。どのファイルも、中の用紙で膨張しているような代物だった。
呆然とそれを見て、
「はい?」
と、紗与里は男を振り返った。
「時給は××××円。一応、休みは決まってないけど、要望があれば言って。あ、1日あたりの労働時間もね」
「時給××××円? そんなにもらえるんですかッって言う前に、あたし、採用されてるってことですか」
「仕事したくて、ドアの前で何度も貼り紙見てたんじゃないの」
「面接とかないんですか。り、履歴書とか」
慌ててショルダーバッグの中から、ほとんど徹夜で書き上げた履歴書を差し出す。求人情報誌に付録されているものだが、書き損じや、文字の汚さのあまり自己嫌悪になりながら、3回くらいコンビニに通ったのだ。
店に置かれている無料の求人情報誌を持って帰る時も、3回目には窃盗をしているようなやましい気持ちになりつつ、ようやく書き上げたものなのだ。
「ああ、じゃ、ここへ置いといて。後で見るから」
カ――ン! と軽い金属的な擬音が頭の中で響くほど、男は無関心だった。
そう言いながら彼は、自分の机の前に座った。そしてノートパソコンの画面を見ながら、キイボードを叩き始めた。
机の上には2台のPCがあり、2つともノートパソコンだった。片方の画面を覗きこみ、何やら操作した後、またもう一台のノートパソコンのほうで、おそらく文字入力の作業を続けている。
紗与里はたっぷり20秒ほど、その場で呆然としていた。
「あ、悪いけど、コーヒー入れてくれないかな。インスタントのやつ。ブラックで」
その言葉で突き動かされた。
コーヒーなどのお茶類がどこで用意できるかは、見たらわかった。
ビルの谷間にある奥へ向かって細長い建物なのだ。一番奥右手が洗面所で、通路を挟んで反対側に給湯室らしきものがあった。
給湯室にはコンロやシンクもあった。
棚にはまともな珈琲豆もあったし、ドリップする容器もあった。
「あのー、インスタントですかぁ?」と、呼びかけた。
「インスタント」という必要最低限の返答が戻ってきた。
ハーブティなども常備しているようだし、しゃれたカップも用意されていた。
しかし、悩んだ挙句、紗与里はもっとも使用されていると思しき猫の絵柄の入ったマグカップにインスタントコーヒーを入れた。それがシンクの横の水切りの上に置かれていたからだ。
「ありがとう」
マグカップを運んでいくと、男は作業しながら礼を言った。
いろんな意味で、ほっとする。
「あ、あの、本当にあたし、採用されたんでしょうか」
「辞めたいのなら辞めてもいいけど、今すぐ辞めたらさすがに時給は払えないよ」
「あ、いえ。あの、よかったらさせてください。でも、あの……せめて……」
あなたのお名前を、と言おうとしたとき、店の扉が荒々しく開いた。
スーツ姿の男が二人、店に入ってきた。そして、メガネをかけた背の高い男が言った。
「那智(なち)九郎さんですか」
「はい。そうですが」
「警察です。少しお話をお伺いしたいのですが」
男が警察手帳を提示したとき、紗与里は軽いめまいを覚えるとともに、とんでもないところへ来てしまったと思った。
2
「県警捜査一課の三崎と申します。こっちは吉川」
刑事はそう言いながら、提示していた警察手帳を胸にポケットにおさめた。
「よろしかったら、署までご同行願えないでしょうか」
「もう30分もしたら来客がありますので同行は無理ですね。ここでお願いします」
那智は刑事の顔も見ず、キイボードを打ち続けていた。相手が警察だというのに、まったく動揺した様子もない。それどころか、奇妙なことを口走る。
「「いや、面白い」
「は?」
「このタイミングで警察とは……。どうぞ、そこへおかけください」
刑事たちは彼のデスクの前にある椅子に腰かけた。
おろおろしている紗与里に、那智はそのとき初めて履歴書を見て、
「ええと、斎木(さいき)さんか。お二人にお茶を出してあげて」と指示した。
「は、はいッ!」
飛び上がるように反応して、紗与里は給湯室へ向かった。
ととと、と柔らかい軽い足音がした。何だろうと思ってみると、給湯室横にある階段を白と黒の長い毛並みをした猫が降りてくる。
うわ、かわいい~~~。
目がくるくる真ん丸で、宝石みたいだった。
こんな事態ながら、紗与里は思わず手を伸ばした。
が、猫は手の届く少し前で足を止め、不審そうに紗与里を見た。指先の匂いを嗅ぎ、ふいっと知らん顔するようにすり抜けていく。
ナアォ、と鳴き、那智のデスクの上にひらっと上がった。
そうすると当然、二人の刑事と顔を突きあわせることになる。
沈黙。
と、いきなり、ファーッと猫は牙をむき出し、威嚇するような声を発した。
丸めた背と長くて太い尻尾の毛が逆立っている。
刑事が思わず引くほどの迫力だった。
「ベガ、おとなしくしてなさい」と、那智が頭を撫でる。
すると猫は、そのまま見張りをするように、机の上に居座った。
刑事二人と、那智とその飼い猫。
後ろから見ると、異様な光景だった(ちょっと可笑しい)。
「那智さんは金井さんという方をご存知ですか。金井直子さん」
「その前に、これは何の捜査なのか、お伺いしてもよろしいですか」
「殺人事件です」
ひええ~~~っ
紗与里は本当に恐れおののいた。
殺人事件の捜査員がやってくるような場所に、アルバイトで雇われてしまった……。
大丈夫なの!?
と思う一方、好奇心がむくむくと膨らみ、お茶を入れる作業をしながら、耳は外の会話に向かってダンボになっていた。
「で、金井さんから僕のことを聞いてきたということですか」
「そうです」
「ということは、首が見つかったということでしょうか」
「…………」
首? 首ってなに? なんなの、いったい?
「そうなんですよね? だから、刑事さんは僕のところへ来た」
刑事は咳ばらいをした。
「まあ、そういうことです。金井さんはあなたが言われる場所を調べた。そこから本当に頭蓋骨が見つかった」
「二つ?」
「ええ、二つ」
「よかったじゃないですか。事件が起きてからもう十何年も見つからなかった頭部が見つかったんですから」
も、もっと聞きたい! はっきり聞きたい!
紗与里は急いでお茶を持って出た。
刑事の前にお茶を出すと、自分のデスクに座って硬直したようになり、何もせず耳だけをそばだてた。
「被害者のものと確認されたんですか」
「ええ、まあ」
刑事たちは具合が悪そうだった。自分のペースではなく、なぜか那智のペースで話が進んでいるからだった。
「私たちが確認したいのは、那智さん、あなたがなぜ被害者の首がある場所を知っていたかということです」
「知りませんよ」
畳み掛けようと思っていた三崎は、空けた口から続きがうまく出なくなり、身体を前後に揺らした。へたくそなドライバーがさせる車のノッキングみたいな動きだった。
「いや、知っていたということでしょう。現にそこから首が出たわけですから」
「刑事さんがおっしゃりたいことはおおよそ見当が付きます。誰も見つけられなかった首の場所を僕が言い当てた。つまりその場所を知っている僕が犯人なのではないか? そういうお考えですよね」
はあああ? ? ?
紗与里は口が半開きになってしまった。
「斎木さん」
「は、はいっ!」
「さっきも言いましたけど、顧客リスト」
「あ、はいっ!」
紗与里は分厚いファイルを手に取った。PCを立ち上げ、エクセルを起動させるが、開いたファイルのデータなど、ろくに眼に入ってこなかった。
那智と刑事たちの会話ばかりが耳から脳に届く。
他の情報は、いっさい、微塵も入る余地がなかった。
「僕は金井さんに依頼され、非業の死を遂げられたご親戚の首の場所を推理したにすぎません。十何年も首だけが見つからないままでは、成仏もできないだろうと、金井さんは言われました」
「推理?」
「推理ですね」
「どうやって? われわれだって、いろいろな可能性を考え、あちこち調べた。問題の場所だって、事件発生後、調べてる」
「じゃ、見落としたんでしょう」
「見落とし?」
「現にそこから首が出たのなら、その当時の捜査が不十分だったか、あるいは首がどこかに隠されていて、警察の捜査が終わってからそこに隠されたか、どっちかです。しかし、犯人が決定的な証拠となる首を、しかも二つもいつまでもどこかに隠し持っていたというよりは、最初からそこへ埋めるか隠すかした。それを見つけられなかっただけだという方が正解じゃないかな」
「だとしても!」
三崎は声を荒らげた。そして、我に返り、咳ばらいをした。
「いや……そうだとしても、おかしいじゃないですか。なぜ、あなたが警察のわれわれよりも、首の場所を正確に推理できたのか」
「占いですよ」
「占い?」
「ええ。ホロスコープ・チャートを見て、そしてタロットカードを引き、結論を下しました」
3
「占い。ハッ! 冗談もたいがいにして頂きたいですな」
三崎刑事は威嚇するような剣呑な調子で言い、身を乗り出した。
そのとたん、また机の上のベガが、「ファー」と怒気を発した。
今にも引っかかれるのではないかと、刑事も思わず身を引く。
たかが猫一匹のために、ずいぶんやりにくそうだった。あるいは猫が嫌いなのかもしれない。
「あなたが僕の話を信用できないのは、きわめて当たり前の反応ですね。チャートで説明をしたところで、たぶん理解もできないでしょうし」
三崎はむっとなった。
「説明できると?」
「できますよ。なぜ、僕がそのあたりに首があるだろうと言ったかは」
「聞かせてもらえますか」
三崎は四十代半ばだろう。がっしりとした体つきをしていて、いかにも武道とかやっていそうだった。負けん気も強いのだ。
ふむ、と那智はうなずき、PCを操作して、そしてディスプレイを刑事に向けた。
「これは事件発生時のイベント・チャートです」
「イベント?」
「出来事が起きたときのホロスコープです」
「ホロスコープとは?」
むきになったように質問する。
「地球を中心にして見た12星座と太陽系の天体の位置を表示したものです」
三崎がその説明を理解したとは思えなかった。
画面には、円形の図の中に赤や青の線が走っている。周辺に記号のようなものが散らばっていた。

「私が金井さんからお伺いしたところによると、犯行はこの日の夕方5時からくらいから翌日の2時半くらいの間だとか。それに間違いないですか」
「ああ、被害者の老夫婦が最後に目撃されたのが夕方の5時ごろで、この老夫婦の家が燃えていると119番通報があったのが、午前2時半ごろだからな」
「この9時間半のどこかで被害夫婦は殺されているのですが、その時刻は確定していません。とりあえず世間にこの事件が知られるきっかけとなった、2時半のものを作成しましたが、この図は私なりの判断で修正して、一応、18時半に設定しています。ここが犯行時刻と決まっているわけではありません」
紗与里はずっと耳を傾けていたが、言っていることの半分くらいが理解できなかった。
「事件が起きたときのチャートからは様々なものが読み取れますが、じつはこの日のチャートには夕方であろうと、深夜であろうと、変わらぬある特徴があります」
「特徴?」
「ほら、ここ。ここに一つだけ星が離れているでしょう」
三崎は眉間にしわを寄せ、画面に顔を近づけた(ちょっと猫の様子を気にしながら)。
もう一人の吉川という刑事も、メガネを直しながら画面を見た。
「火星です。この時のチャートは、この火星だけがぽつんと離れた状態だったということです」
「それで?」
「これが切り離された首です。火星には頭部という意味がある」
…………
聞いていて、紗与里は背筋に冷たいものを感じた。
「ほかにも火星は、暴力、刃物、火災なども暗示します。この事件は、老夫婦が殺害され、首を切断され、家が放火された。そして首は見つかっていない。そういう事件です。この事件の起きた日のチャートとしては、これは実に申し分ない」
那智は腕組みをし、たんたんと解説している。
「申し分ない?」
「ええ、うまく事件を説明するチャートだということです」
紗与里の耳にも、彼の発言はやや不謹慎に思えた。
「面白がっとるんですか、あんたは」
三崎も同じように感じたらしい。
「面白いというか、興味深くチャートを見ているだけです」
「これは殺人事件なんだぞ。人が死んでいるんだぞ」
「あのね、刑事さん」
那智はうんざりしたように言った。
「僕が面白いと感じているのは事件そのものじゃない。人が殺されたのも面白いとは思っていない。事件とチャートがうまくつながっていることが興味深いと言っているだけです」
「…………」
「続きを聞きたくはないですか」
三崎はむっつりとしたまま、うなずいた。
「この火星はこの事件全体を物語ると同時に、首そのものの象徴です。ですから、僕はこの火星が首の隠された方位だと判断した」
「方位?」
「この場合、北東方位です。被害者の家から見て」
「首が出たのはたしかに北東です」
と、吉川刑事が三崎に言った。
「北東方位にある池か貯水池かプールか、そのような水辺に埋めるか、水の中へ沈めるかしたのではないかと判断したのは、タロットカードです」
那智はPC画面を操作し、記録してあったのであろう、タロットの写真を表示させた。
それはあまりにも衝撃的な出来事を物語っていた。
4

「このカードは、『首はどこにあるか』という質問で引いたものです」
那智の言葉に、二人の刑事はカードの画面を覗きこんだ。
その背中越しに、紗与里も覗いた。鼻の下が長くなってしまう。
「しかし、カードはおそらく事件全体の構造を表現してくれています。最初の『吊るし』のカードの逆位置は、この場合、被害者と見ていいでしょう。ずばり犠牲者的なカード展開です。
その下の『女帝』が見ているのは、『神の家』の逆位置。
『神の家』は天から火が降ってくるカードですが、逆位置になると当然、火は下からついています。これが放火されたということ」
聞いていて、紗与里の顔から表情がなくなる。少し蒼ざめていたかもしれない。
「『神の家』の下にあるのは、『力』と『斎王』のカード。
それはまあ、置いといて、上に戻ります。
『月』のカード、そして『星』のカードが並んでいます。
『月』には二つの建物と手前にプールか池か、そのようなものがある。この隣の『星』のカードも水辺で瓶の水を流している図になっていますが、うまい具合に『月』のカードとつながっているように見えます」
「たしかに」と言ったのは、吉川刑事だった。
むっとして三崎が、肘で小突く。
「カードの質問は、『首がどこにあるか』です。この二枚はその落ち着く先を暗示しています。
この場合は、ずばりどこか池か川か、貯水池とかプールとか、そのようなもののそば。
そのそばに、この『星』の女性が、首を二つ、沈めたということ」
「なんで、そう言える?」と、三崎。
「この女性が持っている二つの瓶。これは二つの首の象徴です」
ゾ――――!
ひぃっと、紗与里は小さなため息のようなものを漏らした。
「斎木さん……」
那智の冷ややかな眼が見ていた。
「あッ、す、すみません」
慌てて仕事に取り掛かろうとする。
「あ、あの、このデータをまるごと写せばいいんですか。け、けっこう、書き込みがありますけど」
「そうだね。よろしく頼む」
「はい……」
冷や汗が滲んだのは、那智に仕事のことを言われたからではなく、彼のカード解説があまりにもリアルだったからだ。
「ちょっと待ってくれ。瓶は瓶であって、首じゃない」
「たしかに。ただ、カードというのはイマジネーションで解読するものなんですよ。その質問に対して、もっとも適切な表現を取るカードが出るという前提で解読する。他にそれを適切に表現するカードがなければ、これで暗示するしかないわけです。たとえば……」
那智は机の引き出しから、きれいな布に包まれたカードを取り出した。
解説しているものと同じカードだった。
「この中にはズバリ切られた首を表現するカードがあります。これです」
恐ろしい絵柄のカードを彼は提示した。
巨大な刃物を持った骸骨のカードだった。その足元の黒いところに、男女の首が転がっている。
「『13番』――一般的には『死神』と呼ばれるカードです。これがなぜ、この質問に対して出なかったのか? もっとも切られた首を表現するには適切なのに。なぜだと思いますか?」
「知るか」
「この『13番』のカードだと、切られた首はこの黒い土壌の上に転がっています。つまりこの絵だと、土のある山の中とかに遺棄されたか、あるいは埋められたというイメージが強くなる。
首が水の中に沈められたのなら、この『13番』は適切ではないことになる」
そういうふうに読むんだ……紗与里はエクセルのセルに、顧客の名前、日時、鑑定内容など、セルの項目を設置して、フォーマットを作る作業を行った。まったく機械的に。
心ここにあらず。
そのため何度もやり直した。
「チャートからは首は北東方位。そしてそこに池か何かあるのでは、と金井さんにお尋ねしたところ、金井さんはあるとお答えくださいました。
鑑定からひと月、金井さんはその心当たりの池を探されたのでしょうね」
「…………」
刑事二人は黙り込んでいた。
彼らの常識からは、あまりにもかけ離れた論理、結論の出し方に、どのように反応していいか、わからなくなってしまったようだった。
「じつはチャートにも、池とか水に関する暗示があります」
那智はPCを操作して、先ほどのホロスコープの画面を出した。
「この日の太陽のサビアンシンボル――まあ、星座の1度ずつに象徴的な言葉を与えたものだとお考えください。それは、これです」
『先祖の井戸にいるサマリアの女』
「この……ナンセンスな話を信じろと?」
三崎は脚をひどく揺すっていた。
「あなたがたがこの話に対してできる態度は二つです」
那智は平然と言った。
「僕の話を信じること。そしてもう一つは、逆に信じないこと。信じない場合、僕が金井さんに行った占いは、ただの偶然に当たったのだと、そのように理解することになる」
「勝手に決めるな。三つ目だってあるだろう」
貧乏ゆすりがどんどんひどくなる。
「三つ目?」
「あんたが老夫婦を殺害し、その場所を知っていた。このホロなんたらも、このカードも、あんたが都合よく並べて解説してるんだ」
「カードは金井さんの目の前で引いていますので、勝手にこの構造を作ることは不可能なんだけどな。それに僕が犯人という説は、絶対にない」
「なぜ?」
那智は立ち上がった。そして背後の金庫を開き、その中からあるものを取りだして、刑事の前に放った。
猫のベガが、鼻先で嗅ぐ。
パスポートだった。
「ご覧ください」
刑事は那智の顔をにらみ、そしてそれを開いた。
「その年の2月から8月まで、僕は日本にいなかった。占星術の研究のため、イギリスへ行っていました。事件は4月に起きている」
カランと鈴が鳴り、入り口のドアが開いた。
「あのー、10時から予約している佐藤ですが」
主婦らしき女性だった。
「裏付けはしっかり取ってください。さあ、お客様がいらっしゃいましたので、お引き取り下さい」
刑事二人は出て行った。
代わりに佐藤という女性が、椅子に腰かけた。
那智の指示で、紗与里は女性に好きな飲み物を尋ね、また給湯室に入った。
紅茶を用意しながら思った。
――もしかして、この男性(ひと)、すごい占い師?
しかしこの事件はまだ終わらなかった。
三日後、二人の刑事がまた訪ねてきたのだった。
三崎は、今度は女性刑事を連れてきていた。
5
その日、紗与里は寝坊した。
ハッ!!として目を開き、枕元の目覚まし時計を見た瞬間、さーっと血の気が引いた。
隣の布団はもぬけの殻だった。
扉を開け、階段を降りて行く。最後の二段で踏み外し、くるぶしのあたりをしたたかに打ち、
「いった――い!」
と叫びながら、足を引きずりながら、それでもリビングに辿り着くと……
不機嫌そうな母・希代子が、子供にご飯を食べさせている図が目に入った。
「お母さん、おはよう」
無邪気な息子の声。
「おはよう……」
「おはよう……」
最後の「おはよう」は、むろん母の声だ。
「おはやくないけどね」
冷ややかな一言が付け加えられた。
「お、起こしてくれればいいのに」
首をすくめながら紗与里は言った。
「起こしましたよ。三回も。目覚まし時計にスマホのアラームも入れたら、計五回、あなたは起こされています」
「や、やっぱり?」
「翔君のママはほんとにお寝坊さんだよねー」
母は別人のような笑顔になって、溺愛している孫に話しかけた。
「だよねー」
「にちゃいの翔君はすぐ起きられるのに、にじゅうきゅうちゃいのママがお寝坊さんなんて、おかしいよねー」
「よねー」
と、二歳になったばかりの翔が、かわいらしく小首を傾げながら同調する。
かわいいだけに、怒りよりも涙しか出ない…(T_T)
自己嫌悪にさいなまれつつ、洗面所で顔を洗い、歯を磨き、お化粧を……あー、もうする時間もないっ! 髪もぼさぼさだあ!
とにかくポニーテールにして、まとめてしまおう。
うん、そのほうが仕事もしやすい!(と自分を納得させる)
服! あー、どれもこれもアイロンが当たっていない! どど、どうしよう。
結局、先日通販で買ったプルオーバーと、昨日もはいていたジーパンでごまかすことにする。
「もう時間ないっ! 翔、行くよ!」
焦りまくって呼びかけながら玄関に行くと、すでに身支度を整えた翔が、にっこり笑って
「行くよ」
……自己嫌悪がいや増す。
翔を車に乗せて、保育園に連れて行き、元来た道を戻り、自宅に車を戻すと、今度は自転車で出勤する。
勤め始めて四日目の、あの占い師の研究所へ。
自転車を研究所と隣のビルの間へこじ入れ、扉を開ける。
ジャスト9時。
ほ――っと、深いため息が出る。
那智は奥の給湯室から、自前のコーヒーカップを持って出てくるところだった。
「お、おはようございます……」
「おはよう」
那智は眼を合わせながら言い、自分のデスクに腰を下ろした。
紗与里も自分のデスクに着いたが、すでにこの時点でどっと疲れが押し寄せていた。
「今日の予約は何時からだっけ」
と、那智が訊いてくる。
「あ、はい」
慌て手帳を開く。この仕事のために百均で買った手帳だ。
「今日は午後からですね。13時の方が最初です。あとは20時の方が最後ですけど、それまではぶっ続けです。先生、大丈夫ですか?」
「なにが?」
「いや、だいたい、50分くらいずつの鑑定時間ですけど、これだと8人も連続で、ほとんど休憩する時間もありませんけど……」
「10件を越えなければ、べつに問題ないよ」
「これから予約を受けるときに、少し間に休憩時間を入れるようにしましょうか」
「問題ないと言ってる」
「あ、はい」
まるでアンドロイドだ。
占いをこなすマシーン。
占いって、すごくスピリチュアルで、霊感とか水晶とか、タロットカードとか、なにかこう神秘的なイメージが強い。
でも、この那智九郎は、そんな印象がまったくない。
PCの画面を見て運勢をたんたんとクールに解説し、タロットも本当にマシーンのように読み取っていく。
かといって、冷たいというのとも違う。
たいていの来客者は、満足して帰っていく。来たとき暗かった顔も明るくなり、時には涙を流す者もいる。
なかなかの占い師なのだということはわかるが、やっていることと、彼の雰囲気がまったく結びつかない。
もうちょっと、情とか……そういうのがあっていいんじゃないの?
言葉にすれば、そんな思いが漠然とある。
紗与里は仕事に取り掛かった。
その一方、むずむずと思っていた。
化粧したい。
翔を運ぶ車の中で、信号待ちの時間を使って半分くらいできたのだが、ちゃんと仕上がっていない。
バッグの中にある化粧ポーチに手が伸びそうになるが、でも、仕事の取りかかったばかりで化粧し始めたら、感じが悪いだろうと思う。
わたしって、女子力、最低だ。
これじゃ、再婚なんて遠い話だ。
おまけに母親力も最低だ。
なんか、落ち込む……。
ずどどど、と荒々しい足音が階上から駆け下りてきて、紗与里の思考を遮った。
研究所のドアの前まで、稲妻のようにやってきたのは、猫のベガだった。
彼女はドアの向こうを、丸い目で凝視していた。
人影があり、ドアが開いた。
あ……と、思わず声を上げた。
それは先日の三崎刑事だった。
「悪いな、またちょっと……うわっと!」
三崎が飛び退く。ベガが、ふわーっと牙をむき出したからだった。
彼の背後から、一人の女性が姿を現した。
ほれぼれするほどのパンツスーツの似合う、年齢は紗与里とそう変わらない女性だった。
そして、ほれぼれするほど美しかった。
6
「こちらは県警捜査一課の剣持警部……。那智さんにお話を伺いたいということでお連れした」
三崎刑事の口調は妙にぎこちなかった。
先日の高圧的なところはなく、どのように喋ったらいいか、迷っているような様子が見受けられた。
しかも紗与里には不思議に思えることが一つあった。
剣持という美女刑事は、あきらかに三崎よりもぜんぜん若い。
それなのに、彼のほうが上司に接するような気の使い方をしているのだ。
「剣持観鈴(みすず)と申します」
と、警察手帳を開いて提示する。
ひゃー、なんて素敵な声なんだ。
紗与里は同性ながら、惚れ惚れした。張りと力がある。外見の美しさといい、そう、ちょっと宝塚女優みたいな雰囲気なのだ。
「そのご様子では、さいわいにも僕の容疑は晴れたということかな」
那智は三崎に向かって言っていた。
「ま、まあ、事件当時、那智さんがイギリスに言っていたということの確認は取れました。事件当日も、ロンドンの……ええと、せ、占星術師、バーバラ・ロックウッドさんが主催する会合に出席していたということもわかりましたので」
三崎は手帳のメモを見ながら言った。
紗与里は空気を読んで、お茶を入れに席を立った。
那智も追い返すつもりはなさそうで、二人に席を勧めた。
「お忙しい方のようなので、ぶしつけですが、さっそく要件に入らせていただいてもよろしいでしょうか」
観鈴は涼しい眼を那智にまっすぐに向けて言った。
「どうぞ」
那智もPCに向かうのではなく、手を休めて、観鈴に向き直った。
「こちらの三崎警部補から那智さんが占いで、老夫婦の首がある場所を推理したというお話を伺いました。
にわかには信じがたい話です」
「そうでしょうね」
「警察としても、このような非科学的なものを根拠に捜査や犯人の検挙を行うわけにはまいりません。
ですから、今日、お伺いしたのは、まったくのわたくしの個人的な興味だとご理解ください」
「わかりました」
「そこで個人的な興味の質問なのですが、那智さんは老夫婦を殺した人物は誰だとお考えですか」
「僕は事件関係者のことなど、ほとんど知らない」
「そうですね。では、どのような人物が犯人だとお考えですか? そのようなことも、あなたの占いで推理できるのでしょうか?」
那智は少しだけ考え込んでいた。
どのように対応するか、迷っているのかと、紗与里は思った。
ところが彼は、
「なるほど……。面白いな」
と、うなずいた。
「何が面白いのでしょうか」
紗与里は話をしている彼らの前にお茶を出した。そして席に戻った。
「ここしばらく、僕にとってはかなり重要な日が続いているんですよ。
かなり運命的というのか、大きな影響力を持つ日です。
そんなときに事件に関する鑑定を依頼され、やがてあなたがたが来た。
これはかなり面白い。
そして、これはあなたの質問に答えるべきということでしょう」
紗与里は刑事が初めて来たときにも、那智が似たようなことを言っていたのを思い出した。
「申し訳ありませんが、那智さんのおっしゃることの意味はよくわかりません。
が、お話し下さるということですか」
「犯人は女です」
「!!」
刑事たちは固まった。
「ば……馬鹿な」
と言ったのは、三崎刑事だった。
「犯人は、老人とはいえ、二人の首を切断しているんだぞ。そんなことが女にできるわけが……」
「そう。たぶん、その思い込みが事件解決を遅らせている」
那智はすごく平静な雰囲気と口調で続けた。
「金井さんから警察の捜査については、ある程度お話を伺いました。
警察はこの事件で、近隣に住むある男性を容疑者と考え、その人物について徹底的な捜査を行ったらしいですね」
「あ、う……」
三崎が言葉に詰まるのを、観鈴が引き継いだ。
「そうです。わたくしはそのように報告を受けています」
「報告?」
「ええ、事件発生時はまだわたくしは小学生でしたから」
「それもそうか」
那智は珍しく破顔した。
「しかし、その容疑者には鉄壁のアリバイがあった。
警察はそのアリバイを崩そうとした。
そして、その男の周辺から首も見つかると、捜査し続けていた」
「そうです。仰る通りです」
「まったく愚かな見込み捜査だと言わざるを得ません」
三崎刑事の首筋まで赤く染まるのが見えた。
7
「見込み捜査だと……」
三崎は語気を荒らげた。
それを観鈴は手を上げて抑えるそぶりを見せた。
彼女の足もとに、ベガが近寄って、しきりと匂いを嗅いでいる。
「それで、女が犯人だという理由は?」
「一つは、事件当日の太陽のサビアンシンボルが『先祖の井戸にいるサマリアの女』というものだったことです」
那智はPC画面にホロスコープを出し、前回と同じように見せた。
「サビアンシンボル……星座の一度ずつに詩文的な意味を与えた前衛的な占星術技法ですね」
観鈴の言葉は、他の者を驚かせた。
「その訳はジョーンズのほうですよね」
「ご存じでしたか。ルディアのものでも『サマリアの女』です。どっちにしても、女を暗示しています」
――この人、占いのこと、知ってるんだ。
その知的な印象からは想像もつかなかった。那智と普通に会話しているが、紗与里やもう一人の三崎刑事はさっぱりわけが分からなかった。
「それだけが犯人が女だという根拠ですか」
「もっとも大きな根拠は、タロットです。これも先日、お見せしたものですが」
那智はPCに保存しているタロット画像を提示した。

「このタロットは首をありかを尋ねたものですが、結果的に事件の起きた状況や関係者も表示しています。
『吊るし』の逆位置は、殺された老夫婦。
その下にあるのが『女帝』です。
『女帝』は『神の家』の逆位置を見ている。
この『神の家』は逆になることで下から火がついている構造になっていて、放火を意味します。
つまり被害者を吊るした……この場合は殺したという解釈でいいと思うのですが、その犯人は『女帝』で表現されうる人物で、その人物が当然、放火にも関係しているわけです」
「その女性がこの犯行を行ったと?」
「ですが、たぶん単独犯ではありません」
「単独でない?」
「『神の家』の下にあるのは、『力』と『斎王』です。ここにも二人、女性に関するカードが出ています。
たぶん『斎王』は母親で、犯人は助けを求めたのでしょう。
あるいは母親が事態に気づき、状況をコントロールした……。
このカードでは逆位置のカードの下に、必ず女性のカードがあります。
女性が犯人としか思えない。
老夫婦を殺した犯人、そして首を切り放火するとい隠ぺい工作を行った人物が、ほかに一人か二人いるはずです」
「右上のカードも女性ですね。『星』のカードですね」
「これは瓶を首に見立てています。二つの首を水の中に捨てたという行為を示していますが、これを行ったのも女性です」
「女性以外、犯行グループにはいない……? そうお考えですか」
「おそらく。たぶん比較的近所に住む女性で、この老夫婦に恨みを抱いていた、あるいは利害があった人物。それが最初の殺害犯で、その犯人の女性を助けるために、母親や他の家族が協力しています」
「犯行の手口から、警察は最初から男性による犯行だと断定していたむきはあります」
「それが初動の失敗でしょう。最初から女性を視野に入れて捜査していれば、あるいは……」
ひらっとベガが机の上に舞いあがった。
そして、観鈴のほうに顔を近づけた。
目がすごく見開かれている。
「可愛い猫ですね」
観鈴は手を出した。
パシッ、とベガの猫パンチが、観鈴の愛撫を拒否した。
ぐるる、と喉の奥で威嚇する。
観鈴はあきらめて手を引っ込めた。
ちょっと紗与里は痛快だった。
ザマミロ。
その猫はなあ、そんなに簡単になつくようなタマじゃないんだ。
あたしだって、まだぜんぜんなつかれてないのに、てめーなんか……
「ありがとうございます。鑑定料はいくらお支払すればよろしいでしょうか」
観鈴はそんなことを言いだした。
「いや、べつによろしいですよ」
「これはわたくしの個人的な興味ですので。料金を取っていただかなければ困ります」
「この件に関しては、最初のご依頼者の金井さんからちゃんと料金をもらっていますので」
「しかし、金井さんには犯人については何もお知らせしていないようですが」
「僕が受けた依頼は、首がどこにあるか、です。
犯人について言及すれば、金井さんは犯人を探ろうとするかもしれない。
そうなったとき、金井さんの身の安全は保障できませんしね」
「だから言わなかった」
「そういうことです」
観鈴は立ち上がった。
「とても興味深いお時間でした。またお会いしましょう」
三崎も追いかけて慌てて立ち上がる。
剣持観鈴はドアを開けて出て行った。
――また?
紗与里はその言葉が、ずっと引っかかっていた。
8
ひと月が経過した。
紗与里はなんとか仕事も慣れ、那智との付き合い方もわかってきたところだった。
アンドロイドのようなという印象は、ますます強くなっていた。
占い師というには、彼はあまりにもクールだった。冷淡とも言っていい。
よく紗与里は、友達の樹子と電話で話をしていた。
「だって、鑑定中に泣き出すような女の人も多いのよ。
やっぱり、昔の悲しいこととか辛いこと思い出すじゃない。ああいう仕事だと。
そんなときだって、あの人、ほろりともしないのよ」
「あー、わかるわかる」
樹子は高校以来の友達で、今はエステのサロンで働いている。近い将来には独り立ちする予定だ。
エステティシャンだけあって、紗与里とはまったく外見的な差が大きい。いつもきれいにしている。
「あの先生、いつもそんな感じだから」
「でしょ。ふつう、そういう時って、『お気持ち、わかりますよ』とか言うじゃない。
あの人、まったくそういうの、ないから」
「でも、一応、気遣ってはくれてるでしょ」
「ああ、まあ、一応、相手が泣き止むのを待ってたりするけど。
だけど、すぐにまた、たんたんと解説をしたり、アドバイスしたり」
「でも、だいたい、お客さん、納得したり癒されたりして帰るでしょ」
「それが不思議なのよねー」
「紗与里も一度見てもらえばいいのに。あたしなんか、毎月一回くらいお願いしてるのに」
「いや、いい。なんか、むちゃくちゃ悪く言われそうな気がするからっ」
というのは理由の半分。
残り半分は、まともに鑑定料を払うのは経済的に痛いからだ。
中途半端なところで採用されたので、最初に支給された給与は、半月分ほどしかなかった。
生活のこと、子供のことを考えると、余裕が出るのなんか、だいぶ先の話だ……
というよりも、いつか余裕が出る日が来るのだろうか、と疑問に思う。
「でも、ほんとよかったよ。あんたが採用されてさ」
「ほんと助かった。樹子には感謝してる。
あそこで募集してるって教えてくれて」
「たまたまあたしが鑑定してもらって、そのときに先生がぽろっと言ったんだよね。
事務仕事をしてくれる人が欲しいから、募集の張り紙を出すって」
「へー」
「それがさ、すごい先生らしい理由でさ」
「え?」
「自分にとってここしばらくはすごく重要な、良い出会いがある時期だから、今、募集を出すんだって。
そういう時には、たいてい良い人が来るからって」
「ふうん、そういうのあるんだ」
「普通の人間なら、運命的な出会いもある時だって言ってたよ。
そんなタイミングで、まあ、よりによって紗与里が採用されちゃうなんてね~。
もしかして、紗与里、あの先生の運命的な出会い?」
「ばか。そんなことあるわけないじゃない」
「あの先生も、そういえば独身かどうかわかんないしね。そういえば、いくつなんだろ」
「そういや、あたしも知らない……あ、そうか」
「なになに?」
「いや、最初に警察が来たときに言ってたのよ。
このタイミングで来たのが興味深いとかなんとか。
それって、その時期のことだったんだ」
納得。
謎めいたセリフの意味が解けた。
うん? ということは、その運命的な出会いのタイミングで、あのちょっと素敵すぎる女刑事も登場してきたことになるわけか?
ということも考えた。
まあ、どうでもいい。
と、頭から考えを振り払った。
ただ、一点。
紗与里は、那智がいつも礼を言うことには、安心感を覚えていた。
たとえばコーヒーを入れるとか、頼まれた仕事をやるとか、そういう紗与里の行為に対して、彼はたいてい「ありがとう」と言う(お客と話し込んでいたりすると別だが)。
礼を言わない人。
自分のやっていることが当たり前。
彼女にはそのように自分のことを扱われる経験が、これまで数多くあった。
以前に勤めていた会社でも。
そして結婚でも。
そんなものかもしれない、とは思う。
しかし、自分のしていることに礼を言われると、存在を認めてもらえていると感じる……。
殺人事件絡みの、あまりにも刺激的な勤務の始まりだったけれど。
これだけ繁盛していて、待遇の良いところ、しかも冷たいけれど、人間的には安心できそうな人間のところで働けることで、ようやく切羽詰った状態を抜け出し、安堵感を覚え始めた頃――。
また、観鈴はやってきた。
今回は一人だった。
彼女は開口一番、言った。
「今日はお礼を申し上げに参りました」
9
「犯人が逮捕されたのですか」
那智は尋ねながら、観鈴に椅子をすすめた。
「はい。自供を得ました。おそらくもうすぐ記者会見が開かれ、世間にも報道されると思います」
観鈴は椅子に腰かけた。
紗与里はお茶を入れに立った。
ベガが階段のところで、じっと入ってきた観鈴を見ている。
「あなたのおっしゃる通り、事件は娘と母親によるものでした。母親は娘をかばって、偽装工作を手伝ったようです」
その後、観鈴は事件の詳しい経緯を語った。
動機。事件発生時の偶発的な状況。
お茶を出した後、紗与里も自分の席で話を聞いていた。
「そうです。もう一つ、付け加えると、その母娘(おやこ)の住んでいた家の近くに、今はもう使われていない井戸があったそうです」
「井戸が?」
「もうそこは埋もれていますが、近所の人の話ではあったそうです」
「先祖の井戸にいるサマリアの女……か」
紗与里は聞いていて、鳥肌が立った。
あまりにも那智の指摘したキイワードがつながりすぎていた。
「ただ……後味の悪い事件になりました」
「というと?」
「その娘のほうは、今、もう結婚していて、子供もいたのです」
紗与里はその言葉に衝撃を受けた。
「そういうことがあっても不思議はないでしょうね。歳月がたちすぎていますから」
「その今は母親となっている娘を連れて行くとき、彼女の子供が泣き叫んで……」
「あ、あの……小さい子供ですか」
思わず、紗与里も口を挟まずにはおれなかった。同じ子を持つ母として。
「小学校に上がったばかりの男の子でした」
観鈴は少し振り向き、紗与里のほうを見て言った。
「そうなんですか……。なんだか、やりきれないですね」
「これから事件が報道されれば、その子の運命も変わってしまいます。ご主人も」
「たまらない……」
わが身に置き換えてみて、紗与里は暗澹たる気分になった。
自分がもし人を殺し、そして逮捕されたら?
そうしたら翔はどうなるだろう。
そして母は……。
世間から後ろ指をさされ、どのようにして生きていくのだろう。
那智を見ると、彼は無表情にコーヒーを飲んでいた。
いつもの、インスタントのブラック・コーヒーを。
「ともあれ、那智さん、あなたのご助言のおかげで今回の長い事件、ようやく解決を見ました。
被害者も浮かばれると思います。
本当にありがとうございます」
頭を下げる観鈴にも、那智は無感動だった。
普通だったら、「いいえ」とか「とんでもない」とかいうリアクションを予測してしまうのだが、それすらない。
何を考えているのかわからない。
そんな那智に向かって、観鈴は意外なことを言い出した。
「予約もお取りしてないのですが、今日はわたしの鑑定をお願いできませんでしょうか」
「よろしいですよ。今は予約も入っていませんし」
「よかった」
観鈴は笑顔になった。笑うと、宝塚女優みたいな雰囲気が輪をかけて、ぱあっと花が咲くようだ。
少しばかり妬ましさを覚えるほどだ。
「生年月日、それにわかれば出生時間も」
那智に問われ、すらすらと観鈴が答えた。出生時間まで知っている人間が少ないが、あらかじめ調べてきたのだろう。
あるいはすでに知っていたのかもしれない。
彼女はホロスコープの知識を持っていた。
そうして彼女の鑑定が始まった。
紗与里は膨大な顧客ファイルの整理作業を続けながら、しっかりと耳を傾けていた。
鑑定そのものはありきたりなもので仕事や健康、それに家族のことなどだった。
それを聞いていると、どうやら観鈴の家系は、警察関係者が多いらしかった。
父親も警察官僚だという。
観鈴も尊敬する父と同じ道を進み、国家公務員上級試験に合格。
警察庁に入庁した。
つまり世にいう「キャリア組」である。
つまり警察官僚に向かうための人材であり、スタート時点から、一般的な警察官とは階級も違っているのだ(どうりで、三崎刑事が年齢も下の女性にヘコヘコしていたわけである)。
「じゃ、月並みですけど、結婚運を見てもらえますか」
と、最後に観鈴は言った。
「かなり変わったタイプの配偶者を得る可能性がありますね。
離婚する確率もやや高めですが、相手によるでしょうね。
あなたの結婚相手は、天王星という星が表示しています。そうですね、全体の6割から7割が、この天王星の暗示です。
天王星は変化や別離を呼ぶ星でもありますが、もし相手が天王星そのもののような人間であるということも考えられます」
「その場合は離婚率は低くなりますか?」
「ええ。天王星がどのように出るか、という問題ですからね。相手は天王星的な人間であれば、離婚として出る可能性は減ります」
「天王星的な人間とは?」
「風変わりで常識の枠からはみ出している人格、あるいは職などを持っている人物。
天王星そのものは宇宙工学や航空機関係、パイロットや空港職員であるとか、あるいはそういう航空機を使っている産業とか。
宇宙を示すのもの天王星で、プラネタリウム、天文学なども天王星です」
「占星術をお忘れでは?」
「占星術も含まれます」
「結婚の時期はいつになりますでしょう」
「ここ数年以内に結婚される可能性があります」
「出会いの時期は?」
「ちょうど今、太陽と月のトラインが発生していますね。今年の3月から5月……この時期に何か出会いや変化はありませんでしたか」
「今の警察署に赴任しました。そしてこの事件を担当しました」
「職場で誰か良い出会いなどは?」
「おじさんばかりですので。だいたい既婚者です」
「なるほど。しかし、良い出会いにつながる導きの時期ですから、後で何かわかってくることがあるかもしれませんね。職場以外でももちろん可能性がありますので」
「わかりました。期待しておきます」
観鈴は腕時計を確認した。
「そろそろ記者会見が開かれる頃です。わたしも署に戻ります」
観鈴はにっこり笑い、そして礼を言った。料金を紗与里は受け取った。
「たしかに良き出会いだったと思います。また先生、よろしくお願いいたします」
観鈴は去って行った。
彼女を送り出し、お茶を下げながら、紗与里はどうしても確認したくなって尋ねた。
「あの、先生」
「なに」
那智はすでにPCに向かっている。
「太陽と月の……ト、トレインでしたっけ」
「トライン」
「あ、すみません。トライン……トラインですよね。
それって、先生のホロスコープにも今あるんですか?」
「あるね。まあ、もうアスペクトが弱まってきているところだけど。なぜ?」
「あ、樹子が言っていたんです。だから、バイトの募集をするって」
「なるほど」
「あたしのこと、履歴書も見ずに採用したのは、それがあったからなんですね」
「そう」
本当に変わった人間であることは間違いなかった。
普通、そんなことを基準に行動する人間はいない。
「ということは、先生も良い出会いがある時なんですね」
「そうなるね」
「あの剣持さんもあるということは、お二人ともそれがあるということで……」
「うん」
「そういうことって、あるんですか?」
「僕の人生には、わりとざらにあるね。ただ、一般的には、確率的には非常に低いよ。今問題にしている太陽と月のトラインは、だいたい何年かに一度、三カ月くらいしか生じないものだ。
それがたまたま一致するというのは、相当な偶然だよ」
「そうなんですね。そういうのって、ロマンチックですね」
「まあ、偶然というのはこの世にないけどね」
「? 運命の出会いって、そういうタイミングで起きるものでしょうか」
「かならずそれで出会うわけではない。
一つの有力なパターンには違いないけどね。
ああ、ついでに、コーヒー、入れてきてくれないか」
那智がカップを差し出すので、「はい」と言って、紗与里はそれも一緒に給湯室に運んだ。
一度、カップをきれいに洗って、水を拭き取ってから、新しいインスタント・コーヒーのブラックを作った。
このごろはもう、どの程度の濃さが好みなのかもわかってきた。
カップを那智のデスクに置くと、彼は仕事をしながら、「ありがとう」と言った。
…………
紗与里は自分のデスクに戻った。
そして、仕事を再開した。
ベガが「にゃあ」と鳴きながら、那智の足もとまでやって来て、そしてひらっとデスクの上に飛び上がった。
――episode.1 END