1
「洪水だ!」
叫びがトリカミに響き渡った。それは鋭い揺れの地震の後だった。
地震は激しいもので、家屋のいくつかが倒壊した。慌てて外に飛び出した里人がほとんどで、下敷きになって怪我をするような者はいなかった。が、それからほどなく斐伊川のほうから異様な轟きが迫ってきた。
トリカミは小高い場所に中心の集落があり、洪水そのものがその丘に駆け上ることはなかった。が、それによって甚大な被害をこうむったのは、他ならぬカガチの軍勢だった。
オロチ連合軍はトリカミ一帯からカナンを追い払うと、そのまま川の下流方向へ部隊を展開していた。トリカミのやや北の広い河原に主力を配備し、さらに北に位置するイズモのカナン軍に備えていたのだ。
気づいたときには遅かった。あっと振り返ったときには、巨大な泥の化け物のような洪水が、兵たちを残らずひと呑みにし、濁流の中に叩き込んでしまった。氾濫した川の水が眼前にまで迫り、命からがら逃げだしたのは、キビから同行していたイオリ――キビで山城を造営していた太守――と、彼の周辺にいたわずかな者ばかりだった。
難を逃れたイオリは泥だらけになってトリカミまで引き返し、カガチに報告をした。
「ほどんど全滅だと……」カガチの表情はさすがにこわばった。
「い、いえ。今も生存者を探しておりますが、あの有様では大半はとても助からぬものと……」
焚火のそばでカガチは、すでに夕闇が濃くなったトリカミの里を見まわした。トリカミには里人の反抗があったときのために百名ほどの兵を残していた。それだけいれば、武器を持たぬ者のコントロールなど容易だと考えていたのだ。
そして残りすべてを北へ向かわせたのは、カガチ自身の判断だった。カナンがどこかで態勢を立て直し、反攻に出てくる可能性を考えたら当たり前の措置だったが、この責はどこへも持って行きようがなかった。
「こんな馬鹿な……」
ヨサミはカガチのそばにいて、彼がそのような言葉を漏らすのを初めて聞いた。さしもの鬼神も動揺は隠しきれなかった。
「全兵力の半分近くを失ったということか……」
オロチ軍はタジマから西進したミカソ率いる軍と、そして海から攻め入ったタジマ水軍、コジマ水軍の二つが、イズモのカナン主力と対峙しているはずで、まだそれは残されているはずだった。そこへ南の山側からカガチたちが進軍すれば、もはや壊滅的な状態になる――はずだった。
その計画が、今、根底から瓦解してしまっていた。たった一度の洪水で。
「カガチ様、この上はミカソらの部隊と合流するのを急いだ方が良いかと」脂汗を浮かべるイオリは、今にも激高したカガチに切り殺されるのではないかという恐怖をありありと見せていた。「もしここへカナンが攻勢をかけて来たら、ひとたまりもありません」
「ひとたまりも?」カガチの眼が酷薄そうな光を浮かべて見つめた。「この俺がここにいるというのにか」
「あッ――いえッ! それは、カガチ様がおられれば」ぶるっと震える。
カガチは立ち上がった。イオリは、ひっと後ずさる。
「巫女どもの様子を見てまいる。イオリ、おまえは生存者の救出の指揮を取れ」
「わ、わかりました」
イオリが頭を下げる横をカガチは素通りして行った。巫女たちを収容している家屋のほうへ向かって歩いて行く。
「皆、死んだ――?」
愕然とした声を上げたのはアナトだった。
巫女たちの前には一人の男が身を低くしていた。彼はイスズがヤマトから連れてきた従者、カーラだった。浅黒い肌をした小柄な男である。
カーラはイスズが連れてきた兵たちとは行動を共にせず、影のようにひっそりとイスズにだけつき従っているのだった。
「先ほどの地震が引き起こした洪水は凄まじく、ここより北に陣を張っていた軍勢すべてをひと呑みに致しました。そこにはほとんどの兵力が集められていました」
カーラはその眼で見た光景を語った。それはすなわち、アナトたちにとっては同胞たちの死を告げるものであった。アナトらキビの巫女たちは、がっくりと肩を落とした。
「わたくしがヤマトから連れてきた者たちもか」と、イスズが問うた。
「はい」
「狂気は凶事を呼ぶ……」ナオヒが言い、傍らでまだ眠っているアカルを見つめた。「アカルがさきほど穢れを吐き出したように、大地もまた穢れを一掃しようとする。穢れを地に溜めこむのは、それは人じゃ。草木も動物も、皆、自然のままに生きておる。ただ、それだけ。が、人は違う。人は意識の在り様を地に反映させるのじゃ」
「人の意識が穢れれば、このようなことは起きると……」と、シキが言った。キビでの災害を目の当たりにした彼女らには他人事ではなかった。「わたしたちのせいということでしょうか」
「シキと申したな」
「はい」
「そなたは意識を身体から離して飛ばすことができよう」
「あ、はい……」初対面なのに能力を見透かされたことに戸惑いを見せた。
「ならばこのネの世界が、丸い星であることも知っておろう」
「はい……。美しい青い星です」
「この島国の様子や星の在り様を見て、何か不思議に思うたことはないか」
「…………」シキはしばし床に眼を落としていたが、はっとしてナオヒを見た。「このワの島国の形のことでしょうか」
我が意を得たりとばかりにナオヒは笑みを浮かべてうなずいた。
「このワの島々は、この星の他の大きな島々と形が似ております! まるで世界を集めたような……不思議に思っておりました」
「その通りじゃ。カタチが似るということは通じるということじゃ。このワの島々には多くの地脈が集まっており、外国(とつくに)ともつながっておる。人の身体で言えば、臍のようなものじゃ。腹の中の子は、臍で母親とつながっておるであろう。ここにイザナミ様がここにおわすのもそのため」
クシナーダ以外の巫女たちは驚き、顔を見合わせた。彼女らにとっては未知というよりも、すでに失われつつある情報だったのだ。
「ワの国は地脈を通じて、じつはこの島国以外の世界の浄化も行っておる。そのためこの島国には地震も火山も多くできておるのじゃ。しかし、もしこの臍であるワの国自体が穢れてしもうてはどうなる?」
「胎児は死にまする」シキは寒々とした声音で言った。
「さよう。この場合、胎児というのはこのネの世界、このまあるい星のすべてじゃ。根が枯れれば、すべて死に絶える……」ナオヒはたんたんと恐ろしいことを語った。「もう一万年も昔、そのような恐ろしい崖っぷちに至ったことがあると聞いておる。その時も人の心は乱れ、穢れを地に溜めこみ、それが溢れ出した。心を持たぬ者はおらぬ。人は皆、その心でこの星の命運にかかわっておる。心こそが未来を作るのじゃからな」
「未来が視えなくなりました、なにも……」イスズが宙を見つめて言った。「ついしばらく前まで、あれほど多様に広がっていた未来が、たった今は閉ざされたように……。そうではありませぬか、クシナーダ様」
クシナーダはうなずいた。「わたくしがかつて視ていた、自分の二つの未来。それが今は闇に塗りつぶされたように、まったく何も視えなくなりました」
彼女は自分の胸を片手で押さえていた。まるでそこが痛むかのように。
「それは、もう未来がなくなったということでしょうか」アナトが蒼ざめて言った。「わたしたちがあまりにもこの世を穢してしまったせいで」
「ヨモツヒサメをヨミに返さねばなりません」と、クシナーダが言った。「あれがこの世に出ているかぎり、未来はないのです」
「わたしはあのようなもの、ただの言い伝えに過ぎぬと思うておりました」年若いイズミが言った。「トリカミが守っている岩戸。天にも地の底にも通じる岩戸。トリカミが侵され、穢されるとき、岩戸に封じられていた〝死の力〟がこの世を滅ぼすという……」
「ヨモツヒサメは人の意識の闇が集まったものです。復讐心、憎悪、嫉妬、強欲――そのような意識の集合体ですが、地の底にある手を触れてはならぬ〝力〟――石のようなものの化身でもあります。それを掘り出し、手を触れてはならぬのです。ぷ……ぷるとにうむ……そのような名の化身です。それにはこの世を滅ぼす〝力〟があります。まさに死の化身なのです」
クシナーダの言葉に、皆、重い沈黙に落ちた。
「クシナーダ様、大丈夫ですか? さきほどから何かお苦しそうなご様子」ややあってイスズが声をかけた。
「はい。ありがとうございます。ご心配には及びません」
その言葉ほど、彼女は顔色も冴えなかった。ずっと胸に手を当てたままである。
「クシナーダ様」アナトが言った。「わたしは先々代の老巫女から聞いたことがございます。〝ヨミ返し〟という技があると」
「はい……。しかし、そのためにはまず私たちが諍いをやめなければなりません。この地で起きている戦いをやめさせることが絶対に必要です」
クシナーダはイスズを見た。その眼差しを受け、イスズは感嘆をあらわにした。「本当に……クシナーダ様は何もかも見抜いておられるのですね」
周囲が何のことかわからず、きょとんとした。ただ一人、ナツソだけが、あ……と思い当たるような反応を示した。
イスズは彼女らに向かって静かに言った。「皆様、わたくしはこの戦いを終わらせるために参りました。それこそがわたくしが果たさねばならぬ責なのです」
一同はその言葉にあっけにとられた。イスズにこの戦いの何の責任があるというのか。そして、この戦いを終わらせる、どのような手段があるというのか。
「カーラ、あの者の居場所は?」イスズは、変わらずそこに待機している従者に言った。
「はい。わかっております」
「今宵、わたくしをそこへ連れて行っておくれ」
「はい。しかし、見張りが……」
「この里の者に頼んで、お酒を分けてもらい、彼らに呑ませなさい。あとは、わたくしが彼らを眠らせます」
「わかりました」
「では、行きなさい」
カーラは頭を下げ、家屋を出て行った。巫女たちに食事を届けるという口実で家に入ったのだが、やや長かった滞在にも衛兵はあまり神経をとがらせなかった。オロチ軍は今それどころではないのだ。今も次々と洪水の現場から、負傷者が里の中へ運び込まれている。
「もし事を起こすとしたら、今宵以外、機会はないでしょう」従者を見送って外の様子を眺め、イスズが振り返った。「わたくしが今夜、ここを抜け出られるように、お力をお貸しください」
「それはできうることなら……」アナトが言った。「イスズ様、いったい何を……あの者というのは?」
「モルデという、カナンの者です」
巫女たちは顔を見合わせた。
「モルデを生かしてここから解放するのです。それだけが唯一、この争いを止める手だてとなります」
「なぜ、あのような者が」
「それは……」
イスズが言いかけたとき、クシナーダが前のめりになって倒れた。
「クシナーダ様!」
巫女たちが動揺して詰め寄る中、クシナーダは胸を抱きかかえるようにして、うわ言のようにつぶやいた。「生きて……」
覗きこんだナオヒが言った。「クシナーダは今、スサノヲを助けようとしておるのじゃ」
「スサノヲ?」
「この争いの命運を握る男じゃ。今おそらく傷つき、死にかかっておる。クシナーダはそれを助けようとしておるのじゃ。そなたらもわかるじゃろう。病の者を癒そうとすれば、同じ場所が痛くなったりするであろう? それを浄化することで病は治る。それと同じことをクシナーダはしておる」
「何事だ」
はっとして振り返った。戸口にカガチの巨体があった。その眼が横たわるアカルを、そしてクシナーダを見た。
「約束通り、アカルの命は救った」ナオヒが言った。「が、まだ二人とも予断を許さぬ。今しばらく安静にさせておかねばならぬ」
カガチは黙って、アカルの顔を覗きこんだ。そのごつい指先で、そっとその頬に触れた。その仕草は似つかわしくないもので、巫女たちを戸惑わせた。しかも、その指先は震えているように見えた。
「よけいな考えは持たず、おとなしくしておることだ。戦いが終われば国に戻れる」
カガチはそのように告げると、去って行った。
2
東の夜空に赤い星が上ったころ、イスズは行動を起こした。衛兵たちはカーラが差し入れた酒を上機嫌で呑み、連日の行軍での疲れも手伝い、焚火のそばで居眠りが付き始めた。
巫女たちは聞こえるかどうかというほどの声音で、人の神経を和らげる歌を口ずさんだ。その一方、イスズたちはやや遠隔ではあったが、〝気〟を衛兵たちに送り続けた。心地よい〝気〟を注入された人は、猛烈な睡魔に襲われる。疲れていればなおさらだった。
衛兵たちの意識がなくなるのに、さほどの時間は必要なかった。
「よいですか。わたくしが勝手に行動したのです。皆様は何も知らずに眠っていた」他の巫女たちを諭すイスズの切れ長の目には、静かだが強い意志がみなぎっていた。「何が起きるかわかりませぬ。わたくしが無事に事を成就して戻ってくることを祈ってください」
アナトたちはうなずき、イスズが衛兵たちの間を抜け、カーラに迎えられるのを見送っていた。里のあちこちで篝火が燃やされているが、やがて二人の姿は闇に同化したように見えなくなった。
「アナト様、わたしは意識を飛ばして、お二人を追いかけます」シキがそう言い、静かに座った。彼女にとっては慣れた技だった。目を閉じて呼吸を整え、幽体を肉体から離脱させる。
シキの幽体はアナトたちには霊視で追うことができた。
「わたしも遠視を……」
アナトたちキビの巫女は囲み合うようにして座り、目を閉じた。肉眼を閉じていようと、シキの姿はしっかりと見据えられている。〝力〟は同種の能力を持つ者と共鳴することで高められる。シキが幽体離脱することで、引っ張られるように彼女らの意識も遠隔視が容易になった。
ナオヒも眠りこけているように見えて、じつはすでにシキと同じく幽体離脱し、イスズの姿を追いかけていた。
里の中は苦痛で満ちていた。昼間の戦争で傷ついている者たちの呻き、悶え苦しみが夜陰の中、気配として伝わってくる。警備に当たっている以外の兵はトリカミの里の祭殿に集まっていること、里人はそれぞれの家屋で過ごしているらしいことがわかった。
カーラに連れられてイスズが向かったのは、その祭殿の近くにある物置のような小屋だった。祭殿前の広場には中に収まり切らない兵士たちが野営している。彼らに気取られないように行動しなければならなかった。
小屋の戸口のところにも衛兵が二人立っていた。指示されるまでもなく、カーラはこの二人にも酒を差し入れたようだった。しかし、疲れと眠気は見せてはいるものの、焚火のそばで話し込んでいて、睡魔に引き込まれる様子はなかった。
イスズがほとんど無言で出した指示で、カーラが動いた。彼は堂々と彼らの前に姿を現し、笑いながら近寄って行った。酒を差し入れていることもあって、衛兵はカーラに気を許していた。
隙をついてカーラは二人を襲った。一人は背後からの強打で、もう一人は振り返ったところをみぞおちに入れた拳で気絶させた。カーラは茂みに隠れるイスズを目で呼ぶ一方、衛兵二人は見えないところへ引っ張り込んで隠してしまった。
イスズが祭殿のほうを気にかけながら急ぎ駆け込んできた。カーラはそのまま戸口のところで警戒に当たる。
小屋の中に横たわる男は満身創痍だった。露出している腕や脚で傷や痣のない場所を探す方が難しかった。髪はぼさぼさ、髭におおわれた顔はやつれ、眼だけがぎらぎらと輝いていた。女の手ではにわかにほどけないほど両手を背後できつく縛られている。イスズはカーラを呼び、戒めを解かせた。
両手が自由になったモルデは、その場に座り直した。そして不審げな眼差しをイスズに送った。
「あんた、誰だ……」血流の通い始めたのを確かめるように手首のあたりをさすりながら訊く。
「ヤマトのイスズと申します」
「ヤマト?」その言葉にモルデは引っ掛かりを感じたような反応を示した。
「一緒に来てください。さあ」
「どういうことだ」
「すぐにお話します。さあ、急いで――」
促すため手を伸ばした瞬間、モルデは厳しい拒絶のこもった動作でイスズの手を払いのけた。
「触るなッ――。異教徒の巫女が」
それは見ている巫女たちも愕然とするほどの、非常に際立った嫌悪だった。これまでの苦痛と憎悪の分もこもっているとしても、モルデが見せた「異教徒の巫女」への嫌悪は、ほとんど本能的なものとさえ言えた。
「あんた、巫女だろう。身なりを見ればわかる」モルデはそう言いながら、周囲のものにつかまりながら立ち上がった。「俺に何の用だ」
幽体となってその場に居合わせたシキは、遠隔視をしてそばに来ているアナトの意識が失望しているのを知った。アナトは一度、キビでの交渉でモルデに相対し、彼らカナンの民が持つ強固な選民的思想を見抜いていた。そのとき以来、モルデは何も変わってはいないということの証明だった。
――しかし、と巫女たちは期待を込めて思った。
イスズが彼女らに語った真実。それをモルデに話し、そしてモルデがもしそれを受け入れることができたなら……。
「あなたを逃がして差し上げます」
「俺を……? なぜだ? おまえらはあのカガチの仲間だろう」
「心ならずも……。あなたには真実を知る勇気がありますか。わたくしが知りたいのはそれです。もしそうでないのなら、このままあなたを置いてここを去ります」
「真実だと? どういうことだ?」モルデの顔に苛立ちがあらわになってきた。「持って回った言い方をせず、はっきりと言え」
「わたくしはあなたがたと同族です」
「!」
このときのモルデの驚愕と混乱ぶりは見ものだった。驚き、猜疑、揺れ動き、そんな感情をぐるっと回ったのち、彼は最後に笑いという表現を選択した。
「ばかな……。はは、何を言い出すかと思えば」
「ヤー・マト」イスズが言った。「その言葉の意味は?」
それはモルデがさきほど引っかかった言葉だった。
「……神の民……」心を許さぬ警戒を滲ませながらモルデは言った。
「そう。あなた方の元の言葉で〝神の民〟――それがわたくしの国の由来でもあります」
「あんたの……?」
「わたくしはあなたがたより先んじて、この〝もう一つの土地〟――エルツァレトに辿りついていた者の末裔です」
この瞬間、モルデの顎が外れるのではないかというほど口を開いていた。「あ……あ……まさか、〝失われた支族〟……!?」
「そうです。わたくしたちの先祖は北の王国サマリアが滅び去った後、ここへたどり着いたのです。そうして幾世代も、この地の人々と交わり、溶け合って時代を生きてきました。モルデ、あなたがたは南の王国の末裔でしょう」
「し、しかし、そんな……それなら、なぜそのような異教のわざを……神のご意志に背き、また邪教に堕落したのか」
「愚かな……」
「愚か?」
「わたくしの先祖は長き放浪の果て、この地に辿りつき、真実を知ったのです」
「真実とは……」
「創造されたこの世界にただ一つの神を見る者と、この創造された世界すべてに神を見る者の違いでしかないということに」
――唯一の神。そなたらの言う唯一の神というのは、いったいいかなる神なのか。
――この地のすべてを創造され、支配されておられる神。
――その神のどこが、われらの感じる神々と違うのだ。
モルデの脳裏に、アナトと交わした言葉がよみがえった。あのときは一笑に付してしまったが、あのやり取りの裏側にあったアナトの言わんとすることは……。
「モルデ、良いですか。神は普遍的なものです。しかし、それは伝える人間によって、否応なく色づけされてしまうのです。人の言葉で神のすべてを表現することはできないのです。それは子供が、大人の考えを把握できないのと同じことです」
モルデはよろめき、背後の壁にぶつかった。積み上げられていた薪が崩れた。
「そんな……」
「あなたの君主であるエステル様にお伝えするのです。戦い、奪うことをやめれば、この島国で当たり前に生きていけるのです。わたくしたちがその証明です。もしよかったら、わたくしの国に来てもらってよいのです」
はっとモルデはイスズを見た。捕虜の身であっても、彼にもこの戦況がカナンにとって極めて厳しいものであることは理解できていた。
「あんたの国に……」
「そうです。ヤマトに」
「ヤマト……」落ち着きのない眼が、足元のあたりをさまよった。激しい迷いが彼の心に生じていた。
「わたくしが嘘をついていると思いますか」
「い、いや……」
「いつか、あなたがたのような者が到来すること、わたくしたちは待っていたのです。争い奪うのではなく、共に生きましょう。このワの国で。さあ――」
イスズの差し出した手。モルデはそれをしばらく凝視していた。
シキやアナトたちは残らず、このとき祈っていた。イスズの想いがモルデに伝わり、彼を動かすことを。
モルデの手が、ゆっくりと持ち上がった。
この国に来たときから、他の異教徒と〝どこか違う〟と感じていた、その漠然とした想いの根源――それが今、イスズという巫女として彼の前に存在していた。
それと彼は、手を結んだ。
イスズは、これ以上はないというほどの微笑みを浮かべた。
「神はすべて……。ならばこの世のすべてに神は宿っておられる。このワの地に来て、わたくしたちはそれを知るというよりも実感したのです。すべては貴い。すべてに神性がある。この島国の民は、まるで息をするかのように、その感覚を普通の暮らしにしていた。そしてあなたがたも、わたくしたちの祖先がそうであったように気づくでしょう。このエルツァレト――葦原の国は、本当はわたくしたちにとっても、はるかな……」
「イスズ様、お急ぎください」カーラの鋭い声が割って入った。
小屋の中の二人は、はっとして動き出した。
――カガチが来る!
幽体離脱しているシキは、あえてそのとき小屋から離れ、上空からの視点を得ていた。そして警告を発した。
その思念はイスズにも伝わった。
「カーラ、モルデを導き、この里を出なさい。そして彼と共にエステル様に伝えるのです。戦いを終わらせ、違った道を選ぶように。このような手段によらずとも、カナンはこの地で生きられる。わたくしたちの祖先がそうであったように」
イスズの言葉にカーラは衝撃を受けた。「イスズ様は――」
「おまえはこれより後はアナト様にお仕えするのです」
「イスズ様――」
「お行きなさい!」イスズは鋭い声音で従者に命じた。そして、モルデの背中を押した。
硬直している男二人をしり目に、イスズは祭殿に向かって歩き出した。篝火に照らされた広場を、巨漢が歩いてくるのが見えた。カーラはそれを見て、モルデの腕をつかんだ。茂みをかき分け、里を出るべく、もっとも近い進路を走り出す。
イスズはあえて目立つようにカガチに向かって歩いて行った。
「なにやらおかしな気配がすると思うておったが……」カガチは酷薄な眼を下ろして言った。「イスズ……こんな夜中になにをしておる」
「あなたと話をしようと思ってやってきました」
「ほう。なんの?」カガチの視線はイスズの背後の小屋へ動いた。そこにいるはずの衛兵の姿がないことには気づいていた。
「兵をお引きなさい」
「なんの冗談だ」
「あなたは大きな過ちを犯しています」
カガチの背負う悪霊の如きものがざわめき、イスズに圧力をかけてきた。
「あなたの行いが触れてはならぬものに触れ、解き放ってしまいました。あなたは自分の未来をも、自分で消し去ったのです。しかし今ここで、未来にはかすかな光がある。その光を広げ、未来を呼び戻すためには、ここで兵を収める必要があります」
「ふざけたことを……。あの者を逃がしたな」カガチの眼が小屋を見た。「どういうつもりだ。何を考えておる」
カガチは予知や読心の能力をヨサミから得ていた。この夜にイスズの動きを察知したのも、その〝力〟と無関係ではなかったろう。が、彼は本来の巫女ほどその能力を使いこなせてもいなかったし、イスズのような巫女が心を閉ざしてしまえば、その考えを読み取ることなどはできるものではなかった。
ちっと舌打ちし、カガチは祭殿の広場で野営している者たちに叫んだ。「捕虜が逃げたぞ! 追え!」
疲れ切って眠りに着いていた兵も、その轟くような一声で飛び起きた。
「カガチ様! いったい何が――」
「さっさと追え! カナンの捕虜が逃げた! 探し出し、連れて来い!」
兵たちは慌てふためき指令に従って散っていく。
「あの者の首をエステルとやらの目の前で切り落としてやるのが趣向よ。おまえなどに邪魔はさせん」
イスズは眉根を寄せた。
「ヨサミはそれを見て、さぞかし喜ぶだろう。やつらにはただ死ぬよりも惨い思いを味わわせてやる」
「愚かな……」
「イスズ、おまえはいつもそうだ」カガチはゆっくりと巫女の回りを歩きながら言った。「俺を哀れな者のように見下げた物言いをする」
「あなたの行いは、ただ憎しみを生み増やし、育てるだけ。それはいつか自分に戻って来る。それを愚かと言わずして何と言えばよいのですか」
カガチは腕を伸ばし、大きな掌でイスズの顔面をつかんだ。指の間から切れ長の眼が、ずっと見つめ続けていた。
カガチの背負うものが、いっそう大きくざわついた。苦悶し、のたうつようにうごめく。
「……そんな眼で俺を見るな」
頭部を締め付ける握力が強まり、イスズは苦痛に耐えた。が、眼が閉じられることはなかった。
「その眼をやめろ……。その冷たい眼を!」
カガチはまるでボールでも投げるようにイスズの頭部を地面に叩きつけた。細い首が折れるのではないかというほど暴力的なやり方だった。
――イスズ様!
シキが、そしてほかの巫女たちが意識の叫びをあげた。
獣のような唸りを発し、カガチは苦しむイスズの身体の上にのしかかった。「やめぬのなら、この場でおまえを犯し、五体を引きちぎってやろうか」
そう言い、胸元の衣類を引き裂いた。怪力のカガチには造作もないことだったが、衣が裂けるほど引っ張られるのだ。イスズの肌は傷ついた。
「やってごらんなさい」イスズは苦しみながら、それでも毅然とした眼をなくさなかった。「その前に舌を噛みます」
その眼の中に、カガチはかつて自分に向けられた冷たい女の眼を見ていた。
――あんたなんか、生まれなければよかった。
そう言った母の眼だった。
その母は、起きた戦乱の中、他の家族もろとも惨殺された。殺される前、侵略兵によって犯され――。
子供だったカガチは、隠れてそれを見ていた。事後、血の海と化したその場所に、カガチは佇み、骸となった母を見下ろし、思った。
このような惨い死に方をするくらいなら……
俺が殺してやればよかった。
数々の女の面影がフラッシュバックした。それはアワジら、トリカミの巫女たちの顔だった。彼が毎年、殺してきた女たちの顔――それが今、イスズの白い面差しの上に重なり合っていた。そして、母の顔も――。
イスズは視野が暗くなってくるのを感じていた。カガチの両手が首を絞めつけていた。
――イスズ様!
悲鳴のような声が聞こえる。他の巫女たちが狂ったように騒ぎ立てていた。
――見ておくのです。救われ得ぬほどの悲しみを。
イスズは思念を放った。
巫女たちは視ていた。イスズの上に馬乗りになり、首を絞めている男の姿を。
いや、それは巨漢のカガチではなく、少年だった。少年は涙を流しながら、〝母〟の首を絞めていた。すでに息絶えた母の首を、彼はもう一度絞めていた。
その母の顔は、アカルに似ていた。
――それでも……。
イスズの意識が途切れた。
離れた場所にある巫女たちの家屋で、アカルとクシナーダは同時に目を覚ました。
「イスズ様……」
気づくと、キビの巫女たちは抱き合って泣いていた。
ナオヒはクシナーダと目を合わせると、やるせなく首を振った。
遠い篝火が照らすイスズの顔は、もう眼を閉じていた。
カガチはぶるぶると震える両手を見つめていた。よろめき、動かぬイスズの上から離れた。そして彼は吠えた。
月のない夜空に向かって。
3
全身、痛みを発さぬ場所などなかった。身体が熱く、だるい。しかし、そんな状態でありながら、モルデは走っていた。
松明を持った追手が迫る。カガチに命じられた兵士たちだった。
「待て!」幾度も叫びが背中に突き刺さる。
息が切れる。長く囚われ、力を失っていたモルデの足がもつれた。とてつもない氾濫を起こした斐伊川が満たした泥に足を取られ、転倒してしまう。
「モルデ様!」カーラが慌てて引き返してくる。
兵士がそのカーラに斬りかかる。敏捷にそれを避けながら、カーラは相手に足払いをかけた。ひっくり返り、泥に顔を突っ込んだ兵士からモルデがすかさず剣を奪う。
モルデは雄叫ぶように気合を発した。襲い掛かってくる兵を押し返し、斬りつける。
生きる。
俺は生きて、エステル様のところへたどり着く。
その執念が弱り切っていた彼の身体に活力を与えた。カーラも敵兵の剣を奪い取り、応戦した。が、追手は多かった。たちまち取り囲まれてしまう。
もはや退路はどこにもなくなった。
その時だった。オロチ兵のひとりが絶叫を上げた。背後からの攻撃を受け、もがき苦しみながら倒れる。その向こう側から現れた黒い影が、また一人、そしてもう一人、不意を突いて斬りつけた。兵士の持っていた松明が、ぬかるんだ地に落ち、じゅうという音を立てて火を次々に消していく。
突発的な事態にうろたえる反対側のオロチ兵の背後から、また急襲があった。うわああ、と叫びと共に、兵の背中に突っ込んできたのは少年だった。さらにその隣に出現した男は一人の兵を斬りつけ、もう一人は脚で蹴飛ばした。
囲みは完全に破れた、思いがけぬ助勢を得たモルデとカーラは包囲を突破した。
「こっち! こっちよ!」少女の声が聞こえる。
モルデはその声のする方へ走った。
松明の光が少なくなり、闇の濃度が増した場で、攻防が繰り広げられた。が、夜陰に紛れて襲われたオロチ兵は、動揺を立て直す暇も与えられなかった。カーラと最初の黒い影の男が、それぞれに最後となった敵を打ち倒した。たまたま岩の上に落ち、消えるのをまぬかれた松明の一つを黒い影の男が拾い、モルデのほうへ近寄ってきた。
その男はニギヒであった。
そして彼のそばにイタケル、オシヲがいた。オシヲは興奮し、大仕事を成し遂げた後のように玉の汗を浮かべ、荒い息を繰り返していた。
明かりが近づいたので、モルデは自分を呼んだ少女のほうを振り返った。そこにはスクナがいた。
「モルデ様、大丈夫ですか」カーラがやって来た。これも息が荒い。
「誰かと思えば――小汚えなりをしてるが、おめえ、いつかのカナンのやつだな」イタケルが言った。
相手はトリカミの里の男だとモルデも知った。
「どういうことだ、こりゃあ。ちっと説明してもらおうか」
イタケルたちは運に恵まれていた。あの地震をきっかけとする川の大氾濫が起きたとき、彼らはスクナの誘導で川から離れた道を進んでいた。これは当然、川沿いの道に存在するかもしれないオロチ・カナン双方の兵を警戒していてのことだった。岩戸への往路と同じく、復路もスクナが熟知する山中の抜け道へ針路を取っていたとき、洪水は起きた。
これが結果的に彼らの命を救った。トリカミ近郊へようやくたどり着けば、あたりは戦乱の跡、おびただしい死体が横がっていた。このときイタケルやオシヲは、カナン兵の剣を調達した。どこから敵が出現するかもわからないのだ。
トリカミの里にある遠い篝火。それだけがこの月のない夜に頼りとなるものだったが、土地勘の明るいイタケルたちにはなんとか夜陰に紛れての行動が可能だった。
遠目にもオロチ軍が占領しているらしいことは分かった。里の中の状況がどうなっているのか、どうにかして闇にまぎれて侵入する算段を練っている時だったのだ。
複数の松明の光が里を駆け下りてきたのは。
その兵たちが何者かを追っているのは明らかで、追われているのは里の者である可能性が高いとイタケルたちは判断した。そのために助勢に入ったのだ。
しかし、そうではなかった。彼らが助けたのは、見る影もないほどやつれ、みすぼらしい姿となっていたモルデ、そして初対面のカーラという男の二人だったというわけだ。
彼らはトリカミの里から一度距離を取り、およそ里の者以外は知られることのない洞窟に身をひそめた。
「ヤマトにカナンの仲間がいるってのか」岩の上に腰を下ろしているイタケルは、イライラと貧乏ゆすりをしながら言った。「カーラといったな、あんたもそうなのか」
「はい。私の先祖はおよそ四百年ほど前、ツクシを経てヤマトへたどり着き、そこへ定着しました」
「そういえば……」イタケルは首をひねるようにして言った。「アシナヅチ様が言ってたな。その昔、なんとかっていう方士が多くの民を引き連れて、このワの島国各地へ移ってきたことがあると」
「イスズ様の直接のご先祖です」
「イスズって巫女のことは聞いたことがある。ミモロ山の巫女と言えば有名だ」
「それで……」と、ニギヒが口を開いた。「そなたらはこれからどうするのだ。エステルと言ったな、カナンの姫は。その姫のところへ向かうのか」
「はい。それがイスズ様より与えられたお役目なれば」そういうカーラの眼は、しかし、どこか不安に定まらぬものがあった。自分たちを逃がしたイスズのことが案じられてならないのだった。本音では里へ戻りたいに違いない。
「おい、モルデ」イタケルは言葉を投げつけるような調子で言った。「てめーはどういうつもりなんだ」
「どう……とは?」
モルデのそばにはスクナがいた。スクナは濡らした布と、採取してきた薬草で、彼の傷の治療を行っていた。
「エステルのところへ戻り、どうするかっていうんだよ。そのイスズが言ったようなことをエステルに伝えるのか」
沈黙があった。洞窟の中では焚火が燃やされ、モルデの横顔を照らしていた。
「……おそらく、この戦いには勝てぬ」彼はやがて言った。「あのイスズという者がいうことが真実なら、われらはやり方を誤っていた」
「勝てないとわかったら、戦いやめましたってか。ふん、都合よくねえか。てめえらがやらかしてくれた戦のせいでな、いったいどれほどのワの民が死んだと思ってるんだ」
また沈黙が落ちた。
「あんたらが来なければ、ミツハは死ななかった……」オシヲが枝で焚火を突き刺すようにしていた。「アシナヅチ様も」
「カナンもオロチも殺し合って滅びりゃいい。それが俺らの本音だ」
イタケルの言葉に対して、モルデは何の反論もしなかった。できなかったというべきだろう。
「それじゃ、だめだよ」
その声に一同は我に返ったような反応を示した。スクナがモルデの膝に薬草を押し当てながら続けた。「そんなにうまいこと、どっちも滅んだりしない。それどころか生き残った者が、また相手を殺すためにやって来る。……ツクシはずっとそんな日が続いていた。あたしがもともといたナの国だって……」
「その通りだ」ニギヒがうなずいた。
「あたしの住んでいた里は、みんなみんな、殺されてしまった。だから、父さんと母さんはあたしを連れて、大陸に渡ったんだ。殺し合いばかりじゃなくて、人を生かせる方法を探さないといけない。父さんはいつもそう言ってた。あたしが覚えることが得意なので、いろんなものを見聞きさせて、薬草のことや治し方を勉強させたのも、そのため……」
「そういうことだったのか」イタケルはしみじみと言った。「それでナの国には戻りたくても戻れなかったんだな」
「生きている者同士が戦いをやめないと、どうにもならない。戦いはとまらない。死んだ者のことばかり考えたら、どこもかしこも、きっとあたしのもとの里みたいになる」
もっとも年少のスクナが発した言葉は、イタケルやオシヲの胸にある憎悪の立ち上がりを挫く力があった。オシヲは首にかけている朱の領布を手にし、見つめた。
――ミツハに誇れるおまえでいるのだ。
スサノヲの言葉が脳裏をよぎり、オシヲは領布をぎゅっと握りしめた。苦しげに。
ちっとイタケルは舌打ちした。腰から下げていた小袋を手に取り、それをモルデの目の前に放り投げる。「食え――干し肉だ。精をつけなきゃ、明日、歩けねえぞ」
痩せこけた腕を伸ばし、モルデは震える手でそれを取り上げた。中を開くと、鹿の干し肉が詰まっていた。餓死をまぬかれる程度のものしか与えられていなかった男の喉が、ごくりと鳴った。取り出した肉を口に運び、食(は)む。幾度も幾度も噛みしめた。自然と、その頬に涙がひと筋ふた筋と流れ伝った。
「すまない……すまない……!」鳴き咽びながら、モルデは干し肉を食べ続けた。
もともと白い肌が、今は雪のようだった。巫女たちは横たわる美しい巫女の死に顔を、ずっと見つめ続けていた。
「イスズ様……」
その名が口々に、涙と共に呼ばれ続けた。
イスズと血のつながりがあるシキ、イズミはことに大きなショックを受けていた。二人にとっては精神的にも、本当の姉のような存在だったのだ。
カガチがイスズの首を絞めはじめたとき、幽体離脱や遠隔視によって状況を認識していた巫女たちは、もちろんイスズを救おうとして動き出した。しかし、その時点ですでに里は逃亡したモルデを捜索する兵士たちが走り回り、先刻までうたた寝に引き込まれていた見張りの兵士たちも目を覚ましていた。
その状況で、彼女らは肉の身を動かして、イスズを救出に向かうこともできなかった。むろん駆けつけることができたとしても、間にあったはずもなかった。
なす術もないまま、ただ彼女らの感覚はイスズの死を知覚するということしかできなかったのだ。
白い布がイスズの遺体にかけられた。それを見つめるイズミは、思いつめた表情でつぶやいた。「かならずお心をお継ぎ致します」
シキとイズミは知らされたのだ。彼女らの身体にも、はるか昔に渡来したカナンの民と同じ血が流れていることを。その血は混淆しながら、ずっと世代を越えて受け渡されてきたが、彼女らはその古い時代の事実を知らずに生きてきた。
それで良いのだ、とイスズは言った。けれど、この事実を伝承してきたイスズの一族は、この日のあることを半ば予知し、そのとき果たすべき役割があることを自覚していた。そのことだけは心の核に収め、数百年を生きてきたのだ。
その役目を果たすために自分の命を捨ててでも、というイスズの峻烈な使命感は、とくに若いイズミにとって目の覚めるような衝撃だった。なまじの霊能があるばかりに若くして巫女の地位に押し上げられ、まつりごとの中に組み込まれてしまった彼女は、ワケの国の中にあっても自分の存在意義を見いだせずにいた。誰か他の者でも良いのではないか――常にそんな想いがあった。
能力として見たときには、アナトやシキの〝力〟には遠く及ばなかった。それだけに、いつの間にかひがみのような気持ちが根を張ってしまっていた。国の都合のために存在している自分。
イスズの使命感は、それとまさに対比するものだったのだ。
だが、そのような小さな思いにとらわれているときではない。
自分のできることをする。
すっきりと覚醒した意識の中に、強い意志が今は根を張っていた。
「アナト様……提案がございます」
まだ泣き止まぬ巫女たちの中、イズミは口火を切った。その強い声音に触発されたように、巫女たちは悲しみの淵から少しだけ引き戻された。
「クシナーダ様、ナオヒ様、そしてアカル様もお聞きください。……わたしたちキビがカガチの支配を甘んじて受け入れてきた大きな理由は二つ。一つはクロガネ造りのためと称し、国の多くの者を人質として取られていること。そしてもう一つは、このトリカミを守るためでした。されど今、その理由のうちの一つはなくなった。そういうことではないでしょうか」
それを聞いたアナトは、袂で涙をぬぐいながら応えた。「……じつはわたしも、まったく同じことを考えていた」
「アナト様も?」
「はい」
「わたしは信じてはいませんでしたが、あのヨモツヒサメは言い伝え通りの恐ろしい存在でした。あれを世に出さぬためにわたしたちは耐えてきたはず。あれが世に出てしまったのなら、わたしたちがカガチに従わねばならぬ理由の一つは、もはやありませぬ。そうではありませぬか?」
「イズミの言う通りです」
「ならば、あとはキビの国から徴収されて、タジマやイナバに送られている者たちを救い出せばよいのでは?」
「それで、わたしたちは自由になると?」
「カガチと袂を分かつべきです」
キビの巫女たちは顔を見合わせた。
「でも、どうやって囚われている者たちを救出するのです」
「それは……」イズミの強い視線は、アカルのほうへ向けられた。「アカル様ならキビから徴収された者たちがいる山やタタラ場をご存じなのでは?」
周囲の視線を受け、アカルはうなずいた。まだ顔は蒼ざめたままだ。「わたしは存じております……もともとはタジマもイナバも、わたしの父が治めていた土地ですから」
「ナツソ様……」次にイズミは、ナツソに視線を向けた。「コジマの水軍をカナンとの戦いから引かせ、囚われている者たちの救出に向かわせることはできないでしょうか」
ナツソは驚くべき提案に目を丸くし、しかし、しばしの思案の後、はっきりと応えた。「わたしからの指示を伝えることができますれば」
「しかし、コジマの兵の中にはカガチの密偵も紛れ込んでいるのでは?」と、アナトが言った。「モルデがキビに秘密裏に交渉に来たときも、カガチには筒抜けになっていた」
「はい」と、ナツソはうなずいた。このキビの巫女の中でももっとも控えめな娘は、しかし、海の民の巫女らしい、奥深いしたたかさを秘めていた。「あの件があってから、わたしはコジマの水軍の中でも、とくに信頼がおける者たちと、そうでない者を組み分けるようにしたのです。非常に重要な伝達を行うときの合言葉も取り決めております。信頼できる者にさえ連絡が取れれば、そして囚われている者たちの場所さえわかれば、そのように動くことは可能です」
コジマの水軍は、キビの中で唯一、今回の洪水での壊滅的な被害を免れていた。イズモの北面からの侵攻の一役を担って別働隊になっていたためだ。
「ただ、問題はどうやってそれを伝えるかです。わたしたちにはここを出る手段がありません」ナツソは残念そうに言った。
「それは……おそらく大丈夫だと思います」黙って聞いていたクシナーダが言った。「わたくしがかならずなんとか致します」
「ありがとうございます、クシナーダ様」アナトはクシナーダとナオヒ、そしてアカルの方を向き直った。「イスズ様の貴いご意志と同じく、この争いを収めるため、わたしたちも命を捧げます」
四人のキビの巫女たちは、頭を深く垂れた。
「わたくしも同じ気持ちです」と、クシナーダは応え、みずからも深く頭を下げた。
そんな若い巫女たちを見ていたナオヒが言った。「それだけでは不十分」
「ナオヒ様?」クシナーダを振り返った。
「そなたらがカガチに反旗を翻したところで争いはなくならん。カガチを止めねば」
「たしかにおっしゃる通りですね」
「あのモルデという者が首尾よくエステルを説得できたとしよう。しかし、カガチはかならずカナンを滅ぼそうとするであろうし、カナンが撤退したところで、カガチの思惑はこの島国全体の制圧にある。いずれは東国やツクシも争いに巻き込んでいくであろうな」
「カガチを倒さねば解決はしないということですね」アナトが言った。「この戦いと洪水でのキビの被害は甚大です。ですが、本国に戻れば、まだある程度の兵力は集めることができます」
「そのような悠長なことをしておれるのかな。そなたらはヨモツヒサメのことを軽く考えておる。あの者どもは人の憎悪や怒りを吸うだけではない、この地上にそれをばらまく」
「ばらまく?」
「ばらまかれた憎悪は人の中で増殖して、いっそう大きなものとなる。それをまたヨモツヒサメは食らう……。魔の循環じゃ。そうして肥え太った〝負〟の力は、たちまち破滅を引き起こすじゃろう。そこへ至るまで、多くの時間があるとは思わぬことじゃ。まして――」ふっとナオヒは笑った。「カガチを並みの兵力で倒せるはずもない」
「カガチはあの剣を得て、その〝力〟によって鬼と化しました」アカルが言った。「あの〝力〟がある以上、並大抵の手段ではカガチを制することはできません」
「剣を奪い取っては?」と、イズミが言った。
アカルは首を振った。「もはやカガチは鬼神の〝力〟と一体化しております。剣を離すことができても、カガチにはもはや何の変化もないでしょう」
「鬼となった者を救う手段はない」ナオヒが珍しく重い口調で言った。「殺す以外は……。しかし、そのために兵を動かしても、おそらく今はヨモツヒサメの格好の餌食となるであろう。闇に取り込まれ、闇に使役され、よりいっそう世の破滅の助力となろうな」
「カガチを制することができるのはスサノヲだけです」クシナーダが言った。「スサノヲの帰りを待ちましょう。そのとき、いつでも行動を起こせるよう、準備を整えておくのです」
沈黙が落ちた。その中、すっとアカルが立ち上がった。まだ足元もやや頼りない様子ながら、イスズのそばに行き、かけられた布をめくり、しばし、その顔を見つめていた。
「一つだけ、手段がございます。カガチのことは、わたしにお任せください」
その言葉はイスズに対して囁かれたものでもあったようだった。
――そして。
スサノヲは意識を取り戻した。建屋の隙間から差し込む朝の光が眼に痛かった。
鉛が身体に詰め込まれたように重かった。呼吸をして、息を体内に送り込むことさえ、苦労が伴った。
「気が付いたか」
声が聞こえた。逆光の中に人影が揺れた。
4
「気が付いたか」
その人影が発する声には聞き覚えがあった。そばにやって来ることで光の当たる角度が変わり、顔が見えるようになった。
カイであった。ほかにもカナンの兵士たちが一緒にいる。皆、スサノヲの剣圧で吹き飛ばされた者たちだった。
状況が見えず、スサノヲはしばらく自分たちがいる小屋の中を見まわしていた。
「このまま死んじまうのかと思ったぜ」
気力を奮い起こさねば、身体を起こすこともできなかった。これが我が身がと疑うほど力がなく、四肢が重かった。
ざーっと、スサノヲの胸元から何かが落ちた。不審に思ってみると、それは白い砂のようなものだった。指で触れ、確認する。どうやら塩らしかった。汗が乾いたのかと訝(いぶか)ったが、そんなことで説明できるような量ではなかった。
見ると、塩が零れ落ちた胸元には、青黒い大きな痣のようなものがあった。ヨモツヒサメに貫かれた場所だった。
「なにがあったんだ。あんたがこんなふうになっちまうなんて」
問われ、スサノヲは眼を細めて記憶をたどった。
あの土石流が襲い掛かって来た瞬間。
反射的にスサノヲは岩から岩へ飛び移り、洪水から逃れようとした。常人には不可能な跳躍だった。だが、ヨモツヒサメから与えられたダメージはあまりにも大きかった。抗いがたい脱力感に見舞われ、意識を失いかけ……。
羽ばたき。
ぐいっと上空へ引っ張り上げられる力。
最後に認識したのは、それとともに見た大烏の面をつけた男の姿だった。その背には巨大な翼があった……。
サルタヒコであった。その実体を一瞥するのは初めてだったが、スサノヲには自分の手を引っ張り上げているのが、いつもカラスを通じて話しかけてくるあの神だとはっきりわかった。
「俺はどうしてここに?」スサノヲは逆に尋ねた。
「どうもこうも、俺たちが進む先に転がっていた。岩の上に」
「助けてくれたのか、俺を」
カイは戸惑ったように仲間を振り返った。「ま、まあな。あんたも俺たちを助けたっていうか、殺さずに済ませてくれたからな」
スサノヲを見つけたときの彼らの狼狽や逡巡ぶりが目に浮かぶようだった。おそらくどうするか、話し合ったのだろう。背後に置き去りにしてきたはずのスサノヲが道行の先に出現したのも不可解だろうし、助けるという行為がカナンにとって利益となるのかという問題もあっただろう。
「ちょうど日が暮れて、この山小屋が見つかったところだった。たぶんこの峠を越えるとき、夜露をしのぐために作られたものだろう」
「すまない。ありがとう」スサノヲは礼を言った。
彼らの戸惑いはさらに深くなったようだった。
スサノヲは周囲を見まわした。そばに剣は鞘に収められ、立てかけられていた。
「剣はしっかり握りしめていたよ」
カイたちは事情をさらに説明した。彼らは洪水が起きたとき、川からは距離を取って迂回路を進んでいた。トリカミが近づくにつれ、オロチ軍との遭遇の危険が増すからだ。それが結果的に彼らの身を守った。
「夜も明けた。俺たちはイズモのエステル様のところへ合流する。あんたはどうする――」と、言いかけたときだった。
外の様子を隙間から窺っていたカナン兵のひとりが、「静かに」と声を上げた。カイたちは敏感に反応し、剣に手をかけた。カイも戸口に移動し、覗きこんだ。
スサノヲも動かぬ体を叱咤し、剣を腰に収めた。
信じがたいものを目撃したというように、カイが低い驚きの呻きのようなものを上げた。目がみるみる大きく見開かれる。「に……兄さん。兄さん!」
叫んだときには彼は、戸口を大きく開いていた。外へ向かって飛び出していく。
そこにはモルデとカーラがいた。
奇跡的な再会を果たした兄弟の感激ぶりは、たがが外れたようなものだった。二人とも涙を流して抱き合い、存在を確かめ合っていた。カイはすでに兄は死んだと思っていたし、モルデもまたこのような場所で弟たち同胞に出会えるとは、夢にも思っていなかったのだ。
だが、それにも増してカイらを驚かせたのは、先の洪水が南から攻め込んできたオロチ軍の大半を壊滅させたということ、そして――。
「失われた支族がこのワの国へ来ていただって?!」
それは天地がひっくり返るほどの衝撃だった。
「イスズ様はあなた方が争いをやめるのであれば、ヤマトへあなた方をお迎えするお心積もりです」カーラはそう告げた。
浅黒いカーラの顔立ちは鼻筋が高く、全体に容貌がカナンの民に似ていた。その顔をカイたちは食い入るように見つめていた。
「俺はエステル様に進言するつもりだ」やせ衰え、頬もそぎ落とされたようになっていたが、モルデの眼だけは強く輝いていた。「皆でヤマトへ行こう」
もともとオロチとの戦いでは、すでに意見が割れていた彼らだった。あくまでも徹底抗戦を訴えるカイに対して、シモンやヤコブは半島へ撤退することを主張していた。ほかの二人は立場を決めかけていた。そのような状態の彼らでさえ、このプランは丸ごと包括してしまえるものだった。
「失われた支族がいるのなら……」
「そうだ。願ってもない」
「行こう、ヤマトへ」
ワの地へ侵攻して以来、彼らは戦い続けていた。オロチとの厳しい全面戦争になり、敗退を続け、今や膿み疲れも生じてきていたのだ。いきなり希望の灯がともったように、彼らの眼に輝きが戻ってきた。
「ただ……」モルデは言いかけた。
「ただ、なんだ、兄さん」
「いや、このことはエステル様に直接お話する」
「わかった。とにかく本陣に合流しよう。ここからなら今日の内には本陣へ合流できる。スサノヲ、あんたはどうする。トリカミへ戻るの――」
カイの言葉は途中で切れた。スサノヲは山小屋の建つ峠の見晴らしの良い場所に佇んでいた。イズモの地が遠望できる。眼下に斐伊川が流れ、その向こうに小高いいくつかの山が連なっていた。
そこに彼の眼は、常人の肉眼では確認できない、異様なものを視ていた。その上空に暗雲の如きものがあった。それは恐ろしく禍々しい鬼気をはらみながら、生物のようにうごめき続けていた。そこから、まるで黒い雪のようなものが地上に降り続けているのが視えるのである。
胸を締め付けるような不快感。口の中が金属的な味わいで満ちてくる。
ヨモツヒサメに違いなかった。
羽ばたきと共に、近くの木の枝にカラスが止まった。
――何ガ起キテイルノカ、ソノ眼デ確カメヨ。
サルタヒコが伝えてきた。
「俺も一緒に行く」振り返ってスサノヲは言った。「カイ、エステルは無事なのか」
「あ、ああ。まあ、そのはずだけど」カイはいかにも歯切れが悪かった。
「どうした、カイ。エステル様に何かあるのか」と、モルデが尋ねた。
「うん……。まあ、会えばわかるよ。ちょっとこのところエステル様、元気がないっていうか……まあ、それは兄さんの顔を見たら、きっと元気になられると思うよ」
スサノヲは、本音ではトリカミへ戻りたかった。クシナーダが今どうしているかと考えたら、居ても立ってもいられない心地になる。だが、カーラの話によれば、トリカミを占拠しているカガチとオロチ軍は、洪水の被害を受けた仲間の救助に追われている。態勢の立て直しに血眼になっているという話だ。
そして、クシナーダもほかの巫女たちと共にトリカミにいる。
今しばらくの時間の猶予はあるように思えた。身体さえ復調すれば、トリカミとイズモの間の距離など、さして大きな問題ではない、とスサノヲは判断した。ヨモツヒサメから受けたダメージがいかほどのもので、回復に要する時間がどれほどなのか、自分でもはかりかねていたが、今はイズモで何が起きているのか、見定めなければならなかった。
そう決断せざるを得ないほど、嫌な予感がした。おそらくサルタヒコがカイたちの前にスサノヲを下ろしたのにも、深い意図があると思われた。
谷間に沿った獣道を下り、一行は斐伊川に出た。
そこはすでにカナンの勢力圏であり、彼らは防衛線を張っている守備兵たちの手厚い歓迎を受けた。ことにモルデの帰還は熱烈な喜びを持って受け取られ、彼らは現在のカナンの本陣のある場所へ案内された。小舟で川を下り、山を迂回する形で、夕刻にようやく辿り着いたその場所は、複数の小高い山のすそ野であった。(現、神庭谷付近)
そこでスサノヲは信じがたい光景を見た。
近づくにつれ、山々を揺るがすほどの歓声が轟くように聞こえてきた。それはまったく意外なことであり、オロチ軍に徐々に追い詰められ、総攻撃を受けて崩れた兵士たちの発するものとは思えなかった。
山あいに陣を張るカナン軍には、まだこれほどの数がいるのかと驚かされただけではない。彼らは熱狂していた。まるで大戦(おおいくさ)に勝利したばかりのような、とてつもない興奮と喜びが里に満ち満ちていた。
「なんだ、これは……」
カイやモルデでさえ、この狂乱ぶりには戸惑った。
その中心にいたのは、刀傷を顔に持つ、隻眼の男であった。
「ヤイル……」モルデが呻くように言った。
岩場の上に立ち、演説している背高い男はヤイルだった。彼の身振りで兵士たちは静かになった。
「聞け! カナンの民たちよ! 神に選ばれし同胞よ!」
ヤイルの声が響き渡る。
「野蛮なる民どもの軍勢には神の鉄槌が下された! 我が予言通り、大水が彼らを滅ぼした! そなたらは見たであろう!」
おお!! と兵たちの声が返す。
「これこそが神の御業である! 神は私にお約束された! はっきりとお言葉をくださったのだ! 我らにこの島国すべてをお与えになると!! こここそが神のお約束された第二の地! 恐れるものなど何もない! 我らには神がついておられる! 愚昧な異教徒どもなど恐れるに足らぬ! 聞け、民よ! カガチは神の火によって焼かれるだろう! これは神の御言葉である!」
うおおおお――という轟きがまた湧いた。
「皆、耳を澄まして聞くがいい! タジマは間もなく裏切りに遭い、崩れ去るだろう! 真の神への信仰を持たぬ者どもの結束などなきに等しい! 彼らは憎しみ合い、結束は乾いた地の石くれのように脆くなる! もはや我らの敵ではない! キビもまた恐ろしい災厄に見舞われるであろう! 五つの地の邪教の巫女は互いに憎しみ合い、残らず死に絶える! 我らはもはや彼らを打ち倒した! その未来が我が眼には映じておる! そしてこの島国には我ら民が増え、ありとあらゆる地で栄え続けるのだ!」
地の底から噴き上がってくるような熱気と共に兵士たちはまた怒号のような喚声を上げ続けた。目の当たりにして、スサノヲは珍しく血の気が引くような心地を味わっていた。うすら寒さに皮膚が粟立ってくる。見渡す限り埋め尽くす群衆には理性の働きは微塵もなくなり、盲信的な思い込みだけが膨張し、そしてこの地で一つの意志となって結びつき、さらにいびつで異常なものとなって、今まさに生れ落ちようとしていた。
茜色に染まる空には、今は雲一つなかった。だが、スサノヲはその上空に視ていた。悪意に満ちた闇の存在を。
――オマエノ見タイ神ヲ見ヨ。
――オマエノ考エル神ダケヲ信ジロ。
――他ノモノハスベテ滅ボセ。
――認メルナ。
――否定シロ。
――否定シロ。
――ソシテ殺セ。
――殺セ。
――ソレガ正シイノダ。
――正義ヲ為セ。
ヨモツヒサメから降りかかってくる思念は、ヤイルの身体にどんどん吸い込まれていた。彼の隻眼は異様な光を放ち、彼が見渡す群衆を魅了し、魂をわしづかみにして力づくで引きずり込んで行く。魔の渦の中に。
「おい! これはいったいどういうことだ!」モルデが近くにいた兵の肩をつかみ、問いかけた。
「どうもこうもあるか。ヤイルが予言したんだ。トリカミから来るオロチが大水で滅びると。それが的中した! ヤイルは予言者だ! 我らの新しい予言者にヤイルはなったんだ!」
その兵士は涙まで流していた。喜びのあまり震えている。狂気じみた喜悦の顔だった。
「エステル様は?!」モルデは詰問した。
「エステル様?」
「エステル様はどこだ!」
男はすっかり忘れていたというふうに、ようやく記憶を紡ぎ出した。「ああ、ああ、エステル様……エステル様か。たぶん幕屋にいるだろう」
その男を突き飛ばすようにモルデは歩き出した。カイら帰還した兵士と、カーラ、そしてスサノヲもついて行った。歩きながらスサノヲは上空のヨモツヒサメに意識を向けていた。
ヨモツヒサメのほうでもスサノヲのことは認識しているようだった。しかし、このヨモツヒサメはスサノヲに格別な関心はないらしく、攻撃的な意識は見えなかった。むしろヤイルを通じ、カナンの民を扇動することにのみ関心があるかのようだった。
こんな化け物どもが世に出ていたら……凍りつくような想いが湧いた。
地上に平和など望むべくもない。争いと憎しみが地に満ち、累々たる死体の横たわる、この世は本物の地獄と化すだろう。その世界ではもはや亡霊や怨念、死神ばかりが跳梁し、渦巻いているのだ。
心底ゾッとなり、スサノヲは想像を頭から追い払った。
こうなっては、なにがなんでもエステルにこの戦いを収めてもらわなければならなかった。
幕屋には衛兵すらいなかった。誰もがヤイルの元に馳せ参じているのだ。その場には、置き去りにされた何か冷たくて空虚な印象さえあった。
その中にエステルがいた。かつてとは見る影もなく憔悴した顔に、濃厚な憂悶を漂わせ、視線を足元に投げ出していた。人の気配は感じたであろう。が、彼女は眼を上げもせず、腰かけた姿勢のまま、銅像のように固まっていた。
「エステル様……」モルデが枯れたような声を発した。
びく、とエステルの身に震えが走った。眼が上がり、そして宙をさまよい、目の前にいるモルデの姿を捉えた。
「……モ、モルデ……?」見えない糸に引かれるようにエステルは立ち上がった。「本当にモルデなのか? おお……おお……モルデ!」
両手を捧げるように前に出し、エステルはまるでぶつかるような勢いでモルデに抱きついていった。
5
黎明の空に、二つの星の輝きがあった。クシナーダは収容されている家屋の戸口に立ち、その星の輝きを見つめていた。疲れ切った他の巫女たちより先に目覚めたアナトは、クシナーダのその様子に気づいた。
「おはようございます、クシナーダ様」
他の者を起こさぬように気づかい、アナトは小さく声をかけた。クシナーダも挨拶を返してくる。
「しばらく前から不思議に思っておりました、あの星……」アナトは言った。「わたしたちがいつも見るものとは違っています。赤の星でもなく、一つ目の大きな星でもなく、輪の星でもなく……あのように明けの明星のそばで輝く星を私は知りませぬ」
「天津甕星(あまつみかほし)……スサノヲの星です」
「スサノヲ様の……? まだお会いしたことはありませぬが、直接天より降られたとお聞きいたしました。わたしたちワの民が伝える物語の荒ぶる神と同じ名を持たれている……まさしく霊妙なることでございます」
「スサノヲは破壊と再生をもたらす〝力〟だと、アシナヅチ様が申されておりました。そのため常に両面を持つと」
「両面?」ドキッとしたようにアナトはおうむ返しに言った。
「破壊者と創造者です。大陸の南方の土地では、シヴァという神が祀られています。破壊と創造の神ですが、そのシヴァは踊る神なのです」
「踊る神?」
「なたらーじゃ……とも呼ばれています。彼の踊りは世界を破壊し、そして再生させます。シヴァはその地でのスサノヲの働きの表現なのです」
そのような知識を一体どこから得るのかと訝り、アナトはその考えが愚問に近いと思いなおした。クシナーダやアシナヅチの知覚能力は空間や時間を簡単に超えてしまうからだ。
「もしかするとカガチとスサノヲは一対のものなのかもしれません。天津甕星はきっとスサノヲの〝力〟が顕れる験(しるし)なのです」
「わたしはあの星に畏怖を感じます」
「はい。でも、わたくしは今、あの星を見て、安堵していたのです。あの輝きがあるということは、スサノヲの命の輝きもまた失われてはないということ」
「クシナーダ様の御力なら、スサノヲ様のご様子もご覧になられるのでは?」
クシナーダは首を振った。「結界が張られ、聖域化されているこの里の中ならいざ知らず、今結界の外へ意識を飛ばせば、ヨモツヒサメに心を食われかねません。ただ感じるのです、スサノヲが苦しみながら道を進んでいることを」
「お怪我をされているご様子ですが」
「ただの怪我ではないでしょう。おそらくスサノヲはどこかでヨモツヒサメに遭遇してしまったのです。でなければ、あのような傷を受けるはずもありません」
「強いお方なのですね」
「はい……」
「それに離れてらしても、クシナーダ様はスサノヲ様のことを手に取るようにわかっておられるようです……その……」アナトはある言葉を呑み込み、別な表現を選択した。「クシナーダ様はスサノヲ様を信じておられるのですね」
クシナーダはうっすらと微笑を浮かべた。その表情には愛する乙女の喜びのようなものが滲んでいた。そして、「はい」と静かに強く答えた。
「アナト様」
「はい」
「わたくしたちは踊らねばなりません」
その言葉に、アナトはしばらく前にアゾの祭殿で受けた啓示と、そして現れたウズメの神霊から告げられたことを思い出した。
「御霊を集め、浄めよ……。魂で踊り、ワのヒビキでこの世を埋め尽くせ……」
「その通りです。このワの国では、わたくしたちが踊らねばなりません。ワの民は――いえ、人は――歌と踊りでつながり合えます。わたくしたちが昔からこの地でそのようにしてきたように、歌って踊って……天の岩戸を開き、そしてこの闇を払わねばなりません。でなければ、きっとこの国の子らの未来もありません」
「わたしも及ばずながらお力になりとうございます」
「アナト様なくして、きっと岩戸は開かれません。お願いいたします」
クシナーダに頭を下げられ、アナトは狼狽した。「そ、そんな――クシナーダ様、お顔をお上げください」
そんな二人のやり取りを、目を覚ましたアカルが見ていた。アナトはクシナーダよりも六、七歳は年上だが、まるで目上の者に相対するように尊敬の想いを隠さなかった。それはアナトらキビの巫女たちが、結果的にこのトリカミに与えた被害に対しての罪障感を持っているからだけでは決してない。
それはアカルが一番よく知っていた。彼女が、最初にクシナーダにあいまみえたのは六年前だった。カガチがイズモに支配権を広げ、ワの民たちの反撥を抑圧するため、トリカミの巫女を毎年一人ずつ人質にし、挙句に殺すという蛮行に手を染めるようになり、二人目の巫女を連れ去ったときだった。
アシナヅチから打診を受けて、アカルはトリカミに出向いたことがあった。むろんカガチを抑えるための何らかの手段を講じるためだった。この会談はカガチに察知されるところとなり、アカルはその後、タジマに幽閉されてしまうという結果を招くのだが、クシナーダに出会ったこと自体は、アカルにとって非常に衝撃的な出来事だった。
まだ十歳くらいの幼い巫女に過ぎなかったクシナーダは、それ以前も以後もアカルが知るありとあらゆる巫女の次元を越えていた。すでに千年二千年という先を透視し、世界の裏側にいる人々とも交流を持つことができた。
「あなたはお母さんね」クシナーダは一瞥して、アカルにそんなことを言った。
「お母さん?」
「あなたがお母さんに見えるの。きっと大事な人」
その瞳が見ているものは、アカルにはまったく想像もつかなかった。が、少女の精神がこの世の現実の枠をはるかに超越していることは、圧倒的な霊的なヒビキによって伝わってきた。
だが――。
アカルは、少女だったクシナーダの言葉の意味が今ようやく氷解したのを知った。イスズの命が消え去るとき――キビの巫女たちやナオヒが共有していたヴィジョンが、アカルにも飛び込んできた。
少年カガチの母、それはアカルによく似た女性だった。冠島に漂着したカガチが、アカルの顔を見て驚愕したのは、大陸で失った母の面影をそこに見たからにほからない。それが理解できた瞬間、アカルの中でドミノが倒れるようにして、霊的な情報が解き放たれた。
それはカガチと自分との情報だった。
カガチは母親に愛されなかった。母親が溺愛していた兄を事故で死なせてしまったからだった。以来、母はカガチに感情のない冷めた目を向け、呪いのような言葉を与え続けた。
おまえのせいだ。おまえなど生まれなければよかった。
カガチは渇望する母の愛の代わりに、その呪詛を受け続けて生きてきた。やがて起きた戦乱で家族を皆殺しにされ、生き残り、辿り着いた島国で出会った巫女。
そこにまた亡き母の面影を見てしまった。
毎年巫女を殺し続けるカガチの深層にあるものまでもが、アカルには我がことのような痛みとしてわかった。
自らの肉体に鬼の種子まで育てたカガチの根にあるもの。
それは、愛されたい、生きたい、という熾烈なまでの欲望だった。その欲望こそが彼の鬼の根源であった。解き放ったのは霊剣の〝力〟だったかもしれないが、救いのない彼の行く末はいずれ似たところへたどり着いたであろうと思われた。
そして――。
それを救うのは自分でなければならなかった。
アカルがカガチの命を救い、巫女としての予感に逆らい、彼を登用しようとする父にも警告を与えず、今の状況を作り出してしまったという責だけではない。ましてやアカルの面差しが、カガチの亡き母に似ているからというのでも、もちろんない。
もっと根深いものが、アカルとカガチの間には横たわっていたのだ。
「あら、アカル様――」クシナーダはアカルに気づき、すぐに扉を閉めてアナトと共に室内に戻ってきた。「お目覚めでしたか。すみません、お寒うございましたか」
「いえ、大丈夫です」
「お顔色が随分とよくなられました」と、アナトも安堵の色を浮かべた。
「皆様のおかげです」
他の巫女たちも話し声に誘われるように、次々と目を覚ました。昨日は彼女らの手でイスズを弔った。そのこともあったし、その前夜からの強行軍もあって、彼女らも疲れ果てていたのだ。
しばらくして食事が運ばれてきた。トリカミの里の者が命じられて、囚われの巫女たちの食事のまかないを行っていた。食事を運んできたのはスクナだった。彼女は見張りに立っている兵士に戸口を開けてもらい、身に余るような大きな木の板に七人分の器を乗せて運んできた。野草や根菜がふんだんに入れられた粟の粥であった。
スクナと目が合うと、クシナーダはその瞳の中だけで笑って、うなずいた。配膳している最中に、スクナに囁く。
「戻ったのですね。イタケルやオシヲ、ニギヒ様は?」
スクナも小さく返した。「里の近くの洞窟に隠れてる。イタケルやオシヲは顔が知られているかもしれないし、ニギヒ様はあの通り目立つから」
「そうですね」くすっとクシナーダは笑った。「スサノヲはやはり一緒ではないのですね」
「うん。することがあると言って別れたまま」
「スサノヲの気配は北のほうにあります。たぶん、カナンの本陣のほうでしょう。そこへモルデとカーラという者が向かったはず」
「知ってる。会ったよ。じゃ、スサノヲも一緒かもしれないね」
「そんな気がします」
「おい!」見張っているオロチの兵が怒鳴った。「さっさとしろ! 用が済んだら出ろ!」
彼らはカーラが食事を運んだあと、イスズが抜け出した前例から警戒を強めていた。
「ちょ、ちょっと待って」スクナが言った。背後に手を回し、腰紐にさしていた花の枝をクシナーダに差し出す。「これ、イタケルが持って行けって」
まあ、とクシナーダは眼を見張った。「覚えていてくださったのですね」
それは鮮やかな紅色をした椿の花だった。五弁の花びらが大きなめしべを包んでいる。その明るい色合いは、閉塞感が立ち込めていた室内の空気を変えた。
「生まれた日に、その季節の花を贈るのが、この里のならわしなんだ」と、スクナが兵士に説明した。
子供にそう言われ、兵士たちは戸惑いつつ、返す言葉もなかった。
「クシナーダ様は今日がお生まれになった日なのですか」と、アナトが尋ねた。
「はい。とても祝っていただく状況ではありませんが……わたくしはこの一年でもっとも日が短い日の生まれです」クシナーダは眼を細めて、椿の花の色と香りを味わった。「ありがとう、スクナ。イタケルにもお礼を言ってね」
スクナはにっこりしてうなずいた。クシナーダは立ち上がる際に、その耳元に顔を自然に近づけてまた囁いた。
「この花弁がすべてなくなった夜、わたくしたちはここを出ます」
スクナは返事をしなかった。が、聡明な彼女は眼だけで了解したことを伝えてきた。
「また、ごはんを持ってきて頂戴ね」
そう言って送り出すクシナーダに、「うん」と返事をしながらスクナは出て行った。
子供ゆえに気を許しているということもあるのだろう。兵士はさして訝りもせず、スクナが出ると扉を閉めた。
「さあ、いただきましょう」と、クシナーダは明るい声で言った。
「クシナーダ様……今の子と何を……」近距離にいたアナトは、わずかながらやり取りを耳にしていた。
クシナーダは眼を悪戯っぽくきらきらさせながら、指で押し黙るように合図して、椿の枝を家屋の隅にある間口の狭い土器に差した。それに水も差しておく。それからそっとつぶやいた。「スクナはこれから毎朝毎夕、食事を運んできてくれるでしょう。椿の花びらを状況に合わせ、一枚ずつちぎっておきます。すべてなくなった夜にここを出ましょう。そのための合図に使うのです。いつも話せるとは限りませんから」
「え……しかし、どうやって」
「心配いりません。スクナが戻っているのなら」
「え……」
「でも、花がかわいそう……」と、クシナーダは椿を振り返った。「本当は椿は花びらを散らさず、落ちるときは花が丸ごと落ちるんですけどね」
巫女たちはきょとんとしていたが、一人、ナオヒだけがにやにやしていた。
「ナオヒ様、このようにお謀りになって、スクナの身を守るためにニギヒ様と共に里の外へお出しになったのですか」と、クシナーダは視線を送った。
「そなたほどではないがの」ナオヒは細い腕で器を取りながら言った。「なんとなく、あの子を逃がしたほうが良いと思うたのじゃ。スサノヲとの縁が深そうじゃしな」
「やっぱり」クシナーダはにっこりとした。「ナオヒ様はお人が悪い」
「そなたほどではない」
二人は声をあげて笑った。他の巫女たちは戸惑いながら、苦笑のような表情になった。
獣のような唸り声がしていた。
トリカミへ来て、三度目の夜だった。ヨサミは毎夜、その唸り声を耳にしていた。いや、もしかするとイスズという巫女が殺されて以降というべきなのかもしれないが、トリカミに根を張って以来、あきらかにカガチの様子はおかしかった。
常識では推し量れないほどの体力を持つカガチだったが、それ以前はいかなる戦があっても、眠れないなどということはなかった。戦闘で高揚した肉体を持て余したようにヨサミの身体を抱き、そして熱を冷ますと満足して眠りに落ちた。それは飢えた猛獣が腹を満たして眠るのと同じようものだった。それが常だったのだ。
しかし、トリカミに来て以来、カガチはおかしくなってしまった。熟睡することもできず、何かに責めさいなまれるように、浅い眠りの中でうわ言を口走るようになった。母さん、というはっきりとした声もヨサミは幾度も聞いた。そしてまた獣のような唸り声を発して目覚め、不機嫌に荒い息とぎらついた眼を周囲に放つ。そんなことばかりだった。
その夜、ヨサミは不安に襲われた。隣で身体を横たえているカガチは、もはやうわ言のレベルではない、はっきりとした苦悶を表わす声を上げ始めたからだ。肉体を蝕む不治の病の痛みにでも襲われているように、彼は唸り、のたうち、吠えた。
「カガチ……カガチ様!」褥を共にする者が死ぬのではないかという恐怖に襲われ、ヨサミは彼の身体を揺さぶった。
カッ、とカガチは眼を開いた。充血しきった眼だった。
「いかがなされました」
その眼が動き、ヨサミの顔を捉えた。ううう、という唸りと共にカガチの身体は跳ね上がり、そして一瞬にしてヨサミの身体を組み伏せていた。
今下を見ていたのに、あっという間にヨサミの眼は上を見ていた。そこにカガチの鬼の形相があった。彼のものすごい腕が伸び、万力のような両手が首に巻き付いてきた。大蛇が瞬間的な動きで敵を締め付けるようなものだった。
ぎゅうっと締め付ける力が首を圧迫し、ヨサミは両手両足をばたつかせた。苦しいというようなレベルではなかった。涙や血液といったものが、頭部の涙腺や毛穴から圧迫されて噴き出しそうになる。頭が破裂すると本気で感じた。
だが、すぐに意識が遠のいて行った。
死ぬのだ、とヨサミは思った。すとんと胸に落ちたのは、この怨讐にまみれた自分にふさわしい最期だということだった。
顔にかすかに何かを感じた。それは首を絞めながら目の前に迫ってくるカガチの顔から落ちてくる涎や、そして――涙であった。
この人も寂しいのだ。
悲しいのだ。
辛いのだ。
そう思った。
いいよ、殺して。
わたし、あなたに殺されるのでいい。
ヨサミは死の淵に落ちながら、どこにそのような力があったのか、その両手でカガチを抱いていた。いや、カガチの巨躯は彼女の両腕の長さでは、とうてい抱きしめることなどできなかった。そっとその胴に手を回すことしかできなかった。
しかし、それは彼女にとって、カガチを抱くという行為だった。
「うおッ――」カガチが怯えたような声を発し、突き飛ばすように離れた。
一瞬あと、呼吸と血流が戻った身体が、反動のように激しく咳き込み始めるのを感じた。うっ血で青黒くなりはじめていた顔に血の気が戻ってくる。涙も止まらなかった。
ややあってヨサミは、そこに見た。
鬼神が吠え、壁に頭や拳を打ち付ける様を。カガチの力が強すぎ、建物自体が倒壊しそうだった。
ヨサミは褥を抜け出し、荒れ狂うカガチに近づいて行った。
そして、その背後から彼を抱きしめていた。
なぜ、そんなことをしたのか、自分でもわからないままに。
小説 ブログランキングへ
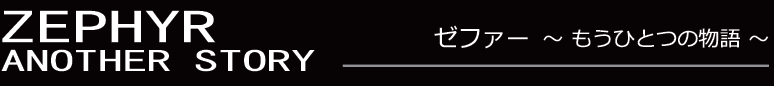







0 件のコメント:
コメントを投稿