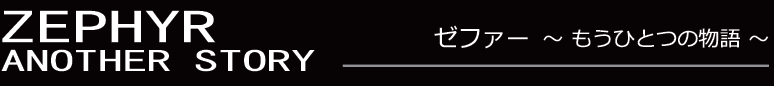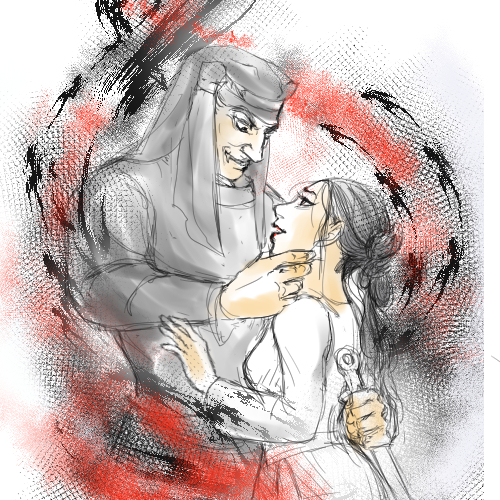1
二年後――。
エステルの姿は日本海を航行する船の甲板上にあった。潮風が彼女の髪をかき乱し続けている。同じように彼女の心はかつてなく高ぶっていた。
「いよいよですな、エステル様」と、ヤイルが隣で言った。
屈強な中年の男だ。額から左眼にかけ、刀傷が生々しく残っているのは、スサの探索中に受けたものだった。むろん左眼は失明している。
ああ、とエステルは低く応え、腰に帯びた剣の柄に左手を置いた。弟、エフライムが使っていた形見の剣だった。二人の視野には島国の青くかすんだ姿が、しだいに、しだいに大きくなりつつある。それとともに彼らの期待は否応なく高まり、胸のざわつきが抑えがたいほどだった。
「あれです。あれが目印です」カイが指差す。
大きな島国の手前にちっぽけな島があった。
「おーい、もう少し東だ!」と、カイは位置を確認して叫ぶ。櫂を漕ぐ者たちが「おお」と言葉を返す。
彼らが選んだのは、大陸の半島から近いツクシという島ではなく、東に横たわる大きな島国の北岸だった。その後もカイの誘導で、舟は刻一刻と目的地に近づいていく。
やがて陸地で男が叫んでいるのが目に入った。モルデである。彼が満面の笑顔で手を振っていたが、潮風にかき消され、声は耳には届かなかった。
船は川を遡上して行く。エステルはそれにつれて見えてくる島国の様子、それにしゃにむに船と一緒に駆けてくるモルデを見ていた。
「エステル様――!!」
ようやくモルデの声が耳に届くようになる。周囲の眼を忘れ叫び返したい衝動を抑え、エステルは接岸を待った。
「兄さん!」
船首まで出て行き、弟のカイが叫ぶ。モルデとは四つ下のカイは、また若干、少年っぽさをとどめる若者だった。
船が接岸するとエステルは真っ先に下船し、桟橋を渡り、陸地を足で踏みしめた。
「エステル様――」モルデが前にひざまずく。
「モルデ、ご苦労」
労をねぎらう以上のことも口にしたかったし、目もしっかりと合わせたかった。が、エステルはあえて歩みを止めなかった。港近くに小高い場所があり、そこからの景色を眺めたかった。
――それにしても、とエステルは思う。
美しい。
その想いは、丘の上に出ると、いっそう深いものになった。大陸の広大な風景とはまったく異なる。こぢんまりとはしているが、豊かで、何か神が作った小庭のような景観だ。周囲を取り囲む山々は、いずれも険しくなく、濃い緑に覆われていた。あまり目にしたこともないような鮮やかな赤や黄も山々を彩っている。入り江に流れ込む河川は清らかで、そしてその周辺には背を伸ばす植物たちが見える。
葦だった。
水中から何百何千もの細い茎が生え、風に揺られていた。
葦の原がそこに広がっていた。
しばし呆然と、エステルはその景色を眺めていた。
自然と涙があふれ出た。
「エステル様……」そばに来ていたモルデが、遠慮がちな声を発した。
「カイから報告を聞いておる」エステルは流れ落ちる涙さえ意識せず言った。「葦の原と呼ばれる美しい国だと。このワの国は、葦の原の国だと」
「われらが祖国も、かつては葦の原……カヌ・ナーと呼ばれておりました」ヤイルが言った。
そう。それが「カナン」という呼び名の由来だった。
「われらが探し求めていた〝もう一つの土地〟――もう一つのカナン」
つぶやくエステルの脳裏に、ここへ至るまでのすべてがよぎって行った。侵略によって国が亡び、神殿も街も焼き払われ、男は殺され、女は犯され、そんな中を命からがら逃げ延び、弟エフライムを喪い、はるか長い大陸の道を、仲間を引き連れ、踏破してきたことを。
荒涼とした土地を旅する中、多くの者が病で亡くなり、ある者たちは脱落してその土地に根付き、ある者は戦って死んだ。
大陸の極東に至り、そこから先にもはや土地はないと知った時の絶望感。そして、東海に理想郷があるという、伝説のような話を聞いたときの、一縷(いちる)の望み。
ホウライと呼ばれる伝説郷は、あくまでも伝説でしかなかった。しかし、情報を集めれば、海を東に渡ったところに、さらに国があることはたしかだった。
――ひたすらに東に向かい、世界の果てにたどり着くことじゃ。
メトシェラの言葉だけが、常に心の支えだった。このときもエステルは、藁(わら)をもつかむ心地で、最後の選択に賭けた。
東海にあるというワの国。そこにもっとも近接した半島までたどり着くと、エステルはモルデとカイの兄弟を核とした先発隊を放った。そして、数日前にカイが戻ってきて報告したのだった。
「ワの国は、葦原の国とも呼ばれております。本当に葦の原が広がる美しい国にございます!」
今、エステルは自分の眼でその言葉を映像として確認していた。
感極まってエステルは、弟エフライムの剣を抜いた。そして、足元に深々と突き立てた。振り返る。そこにはモルデら先発隊、そしてたった今下船してきたばかりの大勢の仲間、カナンの民が集まっていた。
「皆の者、よく聞け!」エステルの号令は、全員の肺腑(はいふ)を震わせるものだった。「我らはこの地に、新しいカナンの国を打ち建てる! ここ以外に〝もう一つの土地〟はあり得ぬ。いや、こここそが神のお約束された、もう一つのカナンの地なのだ!!」
一瞬、間があった。それはエステルの信念が波動となって、全員の心にしみわたる空白だった。しかし、その後、彼らの心から噴き上がってくる熱はすさまじいものだった。
――おお!!
エステルの宣言に応え、彼らは一つの生き物のように声を発した。
「まずはこの地に前線基地を築く! 半島に残してきている仲間を呼び寄せ、ここを拠点に勢力を広げ、やがてこの島国すべてを、我らの支配するところのものとするのだ!」
再び、おお! という声が上がった。
「さあ、家を作れ!」参謀格のヤイルが命じる。「食べ物も獲ってこい! 今宵は宴ぞ!」
ヤイルは民を集め、指示を与えはじめた。カナンの民たちは、精気に満ち溢れていた。一人残らず、喜びと希望で眼を輝かせている。役割を与えられた者は、嬉々として駆け出していく。
「エステル様、こちらへ」と、モルデが言った。
彼は丘陵地の隅に小屋をすでにいくつか作っていた。木造で、屋根は茅で葺(ふ)かれていた。珍しげにエステルは観察しながら中へ入った。切り株を加工した椅子が用意されていたので、そこへ腰かける。
「このワの国では、皆、このような家を作るようです」モルデが解説しながら、エステルの前に座る。「この国は木が豊富です」
「火で攻められたら、ひとたまりもない」と、苦笑する。
「ワの民は、あらゆるところに木を使っています。ああ……ですが」モルデは慌てたように付け加える。「城を築くのなら、考えねばならないでしょう」
「モルデ……」エステルは目を細めた。
これ以上、待つことは二人ともできなかった。互いに手を差し伸べ、指を絡めた。
「エステル様……」
二人は自然と顔を近づけ、口づけを交わした。離れていた分だけ、それを埋め合わせるような激しいものだった。
「お前がここへ来ていた間、ずっと神に祈っていた……。お前の無事を」
「私もエステル様が無事にここへ来られることを祈っておりました」
「ワの国のこと、よく調べてくれた」
二人は顔を寄せ合い、囁くように言葉を交わした。
「私はここへ来て、確信しました。豊かな水の流れる葦原の国。こここそが、我らが探し求めていた土地だと。ただ……」
「ただ?」
「この国の民たちは、あまりにも私たちと違います」
うっとりとしていたエステルの眼は、それで理性的になった。
「違う、とは」
「この国には、我らが信奉する唯一の神はおわしません」
「それは……」エステルは眉を上げた。「どこでもそうだったではないか。我らと同じような、崇高なる唯一の神を崇める民は、この地上のどこにもいなかった」
「ええ。この国の民も多くの神々を崇めています」モルデは立ち上がり、木造の小屋の中から外を見た。「木の神、山の神、火の神、川の神、太陽の神、月の神……。ですが、どこか、違うような気がするのです」
「違う? 他の国々の、多神を崇める者どもと、どう違うというのだ」
モルデは言葉を探し、「いや」と首をひねった。「よくはわからないのですが、そんな気がするのです。気にしないでください」
「いずれにせよ、有象無象(うぞうむぞう)の神々など信奉する民には、救いもなければ叡智もない。我らがこのワの国を平定してしまえば、それで良い。聞けば、このワの国にはろくな集権国家もないという話ではないか」
「いや、そのことなのですが……」
モルデが言いかけたとき、ヤイルとカイが二人そろって小屋にやって来た。人の割り振りが終わったのであろう。
「良い土地だ」と、ヤイルが満足げに言った。「まさに神が、我らのために残してくださった、格別の土地。開墾すれば、良い作物が実るだろう」
「次の便で、馬も運びましょう」と、カイ。
「ちょうどよかった。ヤイルも聞いてくれ。カイもだ」
真剣な表情のモルデに、楽しい雑談をしている雰囲気ではなくなった。
「じつは、カイをカラ国へ送り返した後、この近くで戦があった」
「えッ?」と、カイは目を丸くした。「兄さん、このワの国にはろくな国はないとかいう話だったじゃないか」
「そうだ」ヤイルも言った。「半島からの玄関口のナの国というのは、古くからの強国だが、それ以外はいずれもちっぽけな村々だと」
「違ったんだ。ここは大陸で聞いたような理想郷ではない。それどころか、我らと同じように大陸から渡ってきた勢力が、バラバラに小さな国を作り、争っている」
「うかうかしておれんということだな」と、エステル。
「はい。中でも東にある〝オロチ〟という国が大きな脅威です」
「オロチ?」
「その国ではクロガネを自国で生産しているようです。もちろん剣も持っています。これをご覧ください」
モルデは小屋の片隅に立てかけていた剣をエステルに手渡した。彼女は食い入るようにそれを見つめ、柄の握りや刃の鋭さを確かめていた。
「殺された兵が持っていたものです。むろん、我らが所持する剣ほどの強度はなく、切れ味も劣ります。しかし、クロガネを量産できるだけの技術も持っているとなると、これは侮れません」
彼らカナンの民が拠ったのは、ナの国よりも東にはずれた地域だった。情報収集をし、要らぬ争いを避けるため、力を持つ国から離れた場所に拠点を置こうとしたのだ。しかし、東にも脅威はあったのだ。
「国造りを急がねばなりませんな」ヤイルが言った。「いかような事態にも備えらえるよう」
「……いや」
エステルは宙を見据えていた。彼女のつぶらな、非常に強い瞳は、ある種のカリスマ性を備えていた。でなければ、男性優位の父系社会のカナンの民の中で、リーダーになることなど、決してかなわなかったろう。
「それでは遅いかもしれん」
「遅いと言われますと?」
「ヤイル、ここまでの旅で我らが幾度、苦い思いをしてきたか、思い出せ。こちらの態勢が整うのを待っていては、この約束の土地を追い出されてしまうかもしれん。我らにはもう、ここよりほかに行く場所はないのだ」
「いかがなされます」
「先手必勝。時間をかけて国造りをする必要などない。すでにあるものを奪えばいいのだ。モルデ、カイ」
二人の兄弟は、はい、とエステルの前にひざまずいた。
「明日から周辺の探索をしてくれ。まずは、この周辺のどこか、手ごろな小さな国を奪う」
夜が訪れていた。月明かりが差し込み、虫の鳴き声が耳触り良く、響いている。
こんな静かな心地よい夜を、エステルはここ何年も迎えたことはなかった。それは隣にモルデがいて、肌の暖かさを感じさせてくれているということがあるにしてもだった。
その安堵感は、これまでどのような土地にいても味わったことのない、満ち足りたものだった。エステルは確信を深めた。こここそが、約束の地だと……。
胸の上にあるペンダントの宝珠を無意識に握りしめた。
「……不思議な形だ」耳元でモルデが囁いた。
彼はエステルの指をほどけさせ、宝珠を掌に載せた。
「なぜ、このような曲がった形をしているのかな」
エステルは彼のたくましい肩に手をまわしながら言った。「父から聞いたことがある」
「エリエゼル王が? なんと?」
臥所(ふしど)を共にするときだけは、彼らの間から主従の関係は薄れたが、それでもモルデの態度からエステルへの畏敬が消えることは決してなかった。それがエステルには、少しばかり悲しいことだった。
「この宝珠は、失われた王国の神殿にあったもの。言い伝えによれば、神(ヤー)を象(かたど)ったものだと」
「y(ヤー)を? それで、このような形を? おかしいな」
「なぜ?」
「いや、だって……神は我らを自らに似せてお作りになったはず」
「ああ……そうね」
「だったら、私たちもこの形だということになる」
「似てない?」
「似てない」
二人はクスクス笑い、キスをし合った。そして、再び睦み合った。
エステルはやがて眠りについた。モルデのそばで、胎児のような姿勢になって。
それは宝珠の形に似ていた。
2
美しい山野を清流が駆け下ってきている。深い緑の中に、黄色や赤の鮮やかな色彩が、ぽつぽつと生まれ、そして山自体がみるみる大きな一輪の花のように色づいていく。
秋という季節の変化を、クシナーダはうっとりと見ていた。自然は愛に満ちていて、そして大小さまざまな「意識」に満ちていた。花の意識、樹木の意識、石の意識、川の意識、水の意識、山の意識、そして空の意識……。
その中をクシナーダは全裸で駆けていく。
生まれたままの姿で、そのすべての意識を感じながら。
この世界に充満している喜びの波長。それを目や鼻や耳や、皮膚を通じて、体中で感じられることが、また深い喜びを湧き上がらせるのだった。そして彼女の口からは、喜びの歌が自然とあふれ出る。
すべては美しく、すべては調和している。
が、不穏な気配が彼女の足を止めさせた。と同時に、川は真っ赤に染まった。
川のほとりから、草木が枯れて行った。
愕然としてクシナーダは悟った。
これはいつも見る夢だと。もう何年も前から繰り返し繰り返し見続けている夢の中に、また彼女は迷い込んでいた。
川を赤く染めるのは、鉄穴(かんな)流しによる汚れた土砂だった。その赤い色はますます色を濃くし、やがては血のような真っ赤な色合いに変化した。
川底から何かが首をもたげてくる。
クシナーダは悲鳴を上げた。巨大な蛇がどろどろの真っ赤な血にまみれて現れたのだった。口を開き、牙と舌を見せつけ、シャー、と空気を毒々しく震わせる。
立ちすくむクシナーダの周囲に、一つ、また一つと大蛇(おろち)の首が出現する。川の中から、あるいは地面を割って、あるいは山野を越えて。
八つの首は威嚇しながら、クシナーダのほうへ迫ってきた。逃げなければ! だが、足が動かない。なんとか踵を返すが、体重が何倍にもなってしまったように、思い通りに動かすことができない。大蛇たちはぐるぐる回り込んできて、彼女を包囲した。
夢だ、これはいつもの夢だ、とクシナーダは自分に言い聞かせた。恐れることはない。夢はここでいつも覚める――。
クシナーダは慄然とした。夢は覚めなかったのだ。
大蛇らはいよいよ獲物にありつける喜悦に踊るように、みるみるクシナーダへの包囲を狭めてきた。蛇の割れた舌先が彼女の身体を、ゾッとする感触で舐める。
ひときわ大きな頭部が眼前に迫ってきた。真っ赤な眼が冷酷さの中にも、残虐な歓喜を映し出し、輝いている。牙がむき出され、口が彼女をひと呑みにしようと、裂けるほどに大きく開かれた。
夢の中でありながら、クシナーダは死を覚悟した。
が、大蛇たちは彼女を呑み込めなかった。
雷が幾筋も走り、視野は一瞬、真っ白になった。と、ものすごい突風のようなものが渦を巻き、あたりの景色を一変させた。大蛇はいなくなっていたが、暗い空に竜巻が立ち上がっている。
竜巻は虹色になった。
虹が竜巻になっているのだった。恐ろしくも荘厳な景色だった。
「!」
クシナーダは勢いよく跳ね起き、目覚めた。心臓が胸の中で、暴れ狂っているのを感じた。
――なんだろう。
彼女は自分の胸を押さえた。怖い夢を見れば、どきどきするのは当たり前だ。しかし、それだけではなかった。怖いだけではない、なにか体の芯から震える、期待のようなものがあった。
臥所(ふしど)を抜け出し、クシナーダはそっと家の外へ出た。
黎明のまだ薄い光が、そっと包み込むように村を満たしていた。何もかもが青白くかすんでいる。昨夜の激しい風雨の名残が、湿った土とびしょ濡れのまま枝を下げている樹木の姿に感じられた。風が吹くと、ざーっと水滴が無数に落ちてくる。
茅葺の家屋の間を抜けていくと、彼女はそこに杖をついて佇む古老を見つけた。
「アシナヅチ様」と、声をかける。
里の首長であるアシナヅチは、それでもしばし、反応を示さなかった。耳が遠いのではない。アシナヅチにはよくあることだった。心をどこかに飛ばしていると、戻って来るのに時間がかかる。
「……クシナーダか」
ややあって、アシナヅチは言い、わずかに振り返った。クシナーダはアシナヅチのそばで、膝を折り、低い姿勢を取った。
「おはようございます」
「おはよう。こんなに朝早くから、いかがした?」
「夢を見ました……」
「またいつもの夢か」
「はい。あ、いえ……少し違っておりました。大蛇に食われるかと思いましたが、虹が大竜巻となって現れました」
「虹が?」
アシナヅチは口のまわりと顎を覆っている長い白髭をしごいた。考え事をするときの彼の癖だった。
「あれを見よ」と、アシナヅチは東の空に向けて、杖を指し上げた。
激しい雷雨だった昨夜と異なり、空はすっかり晴れていた。まだ太陽は稜線の下にあり、空がほの明るくなっているだけだ。その上空でひときわ輝くのは、明けの明星だった。しかし、見慣れぬ星がそのそばに、勝るとも劣らぬ輝きを放っていた。
クシナーダは驚いた。明けの明星が金星であるということは知っていた。太陽の比較的近くを公転する金星は、夜明け、あるいは日没時に、そのそばに必ず位置しており、非常に大きな輝きを放つ。しかし、その金星以上に輝きを放つ星など、見たことがなかった。
「アシナヅチ様……あれは」
「天津甕星(あまつみかほし)……」
「みかほし?」
「あの星はわしの眼には、一昨年(おととし)から見えておった。次第に輝きを増してはおったが、ついに肉眼でもあのように輝きを放つようになった」
「なんの兆(きざ)しでしょうか」
「甕星は天に仇(あだ)なす凶星。おそらく、そなたが見た虹の竜巻と同じものであろう」
クシナーダは魅入られたように、甕星の凛とした輝きを見つめていた。まるで魂が吸い込まれるような心地がした。自分がその星へ引っ張られているのか、それとも自分がその星を引き寄せているか、空間の感覚がまったく消えてなくなっていた。
その光は一瞬にしてクシナーダの視野いっぱいに広がり、包み込んできた。
刃物のような、厳しい光だった。しかし、なぜかクシナーダはその光に身をゆだねることができた。自分が拒絶することもなく、また光によって傷つけられることもなく。
光の中でクシナーダは、広大な宇宙空間を視ていた。
宇宙は圧倒的な光芒に満ちていた。宇宙空間は闇などではない。すべてのもの生み出す創造の力に満たされた、母なる海だった。輝きを放つ無数の恒星、あるいは星雲の数々は、その海に育まれた命の輝きそのものであり、すべてが喜びを放ち、そのヒビキが絡み合い、手を取り合い、巡り合い、回りながら、壮大な交響曲を奏でていた。
初めて見る光景ではない。アシナヅチの導きを受け、クシナーダは幾度もこの体験をしていた。だから、自分たちが暮らす地上が平坦な大地などではなく、球体をした青く美しい星であることも知っていた。
――なんという麗しい星だ。
想いが湧きあがる。
と、同時に戸惑う。今のは自分の想い?
――お母さん。
激しい恋にも似た思いが募ってくる。いや、十五のクシナーダはこの時代の娘としてはかなり奥手で、まだ恋慕の情さえ経験したことがなかったはずだった。それもそのはず、巫女として特別な教育を受けてきた彼女は、ある意味で一般的な男性への恋愛感情をはるかに凌駕するものを、すでに得ていた。それは大自然への深い敬意であり、同時に大自然との交感の中でしか得られない、特別な悦びだった。
――お母さん。
その想いは、今、クシナーダが一体化している甕星の意識が発しているものだった。
あまりにも〝個人的〟で、あまりにも原初的な、熾烈な恋慕の情の塊に触れ、クシナーダは全身がしびれる心地がした。生々しく、だからこそ、力にあふれた波動だった。
光はクシナーダを包み込んだまま、青い地球へ到達した。その瞬間にクシナーダは二つのことを同時に味わった、
それは光と一体化した自分が地球そのものになったこと。
もう一つは地球そのものになった自分が、その光を受け入れたことだった。
その衝撃は、これまでのどのような自然との交感よりも鮮烈で、自分のすべてを燃焼させるほどの狂おしい火が体の芯から突きあがってきた。
そこでクシナーダは、現実に返った。垂れ下がるような長い眉毛の下からアシナヅチの眼が見つめているのに気づき、少なからず狼狽する。
「甕星のヒビキに共鳴したか」
クシナーダはうなずいた。そのとき風が吹いた。
――ハハハ。
その風に紛れて、女の笑い声が聴こえた。二人が驚いて見まわすと、桜の大樹の枝に腰かけた女の姿が頭上にあった。鮮やかな青と緋に彩られた衣をまとった、若い女だった。満面の笑みを浮かべ、口の端が釣り針でひっかけられたように、にっと曲線を描いている。
「そなたは……」と、アシナヅチが数歩、歩み寄る。
「ウズメ様……」
クシナーダは畏敬の念に打たれながら、アシナヅチにしたような礼の姿勢を再び取った。
「時が来たのさ」
耳というよりも、胸を貫いて刺してくるようなヒビキの声だった。いったいどこから発声しているのかと疑いたくなるような、ありえない明るさと強さを持っていた。
「甕星はやって来るよ!」
「甕星とは何者?」と、アシナヅチ。
「すぐわかる」
そう言って、ウズメはまた笑った。顔だけではなく、声をあげて笑った。おかしくて仕方ないように。
「――ていうか、あんた、知ってるし」と、クシナーダを指差す。
「え? わたくしが?」
「そう、知ってる」
そう言い放ち、ウズメは木の枝の上で、すくっと立ち上がった。まるで体重がないような動きだった。
「楽しい♪ 嬉しい♪」
ざっと木の枝を揺らして鳴らして、つむじ風が通り抜けた。ざーっと振り落されてきた水滴に思わず目をつぶった二人が、再び瞼を開くまでのその一瞬に、ウズメの姿は消えていた。
「アシナヅチ様……」
クシナーダは戸惑いながら、古老を振り返った。もちろん何がしかの答えを求めてのことだった。だが、アシナヅチは沈黙を守ったままだった。彼自身、はっきりとした言葉を持たないようだった。
冷たい水と砂の感触が、意識が戻るとすぐに感じられた。視野を小蟹が横ばいしていく。
スサノヲはかすかに呻き、起き上がった。ずぶ濡れた衣類が重かった。砂を払い落しながら、立ち上がる。
波が勢いよく寄せてきて、彼の足もとの砂をさらった。
見渡せる限りの砂浜だった。砂浜に沿って、ずっと雑木林が続いている。
――ここは、どこだ。
そして、なぜ自分がこんな場所にいるのか、記憶をたどった。
彼は昨日、カラ国を出港する船に乗った。ナの国の商船だった。ナの国とは、ワの国の一部である。彼はそのワの国へ渡るために船に乗ったのだ。
が、出港してしばらくして、天候が急変した。カラ国の珍品を満載した船は、荒れ狂う風雨の中で翻弄され、流され、そして――。
ひときわ高い波に頭から呑まれたのが、スサノオの最後の記憶だった。
船は難破したらしい。
スサノヲは砂浜を歩き出した。どこだかわからないが、運よく彼は陸地に流されたようだった。
また遠回りをしてしまったかと、臍(ほぞ)をかむ。
カラ国に到達するまでも、相当に彷徨っている。大陸の中央を横断する商人の道があると聞いたのは後の話で、最初からその道を進んでいれば、数カ月は早くに到着できたはずだった。
好奇心もあった。このネの世界のありようを知ろうと思い、気の向くままに歩き、出会う人やモノ、そして多くの国々を見ておこうとしたのだ。
その旅の過程で、彼は知った。この世界の混沌と、はかなさを。
争いのない国などなかった。一国の中でさえ、人は己の欲を満たすことに腐心し、他人を傷つけ、陥れること、場合によっては殺すことさえ平気だった。ましてや国と国は、より肥沃な土地や利便性の高い土地を巡って、常に戦争を行っていた。
その一方で、もの静かに暮らす人々もいた。山野に溶け込むようにして、その日の生活を日の出と日没に合わせて生きる人々も。
旅のスサノヲに親切に宿を提供してくれた者も、数えきれぬほどいた。
しかし、善良な人々ほど、権力を持った抑圧者たちの被害者でもあった。その被害から逃れるためには、隠遁者となるしかなかった。
ただ、どのような立場の人間にも確実に平等な出来事もあった。
それは「死」が訪れるということだった。決して長くはない、はかない人生の繰り返し。
本当に短い、ほんのわずかな時の栄華や幸福のため、人はこのネの世界を生きているのだった。
スサノヲの眼から見れば、それは本当にはかなくもろい世界だった。
ネの国。それは物質的な、有限の世界だった。そして、その中で呼吸をしている自分もまた……。
少し歩くと先に岩場があった。そこへ上がると、どうやら山間(やまあい)に川があり、それに沿って道が続いているらしいのが確認できた。といっても、もちろんけもの道だ。
とりあえず何がしかの集落でも、人のいる場所へ向かう必要があると、彼は判断した。
そのとき彼は、視野の端に白いものを見た。
岩と岩の間に挟まれるようにして、子供が横たわっていた。スサノヲは一段岩を飛び下り、子供のそばにしゃがみこんだ。年のころは六、七歳だろう。その顔と身なりに見覚えがあった。ナの国の商船で一緒だった子供だ。
たしか親と一緒に乗り込んでいたはずだが……。
周囲を見まわすが、他に打ち上げられた者はいないようだった。
スサノヲは子供が息をしているのを確認した。
はかない命。
放っておいても、数十年で消滅する命。スサノヲは一度、それを捨て置こうと考え、その場を離れかけた。
が、足を止めた。
スサノヲは引き返してきて、その子供の胴に手をかけた。ひょいと軽々と抱き上げる。けもの道を歩き出した。
そして、思った。
――腹が減った、と。
3
スサノヲはすぐに後悔するところとなった。まいったな、と何度目かの困惑を胸に感じる。
子供を前に。
その子は今、河原の岩の上で座り込んでいる。
スサノヲはといえば、熾火の上で獲ってきた川魚を焼いている。自分が空腹だったということもあるが、子供に食わせなければならならなかった。
人は脆く、食べなければ死んでしまう生き物だ。
スサノヲ自身、この地上で飲まず食わずでいられた時間は長くない。自分がこの地上のものになったのだということを教えてくれたのは、喉の渇きや空腹だった。
身体の機能を維持するために、水や他の生命――植物であろうが動物であろうが――を体内に取り込まねばらないというのは、おそろしく面倒な作業だった。しかし、避けられない。自分だけでもそうなのに、子供をしょい込んでしまった。
「ほら、焼けたぞ」
スサノヲは熾火の上から、じりじりいっている火傷しそうな魚を取り出した。葉に乗せ、子供のいる岩の上に置く。しかし、子供は膝を抱え込んだままだった。
人は脆い。
肉体だけではなく、心までもが脆い。
この脆い人間の、しかも子供を助けてしまった。ほんの気まぐれに過ぎない。カラ国を出港する前、両親のそばで無邪気に騒いでいた子供の顔を思い出し、憐れに思ったということもある。が、一度助けてしまうと、今はもっと重大な問題になってしまっていることに、スサノヲは気づいていた。
それは、見放すことができない、ということだった。一度助けてしまったが最後、子供を安心のできる環境に届けてやるまで責任が生じてしまっていた。
どこか集落を見つけたら、子供はそこで引き渡してしまえばよいと、最初は安直に考えていた。ところが大きな河川に沿って存在していたであろういくつかの集落は、戦乱の跡地となっていた。誰も生き残っておらず、飼い主を失った犬がうろついているだけだった。
どこだかわからないが、この地も平穏ではないのだ。
結果、スサノヲは随分と川を遡らなければならなかった。人は水のあるところで生活をする。どの国でもそれは基本的にある。どこか無事な集落を見つけるまでは、子供の面倒を見なければならない。
「食わねば歩けない。食わないなら置いていく」スサノヲは新しい魚を熾火の上から取り、熱々の身に噛り付いた。「お前の親は、もしかすると俺たちのように生きているかもしれない。ここがカラ国なのかワの国なのかわからないが……どうする? お前はこれを食って歩くか、それとも食わずに座っているか。どちらでも好きにするがいい」
親が生きている可能性など、スサノヲは信じていなかった。が、今はこの子供を生かすことを考えなければならなかった。
子供はゆっくりと手を伸ばし、魚に噛り付いた。
それを見て、スサノヲは尋ねた。「お前、名前は?」
「……スクナ」
「俺はスサノヲという」
スクナは黙って、魚を食べていた。
「お前、女の子だな」
食べるのがちょっと止まった。男の子のような身なりをしていたが、海岸で担ぎ上げたときに、スサノヲは気づいていた。
「お父ちゃんが、そうしていろって……。男の子に見せていたほうが、連れて歩きやすいからって」
「男の子のほうが安全か。お前はもともとワの国の者なのだろう。お前の親はそうまでして、なぜカラ国へお前を連れて行った?」
スクナは答えなかった。
「まあ、いい。答えたくなければな」
スクナはスサノヲをおずおずと見た。「ここはワの国だよ」
「なぜ、そう言える」
スクナは近くの茂みを指差した。葉がぎざぎざになっている小さな樹木があった。青い実をつけている。
「あの葉は、かぶれや火傷に効くの。あれはワの国にしかない。寒くなったら、実が赤くなる」
「ほう」スサノヲは感心した。「お前、物知りだな」
「お父ちゃんに教えてもらった……」
そう言いながら、少女の目はまた赤くなってきた。両親の命が絶望的であることは、彼女が一番よく理解していただろう。
「ほらっ。もっと食え」
スサノヲは魚を取ってやった。スクナは目をこすり、がつがつと食べた。悲しみがあっても生きようとする健気な意志が、その様子からうかがえた。二匹の魚を平らげると、少女は山の斜面から川のほうに突き出している一本の木を見上げた。
「あれ……採(と)れないかな」
高い木の枝の先のほうに、何か果実のようなものが生っていた。ただ、その樹木の実ではなく、樹木に巻き付いている蔓性の植物のもののようだった。赤紫色の細長い果実がぱっくり割れているのが、いくつか群がるように生っている。
木に登って、枝の先のほうまで行かないと採れそうになかったが、枝は細い。大人の体重にはとても耐えられそうにないし、飛びあがったところでとても届くような高さではない。
「無理かな」と、少女は遠慮がちに言う。
「あれ、うまいのか」
「おいしい」
「そうか」スサノヲは立ち上がり、果実の下まで行った。
道具も何もなかった。スサノヲは丸腰なのだ。スサで生成した剣も、嵐で船が難破した時に失ってしまっていた。おそらくは今頃、海の底だろう。地上になじんでしまった彼に剣を再度生成する力はなかったし、ここで便利な道具を作り出すことなど、もちろんできなかった。
スクナは眼を疑ったことだろう。スサノヲの身体は低く縮んだと思ったら、次の瞬間には宙へ跳ねあがっていた。優に身の丈の三倍は跳躍し、楽々と果実をもぎ取っていた。
「すごい……」
賛嘆の眼差しのスクナの鼻先にスサノヲは果実を突きだした。少女は驚きながらも喜んで、その果実を手にした。宝物を得たような表情がちらっとよぎる。外側の皮のような部分が二つに割れ、その裂け目に白い果肉が見えている。彼女はそこへ口を突っ込むようにして食べ始めた。
「おいしい……」泣きそうなくらいうれしそうな表情だ。いや、泣いていた。「これはアケビ……いつもお父ちゃんが秋に採って来てくれた……おいしい」
「そうか。そんなにうまいか」
スクナは無言で、アケビを一つ、スサノヲに差し出した。本当に見たこともない、ちょっと気味悪い外観の果実だった。
「カラ国にもアケビはあるよ」
「そうなのか?」不信感でいっぱいになりながら、スサノヲは見よう見まねでかぶりついた。ぬるっとした果肉が、口いっぱいに広がった。
そのとたん、衝撃を受けた。甘く、とろけるようなうまさだった。
「うまい……甘くてうまい。なんだ、これは」
呑み下し、また口に含んだ。
「あ! ダメだよ、種を食べちゃ。糞詰まりになっちゃうよ」
ぶーっと、スサノヲは種を吐き出した。「ふ、糞詰まり?」
「この白いところだけを食べるんだよ。本当に知らないんだね」
「先に言え」
むっとしながらスサノヲは睨みつけた。まだ涙で濡れていたが、スクナの顔がくしゃくしゃになって、笑っていた。
ふっと、スサノヲは笑った。そして少女の頭をぐしゃぐしゃに撫でた。そして、そんな仕草をしてしまった自分に戸惑った。
――気ヲツケロ。
奇妙な声が聞こえ、はっとさせられる。スサノヲは旅の途中で、人語の真似をする奇妙な鳥を見たことがあった。ちょうどそのような声に聞こえた。
「どうしたの?」
周囲を見まわすスサノヲのことを怪訝に見るスクナ。少女には聞き取れなかったようだ。
スサノヲは先ほどのアケビが生っていた木の枝に、大きな黒いカラスが止まっているのを見た。まるで人間のような思考力がある眼をしたカラスだった。一目で普通の野鳥ではないとわかった。
「お前か……。スサからずっと俺のことをつけまわしていただろう」
――ツケ回シテイタノデハナイ。案内シテヤッテイタノダ。
カラスを通じて思念が飛んでくる。が、カラスなど媒体に過ぎない。どこかに本体が存在するように思えた。
――ヨウヤク辿り着イタナ。ワザワザ遠回リバカリシオッテ。
「よけいなお世話だ」
スクナは唖然として、スサノヲがカラスと話すのを見ていた。むろん、カラスからの声は聞こえておらず、ただ一方的にスサノヲが語りかけているように見えたろう。
「いつ焼き鳥にしてやろうかと思っていた。なんなら、これから焼いてやろうか」
――ハハハ。ソンナ暇アルマイ。
「どういう意味だ」
――スグ分カル。
ずん、という響きが、どこか深いところで生じた。そのとたん、大地が異様に鳴動し、いっせいに木々が悲鳴のようなざわめきを発した。ゆるやかだった川面もにわかに波立ち、河原の岩という岩が騒ぎ立てた。
地震だった。
スクナが短い叫びを上げ、慌てて岩の上から転げ落ちそうになる。スサノヲは危うくそれを受け止め、少女の頭を抱きかかえ、河原に伏せた。さすがに立っていられない。上下左右にむちゃくちゃに搖動する地面の上に、周囲の木々から葉や木の実が無数に落ちてくる。
山々が鳴動し、メキメキ音を立てて老木が倒れた。大木でさえ、今にも折れそうなほどたわんでいるのが見える。川の水が、大蛇のようにうねった。
さすがに肝が冷える瞬間だった。
しばらくすると、暴れていた地面は沈静化した。しかし、まだ大地には余韻のような震動が、ずっと残っているように感じられた。
「す、すごい地震(なえ)だった……」
腕の中で、スクナが身じろぎをし、言った。スサノヲはアケビの生っていた木の枝を見上げた。すでにカラスはいなかった。
「この頃、地震がとても多い。巫女様は前に言っていた。前触れだと。だから、地震がとても多いんだと」
「巫女様?」スサノヲはスクナから離れ、尋ねた。「前触れというのは、なんのことだ」
「ワの国には巫女様がたくさんいる。みんな、これは大きな前触れだと……」
スクナの眼が、ある一点で止まった。その視線を追いかけると、川の対岸に一人の娘が佇んでいるが見えた。
ススキが無数に立ち上がっている中に、長い黒髪を結った美しい娘がいた。臙脂(えんじ)の衣を身にまとい、手には竹で編んだ籠を持っている。つぶらな瞳を見張って、呆然とスサノヲらを見ていた。唇が動く。みかほし……なにか、そんなふうに言ったように聞こえた。
「あの人……巫女様だ」と、スクナが言った。
「そうなのか」
「ほら、勾玉の首飾りをしてる」
娘の胸元には大きな翡翠の勾玉が下げられているのが見えた。
「ここはワの国か」スサノヲは大きな声で問いかけた。
娘はうなずいた。「はい。ワの国です」
その声のヒビキのあまりの心地よさに、スサノヲは戸惑った。
「ワの国のどこだ」
「ワの国のナカの国にございます」
「ナカの国……」(※現・中国地方)
「東の国と西の国の間の国でございます。ここはナカの国の中のトリカミの里」
「真ん中ということか」スサノヲは振り返った。
「トリカミなら知ってる」スクナは意を察して答えた。「たくさんの巫女様の中でも、一番古くてえらい巫女様の里だ」
「ほう。――ならば、知っているか」スサノヲは娘に問いかけた。
娘は首をかしげる。
「このワの国には、ヨミの国に至る道、ヨモツヒラサカがあると聞く」
「ヨミの国……」娘の顔色が変わった。
「知っているのだな」
言下にスサノヲは跳んだ。川幅は彼の運動能力をもってしても、ひとっ飛びにできるようなものではなかったが、途中の岩や中州を飛び渡ることで、水に濡れることなど一度もなかった。ほんの瞬(まばた)きの間に目の前に近づいた男を、しかし、娘はきょとんとして見、次には「すごい」と笑って褒めた。手でも叩きそうな表情だ。
いきなり調子を外され、スサノヲは気を取り直さねばならなかった。
「知っているのなら教えてもらおうか。その場所を」
娘はまじまじとスサノヲを見つめ、顔を近づけてきた。逆にスサノヲは引かねばならなかった。かと思うと、急に娘は大きく何度もうずいた。自分ひとりで納得するかのように。そうしながら、周囲に散らばっていた鮮やかな色の木の実を拾い、籠に集め始める。
「な……」
うまく言葉が出なかった。警戒するとか怯えるとか、こちらが想定するような反応を、娘はいっさい示さなかった。どうやら拾っているのは、これまで収穫した木の実らしい。先の地震でまき散らしてしまったのだろう。
それにしてはこの娘の気配をまったく感じなかった、ということをスサノヲは不審に思った。あれだけの大きな揺れだ、普通の娘なら悲鳴の一つや二つ上げてもおかしくないのに、この娘はどうしていたのだろう……。
「一つ、いかがですか」娘は鮮やかな橙色の果実を差し出した。「お食事をなさっていたのでしょう?」
「…………」
うまく返事ができず、スサノヲは思わず娘が差しだす果実を手に取っていた。
「おいしいですよ」と、娘が無邪気に言う。
柿だった。スサノヲはそれを大陸でも見たことがあった。いかにもうまそうに見えるその果実は、しかし、口に入れると、とてつもなく渋かった。噛り付く気にもならず、手にしたまま凍り付いていた。
「うん。おいしい」
スサノヲが躊躇しているのを見てなのか、それとも自分が食べたいだけだったのか、娘はその同じ果実に噛り付き、頬張っていた。それを見て、スサノヲも口に入れてみる気になった。先ほどのアケビにも劣らぬ衝撃だった。大陸の柿とは別物だった。
「うまい……。こんな果実があるとは」
「あなた、お名前は? みかほし様?」
「みかほし? いや、俺はスサノヲ」
「スサノヲ?」娘は目を丸くし、その言葉を胸に落とし込むように、何度か小さくうなずいた。そして、振り返って言った。「わたくしはクシナーダと申します」
クシナーダ、という言葉のヒビキは、スサノヲに少なからぬ衝撃を与えた。初めて聞いたような気がせず、なぜか心の琴線に強く触れるものがあった。その理由を探ろうとするのだが、どうしても自分の中には答えは見いだせなかった。
「いいヒビキだ……クシナーダ」
「知っていますよ」
「え?」
「ヨモツヒラサカの場所を」
「やはり知っているのか。教えてくれ。どこにある、それは」
興奮し、娘の両肩をつかんだ。が、彼女は怯えることもなく、まっすぐにスサノヲの眼を見つめ返して言った。
「ヨミの国はさまよえる死者の国。なぜそのような場所に?」
「そんなことはどうだっていい」スサノヲのほうが、やや狼狽せずにはおれなかった。「いいから、教えてくれ」
「理由も知らされず、簡単に教えられるようなところではございません。そこらへんの原っぱに散歩に行くのとはわけが違います」
きっぱりと言うクシナーダは、スサノヲの手を払いのけた。か弱い小娘だと思っていたが、意外に毅然としたところがあった。
「ヨミへ行けば、生きて帰ってこられないかもしれないのですよ」
「それは俺であって、あんたじゃない」
「では、あの子はなんなのです」クシナーダが指差したのはスクナだった。「あの子は、あなたのなんなのです。あなたの子ですか」
「い、いや」どうも調子がくるっているのを感じながらスサノヲは言った。「ただの旅の連れだ。船が難破して、近くに打ち上げられた」
「どうして放っておかないのですか」
言葉に窮した。
「あなたはあの子を助けた。そういうことでしょう」
「まあ、そうなる……」
「あなたがあの子が死ぬのを放っておけないのと同じように、わたくしもあなたが死ぬかもしれないような行いをするのを放ってはおけません」
これはスサノヲの分が悪かった。なぜこのようなことになってしまっているのか……ともかくクシナーダのほうに明らかに理があった。そしてそのような事態を招いてしまったのは、ひとえにスクナを助けるという行いをしてしまったからだと、スサノヲは気づかされた。
「頼む。俺はどうしてもヨミの国へ行かねばならないんだ」
戦術を変えることにした。優しそうな娘だ。懇願するという手段なら落ちるかもしれない――と思ったのは、まことに浅はかだった。
「いずれ死ねば、皆、そこへ行けます。焦ることはありません」
がん、と大きな岩で打ちつけられたようだった。
クシナーダは、話は終わったとばかり、背を向けて歩き出した。慌てなければならないのはスサノヲのほうだった。
「スクナ……! 火を消して、こっちへ……」と言いかけ、スクナには川を渡るのは難儀だと気づき、一度戻った。焚火に水をかけ、消火すると、スクナを背負い、川を飛び渡る。その頃には、クシナーダの姿はススキの影に見えなくなりつつあった。
クシナーダは一度振り返った。そして、腰を折り、頭を低くして、礼の姿勢を取った。誰に向かっての礼だったのか……スサノヲには、彼女があのアケビが生っていた木のあたりに向かって会釈したように見えた。
しかし、そこにはもちろん、誰もいなかった。
三人が去ると、アケビが生っていた木の枝に、いつの間にか人影が二つ出現していた。細い枝の上に、肩幅の広い異形の男と、彼の身体に蔓がまきつくように寄り添って女が、二人もそろって立っているのは、体重を消せる術がない限りあり得ない光景だった。
「相も変わらず騒々しい男じゃ」と、異形の男が言った。鳥類を想わせる尖った鼻の面をかぶっていた。「山を鳴らせおった」
くすくす、女が笑った。「面白い。楽しい」
「ウズメ。そなたはなんでもそうやって面白がる」
「いけませぬか、サルタヒコ様」
「…………」
笑い声をあげ、ウズメは枝から飛び降りた。そしてスサノヲたちの後を辿って歩き出す。
同時に黒い大きなカラスが枝から飛び立っていった。
4
不思議な娘だった。
クシナーダは歌いながら歩いているが、まったく気ままで奇矯に見えた。やることがおかしいのだ。あちこちで草花に話しかけ、急に笑ったりもした。誰もいないのに、誰かと会話している。
「おかしな娘だ……」
スサノヲがつぶやくと、隣でスクナが怪訝そうに見上げ、「スサノヲもだよ。カラスと話してたじゃない」と言った。
言われてみるとそうだった。あのカラスの声は、スクナには聞き取れなかった。それはスサノヲが本来異界の存在であり、あのカラスの本体も異界のものだからだ。
「巫女様は普通の人間が見えないものが見えるんだ。妖精とか神様とか」
「そうなのか?」
とすれば、クシナーダは人間でありながら、異界に通じることができるのだろうか。
スサノヲは旅の途中で、異能を身に着けている人間たちに遭遇することがあった。精神的な力で体を宙に浮かせるとか、あるいは人の心を読んだり、遠くのものを見通したり、先に起きることを予知したりする能力を持つ者たちだった。彼らはある種の苦行を積み重ねることで、そうした異能を発揮するようになっていた。
彼らの多くは、当たり前の生活から逸脱し、エキセントリックな個性を持っていた。日常を捨て、人間らしさを代償とすることでしか、そうした特殊な〝力〟を手に入れることはできないのかもしれない。だが、クシナーダはそんな連中のぎらぎらと何かに執着する雰囲気とは、まったくかけ離れていた。自由奔放であり、のびのびと、すこやかだった。彼女自身が妖精であるかのようだ。あるいは、もしかすると――
「ただのおかしな娘なのか?」クシナーダはいきなり振り返り、言った。「そう思ってらっしゃるのでしょう」
図星過ぎて返答できなかった。そんなスサノヲを見て、クシナーダはくすくす笑った。
「もう少しです」と言って、また歩いて行く。
――空気が変わった?
いわくありげな巨岩のそばを通過してすぐ、スサノヲはふっと自分を取り巻く空気が、いきなり清々しいものに変わったのを感じた。吸い込む胸の中まで清らかになる気がする。
――なんだ、これは。
そう思ったとき、クシナーダが「ほら、もう見えてきましたよ」と片手を差し上げた。
彼女の指し示す方向に集落があった。茅葺の屋根がいくつも見えた。歩き進めて高台へ登っていくと、集落の全容がだんだんと明らかになった。
想像以上に大きな里だった。小高い丘の台地の上に、環状に広がっている。人が歩いてできた道が、三重円になっている。そして三重円の環状道に沿って、住居である茅葺屋根の建物が散らばっている。
集落の中央には、大きな柱がそそり立っていた。見上げると、中天に差し掛かった太陽の光が柱のてっぺんの向こうにあった。大きな鳥が周辺を舞っている。空は急速に曇ってきており、黒い塊のような雲が太陽の光を呑み込んでいくところだった。
集落で飼われているものだろう。犬が二匹、吠えながら走って来て、クシナーダの周囲に尻尾を振りながらまとわりついた。続いて、柱の周辺にいた子供たちが、わーっという歓声とともに走ってくる。クシナーダはそれをしゃがみこんで迎えた。
「お帰りなさい、クシナーダ姉ちゃん」
「さっきの地震(なえ)、大丈夫だった?」と、クシナーダが優しく言う。
「うん! アシナヅチ様が起きる前に教えてくれたから」
「誰も怪我してないよ!」
「でも、家の中、めちゃくちゃ」
「一つ、倒れちゃった。あ、二つ!」
「今、みんなで直してる」
「わあ、柿だあ。ねえねえ、これすぐに食べられる柿?」
「ええ、大丈夫よ。アシナヅチ様のところへ先に持ちしてね」
「はーい!」
「この人は?」
「旅のお方よ。お迎えの宴をしましょうね」
「はーい!」
「ねえねえ、お客人、どこから来たの?」
「ナの国? キビの国? それとも異国(とつくに)?」
いきなり子供たちの好奇心に輝いた瞳に取り巻かれ、スサノヲは「あ、ああ、とつくにだが……」と答えた。わーっと、子供たちはまた盛り上がる。
「異国だってえ!」
「異国のどこ? カラ国? バーラタ?」
「ねえねえ、バーラタには山みたいにでっかい生き物がいるって、ほんとう?」
「あ、いや、それは……」
象のことだろうと思ったが、山ほどではない、と答えようとしたら、すでに子供たちの間では言い争いが始まっていた。
「そんな生き物、いるわけねえじゃん!」
「いるよ!」
「いないよ!」
男の子と女の子が言い争いをはじめ、それぞれに味方するグループに分かれた。それもスサノヲを間に挟むように。左右からの甲高い子供の声に鼓膜が痛いほどだった。
「やーめーろっ!!」ひときわ大きな声で割って入ってきたのは、クシナーダよりも少し若いくらいの少年だった。「お客人が困ってるじゃんか! アシナヅチ様だって言ってたぞ。熊の何倍も大きな、鼻の長い生き物がいるって」
そうそう、それそれ、と思う一方で、スサノヲは不審にも思った。この島国の住人が、なにゆえに大陸の巨大生物のことを知っているのか……。いや、向こうへ渡って帰ってきた人間がいるのかもしれないし、もしかしたら伝聞としてはここまで知れているのかもしれない。
「オシヲ、アシナヅチ様をお呼びして」クシナーダが言った。
「わかった」声の大きな少年は、踵を返した。
オシヲは柱の向こう側の小屋へ向かい、それとすれ違いに男が一人やって来た。
「クシナーダ、誰だ、そいつらは」
血気盛んで、腕っぷしにも自信がありそうな面構えだった。
「イタケル、こちらはみかほし様とスクナです」
「スサノヲ」と、訂正を入れた。
「あ、そうです。この世でのお名前はスサノヲ様」
クシナーダはそんなことを平然と言い、スサノヲを驚かせた。
「船が難破されたとかで、難儀されておられました」
説明を聞き、ふうん、とイタケルは眉を上げた。
「スサノヲ――またふざけた名前を名乗りやがって。最近は大陸から次々とわけのわからん奴らがやって来て、このワの国を引っ掻き回してばかりだ。おめーも、そんな連中の一人か」
あながち的外れな推測ではなかった。
「そうかもな」
「ほう。おめーもこの国に取りつく疫病神か」
「イタケル……」クシナーダがいさめようとする。
「疫病神というのなら、そうかもな」スサノヲは言った。「それも最強の疫病神かもしれん」
イタケルの眼が剣呑さを鋭く増した。「なら、すぐに出て行ってもらおうか」
「そうは行かない」
「なんだと?」
「お前には関係ない。祟られたくなかったら黙っていろ」
「祟るだと?」
「俺は疫病神なのだろう? 祟るかもしれんぞ」
「面白え。祟ってみろ」とは言いながら、イタケルの表情はこわばり、少しばかり青ざめていた。
「俺の祟りはわかりやすい」
「おやめなさい」
クシナーダのふわっとした声が、握り固めた拳を相手の顔面に叩き込んでやろうというスサノヲの意欲を挫いた。
「イタケル、失礼ですよ。スサノヲ様も、争い事を起こしては、あなたがお困りになるのでは?」
その通りだった。スサノヲはヨモツヒラサカの場所を知りたくてついてきたのだ。
「クシナーダ、こんな流れ者、むやみに信用するな」と、イタケル。
「あら、悪い人ではありませんわ。現にこの子を助けて連れてきてくださったのですから」
クシナーダはそっとスクナの肩に手を置いた。
「坊主、どこの子だ」
イタケルは膝を折り、スクナと同じ目線になった。スクナは少し後ろへ身を引く。
「……ナの国」
「この子は女の子だ」と、スサノヲ。
「そうなのか?」
イタケルは、顔をよく見るためにスクナの髪をかきあげようと手を伸ばした。スクナはスサノヲの背後に回って隠れた。すっかりスサノヲは庇護者にならされてしまっていた。
「この子の面倒をこの里で見てやってくれないか。両親も一緒に船に乗っていたんだが、行方が分からない」
「それはかまわないと思いますが……あ、アシナヅチ様」
クシナーダが礼の姿勢を取って迎えたのは、杖をついた白髪白髭の老人だった。先ほどの声の大きな少年、オシヲとやって来る。ほかの里人たちは――子供たちに至るまで――、老人に多大な敬意を示した。里の首長だとはっきりとわかる。
「アシナヅチ様、こちらはスサノヲ様。そしてスクナ……」
これも白くなった濃い眉毛の下で、アシナヅチの眼がスサノヲを静かに見つめた。
「どこからまいられた」
「カラ国から」と、スサノヲは答えた。
「その前は?」
「大陸の西のほうだ」
「その前は?」
「…………」
――こいつ、視(み)えているのか?
そんな疑念がよぎった瞬間、里人たちに混乱が生じた。悲鳴が上がり、走り回る人影が交錯した。
「なんだ?」イタケルがいち早く反応した。
剣を持った男たちが十数名、里に乱入してきたのだ。しかし、彼らは襲ってきたという印象ではなかった。むしろ、何かから逃げ回っているような必死な形相をして、喚き散らしながら、剣をふりまわし、里の中へなだれ込んできたのだった。血を流し、傷ついている者もいた。
「オロチのやつらだ」
イタケルが猛然と走り出した。そこらへんにあった棒切れを手にし、対抗しようとする。が、彼が暴漢たちのところへ到着する前に、暴漢たちの背後におよそ倍はあろうかという軍勢が出現した。そのうちの半数が前面に出て、弓矢をつがえた。
「放て!」
いっせいに矢が射かけられた。ざあっと降り注ぐ矢は暴漢たちの背後から急襲したが、そのうちの何本かは里人を傷つけた。一本はイタケルの頭部をかすめたものもあった。
クシナーダが衣を翻し、走りだした。傷ついた里人のところへ助けに向かったのだ。
「かかれ!!」
号令と共に、整然と隊列を保っていた軍勢は、一気に押し寄せた。見るからに鍛えられた剣を抜き、生き残った者を次々に血祭りにあげて行った。統制され、訓練された兵士たちだった。
武装も異なる。兵士たちは金属製の甲冑を身に着けていて、盾さえ用意していた。だが、暴漢たちは皮の衣を身にまとい、できの悪そうな剣くらいしか持ち合わせておらず、剣戟では折れることすらあった。
混乱した現場から里人が逃げ出していく。しかし、矢で脚を射抜かれた老人は身動きができなかった。クシナーダが駆け寄る。
そのすぐそばで、今まさに甲冑の兵士が敵を切り殺すところだった。返り血を浴びた兵士はぎらつく眼を、クシナーダと老人に向けた。
「お前らもオロチかぁ!!」
剣をクシナーダに向けた瞬間、その兵士は吹っ飛んでいた。走り込んできたスサノヲの掌底が、わき腹を強打したのだ。
それに気づいた数名が、スサノヲに対して反射的な敵意を向けた。左右、そして正面から取り囲む。傷ついた老人とクシナーダが動けないため、スサノヲはその場からは離れられなかった。考えるより早く、すっと身を低くした彼の右脚が地の上を弧を描いて一閃した。正面の兵士がそれで足元をすくわれて倒される。同時に彼は兵士の剣を奪い、回転することで視野に入った左右の兵士の一人の剣を弾き返し、もう一人は胴を蹴り飛ばしていた。
「やめろぉ!!」イタケルが叫んだ。彼は殺された暴漢の剣の一つを奪い、スサノヲのそばに駆け込んできた。「なんなんだ、てめーらは!?」
そのときにはすでに、最初の暴漢たちは全滅していた。ほんのわずかな時間の出来事であり、後から攻め込んできた軍勢にはただ一人の負傷者もなかった。スサノヲに弾き飛ばされた者以外は、すべて地を踏みしめて立っている。
「ここはオロチ国の領土か」
一人の背高い男が、前に進み出てきた。隊長格と思われる男は顔面に刀傷を持つ隻眼の男だった。
里人の大半は、周辺の小屋に逃げ込んでいた。だが、腰を抜かしたようにその場に釘付けになっている者もいる。
「答えよ」
いつの間にか、アシナヅチが前へ進み出ていた。「ここはワの民の村、トリカミの里じゃ」
「ワの民? オロチ国ではないのだな」
「そっちこそ何者だ?!」イタケルが憤りをみなぎらせて言った。「このような傍若無人、許さんぞ!」
「われらは神の民、カナン」
「か、神の民だと?」
あッ、と軍勢の中で声をが上がった。
「どうした、モルデ」隊長格が振り返る。
最初にスサノヲが掌底で突き飛ばした兵士を助け起こそうとしている一人が、驚きの眼でスサノヲを見ていた。
「あなたは……スサノヲ様」
スサの街で、エステル、エフライムと一緒だったモルデだった。彼はスサノヲのことを半ば気にしながら、「カイ、大丈夫か」と倒された弟兵士を気遣いながら立ち上がった。
「モルデ、知っているのか」
「ヤイル、この方こそ、スサでエステル様と私をお助け下さったお方」
「エ、エフライム様に似ている……」
ヤイルははたと気づいたように、スサノヲの顔をまじまじと見つめた。
暗雲がにわかに濃くなった。
そのとき馬に乗った人物が、数名の取り巻きを従えて里に入ってきた。甲冑に身を包み、腰には大ぶりな剣を帯びていた。
「エステル様……」と、モルデ。
馬上の人物はエステルだった。
軍神――それも女性の軍神といった言葉がふさわしかった。カナンの兵士たちはエステルの入場に、皆、腰を落とした。
馬を停め、エステルは周囲の状況を確認していた。そして……
「お前は……」
鞍から飛び降りた。そしてモルデと目を合わせた。
「エステル様、スサノヲ様です」
「まことか……。こんなところで会おうとは……」
「奇遇だな」スサノヲは周囲の惨状をあえて見ながら言った。「ずいぶん派手なご登場じゃないか。会う場所では、かならず流血があるな」
エステルは言葉に詰まった。「……こんなところで、そなたは何をしている」
「俺はただ目的の地に辿りついただけだ」
「では、そなたが言っていた〝ネの片隅〟というのもここだったのか。なんという偶然だ……」
「そうやって侵略しているところを見ると、あんたらが言っていた〝約束の地〟というのもここらしいな。このワの国を征服しようとしているのか」
征服という言葉に、その場に残っていたワの民たちに動揺が走った。
「なんだとぉ?」イタケルが気色ばんだ。
「当たり前だ」エステルは傲然と言い放った。

「この葦原の国、ワの国は、われらのために神がお約束された〝もう一つ土地〟だからな。われらにはここを支配する権利がある」
「ふざけやがって……」
エステルはイタケルの怒りなど歯牙にもかけず、柱の立つ広場の中央、高台へ登って行った。そしてあたりを俯瞰(ふかん)した。
雷雲がいつの間にか立ち込めていた。遠雷が響く。
「ここは良いところだ。実りが多く、清らかな水が流れる土地。このような土地が、この地上にあろうとは……。こここそが、神のお約束されたカナンの地なのだ。ここにわれらはかつての栄華を極めた王国を再建する」
エステルは腰に帯びていた長剣を抜き出した。そして、それを大地に突き立てた。あたかもその行いに呼応するように、すぐ近くで雷光が輝き、大空全体を轟き震わせた。
「われらはこの国を貰い受けに来た。死にたくなければ国を譲れ。神の名のもと、この国の正統なる所有権はわれらにある!」
「お前らの言う神ってのは、いったいどの神じゃ!」イタケルが噛みつくように言った。「山の神か、川の神か、それとも雷の神か!」
「神は一つしかおわせぬ! どれもこれもない!」
「他は否定するか」と、アシナヅチが言った。
「当り前であろう」
「それではやがてわが身を滅ぼす」
「なに?」
アシナヅチはスクナを連れ、そばまでやって来ていた。彼はオシヲほかの残っていた者に負傷している里人を運ばせ、治療するように指示した。クシナーダのそばにいた老人も運ばれていく。
「そなたらは大陸のはるかか西のかなたからやって来たのであろう。国を奪われ、長く虜囚の憂き目に遭い、もはや帰るべき土地も多くの異民族に占拠されておる……」アシナヅチは瞑目していた。が、彼は何かを視ているようだった。「列強の国々が支配を繰り返す中、そなたらは故郷の土地で、その〝神の王国〟を再建することをあきらめ、別な土地を求めてここまで来た。そうであろう」
エステルたちはしばし絶句していた。アシナヅチの言葉がことごとく的中していたからだ。
「そなたらは根本的な考え違いをしておる」
「なんだと?」
「国や土地を得るためには、奪い取らねばならぬ。そう思うておるのであろう? 目には目を歯には歯を」
「…………」
「この国の土地は誰のものでもない。皆このワの島国で共に生きる。ただ、それだけのことじゃ。この島国は、はるかな昔より、多くの民が流れ着き、そしていつの間にか一つになって暮らしてきた。南方より黒潮に乗って来た者、凍てついた雪と氷の大地より下ってきた者、稲を持って渡来してきた者、そしてわれらのように古(いにしえ)よりここで暮らす者……。ここで生きれば、皆、共にワとなる。この国がワの国と呼ばれるのはそれゆえ。それゆえに――」
「ゆえに?」
「そなたらもここで共に生きるがよい。ただ、それで良い」
アシナヅチの論法は、エステルのこれまでの理解を完全に超えたものだった。どう反応したらよいのか迷った挙句、彼女は笑った。
「ふ……ははは。ワの民というのは、つまり争わぬということか」
「さよう。そなたらと争う理由がない」
「理由はあるぜ!」イタケルが言った。「こいつらは里の人たちを傷つけやがった!」
アシナヅチは杖を持つ手で、イタケルを制した。
「その若者が言うことには理がある。悔しければ戦ってみよ。そのほうが現実が骨身にしみるだろう」
エステルは地に刺した剣を抜き、そしてそれをイタケルやアシナヅチに向けた。
「やめろ」スサノヲが言った。「エステル、見ての通りだ。この小さな村には、ろくな武器もない。あるのなら、とっくに持ち出してきているだろう。平和に暮らしている人々から土地を奪わずとも、お前の目的は達せられるのではないか」
「そうも行かぬ」
「なぜ?」
「この地は戦略上、重要な場所だ。東のオロチ国と対峙していくためには、ここを抑えておいたほうが良い。東西だけではなく南北にも通じる道がある。そのために今日は、この近くのオロチの重要拠点を叩き潰したのだ」
「どうあってもここを取るつもりか」
「取ると言ったら?」
スサノヲはスクナが自分を見つめているのに気付いた。それは救いを求める者の眼だった。クシナーダもじっと見つめていたが、彼女の眼差しは色が違っていた。救いを求めるのでもなく、ただスサノヲの為すことを追いかけようとするものだった。
「――ならば、仕方ない」
スサノヲの姿はその場から消えた。人々は眼を疑ったであろう。彼はろくな助走もなく、ひとっ跳びにエステルの立つ場所まで飛びあがっていた。
そして、すでに彼女の喉元へ剣を突き付けていた。
「エステル様!」
兵士たちに動揺が走った。
「兵に引くように命じろ」と、スサノヲは言った。
エステルは青ざめていた。スサノヲの常人ならざる速度は、スサの地で一瞥したものだったが、まざまざと自分の身でその恐ろしさを味わわされていた。
「私を殺したところで、カナンの理想は潰えない。ヤイルやモルデがかならずこの国を制圧するだろう」
「それは不可能だ」
「なぜ、そう言える」
「お前は知っている。俺がたった一人でも、お前の仲間を全滅させられるのを」
それは掛け値なしの真実だった。
「俺を敵に回さないほうがいい。でないと、神の王国どころではなくなるぞ」
再び雷光と轟が生じ、二人の横顔を染めた。
「……いいだろう」エステルの顔が笑みを浮かべた。ゆっくりと自分の剣を鞘に収める。
それを見て、スサノヲも剣を引いた。
「皆の者! 剣を収めよ!」
エステルの命令で、兵士たちは安堵した。
「そなたにはスサでの礼もできていない。そなたがそこまでご執心なら、この里には手を出さずにおく」
「感謝する」
「あのときの剣はどうした?」エステルはスサノヲの手元や腰回りを見て言った。
「ああ、舟が難破して、一緒に海の中だ」
「ならば、これを使え」と、エステルは自分の剣をベルトごと外した。「わが一族に伝わる霊剣だ。弟の形見だがな」
「エ、エステル様、それは――」と、ヤイルが近寄ってくる。
「よい――。さあ、これを使え」
「いいのか?」
「スサで一度、今日で二度、命拾いをさせてもらった。弟も喜ぶだろう。それに、その剣、私には少しばかり重くてな」と、苦笑する。
「ならば、遠慮なく」スサノヲは長剣を受け取った。
「だが、覚えておくがよい」その言葉はスサノヲだけに向けられたものではなかった。アシナヅチ他、ワの民にも発せられたものだった。「われらはこの島国に、カナンの王国を築く! 邪魔するものは容赦なく滅ぼす! 肝に銘じておくのだな!」
エステルは高台を降りて行った。馬に飛び乗ると、号令した。
「行くぞ!」
カナンの軍勢は整然と里を出て行った。一度、モルデが振り返るのが目についた。
雨が降り始めた。最初はパラパラッとだったが、すぐに切って落とされたような豪雨になった。アシナヅチの命で、殺された者たちが運ばれていく。どこかで弔われるようだ。
びしょ濡れになって、スクナとクシナーダが待っていた。
スサノヲは二人のところへ降りて行った。
5
人の気配がして、近づいて来るのがわかった。ばさっと近くの岩場に、衣類が放り投げられた。
「着替えを持ってきてやった」イタケルだった。
「ありがとう」
「クシナーダに言われたからな」言い訳じみた言葉を口にし、彼は自分も着ているものを脱ぎ捨て、湯溜まりに飛び込んできた。
渓流沿いに湧いている温泉の溜まり場で、スサノヲは湯船に身体を沈めていた。川から引きこむ水量が調整されていて、程よい温度だった。これまでの旅で、一度も味わったことのないような湯浴みだった。身体の芯からほどけていくような心地よさである。
雷雨は、今は去っていた。ザーッという渓流の響きが、夕暮れの渓谷を満たしている。
「俺はお前のことを信用したわけじゃないぞ。ほかの連中は、里を救ってくれたみたいに思ってるが」イタケルは乱暴に顔を洗った。「今日、お前が里に来る直前に地震(なえ)があった。そしたらあいつらがやって来た。あのカナンとかいう連中が。俺にはお前が災厄を連れてやって来たようにしか思えねえ」
スサノヲは無言だった。イタケルの言葉は、さして間違っていないように思えた。これまでの旅の途上でも、似たようなことは幾度もあったからだ。
「災厄というのはもっとほかにもあるのだろう?」スサノヲは言った。「〝オロチ〟とか言っていたが」
「ああ。オロチはここ何年かででかくなった国だ。最初はもっとずっと東のほうにできた、小さな国だった。大陸を追われてきた連中だ。だが、クロガネを作り始め、たちまち周辺の国々を侵略し、まとめ上げていった」
大陸から鉄器製造の技術を持った集団が渡来し、勢力を拡大しているということらしかった。
「クロガネはすげえ。うちの里でもクワやスキに少し使うようになったが、まだほんの少しばかりだ。石や木で作った武器なんかじゃ、とても太刀打ちできねえ」
「この里では作れないのか」
「アシナヅチが許してくれない……」悔しげに言った。「作り方はだいたいわかっているんだ。里の中にも知っている人間がいる」
製鉄の技術は大陸ではすでに広く知れ渡っている。この世界の果ての島国には、まだ到達したばかりという状態らしかった。
「オロチ国はこの周辺に手を伸ばしているのだろう? エステルが近くの拠点を叩いたと言っていたが」と、スサノヲは尋ねた。
「ああ」
「ならば、なぜここはオロチの支配下に入っていない?」
「ここは……特別なんだ」
「特別?」
「ああ、特別だ」イタケルはそっぽを向いていた。喋る意志はないという表明のようだった。
スサノヲは湯船から出た。手拭いで身体を拭いていると、湯船の中からイタケルが言った。
「あのカナンの連中とは、どういう関係なんだ」
「カナンのエステルとは、ずっと西のほうの街で出会った。そのときあのお姫様の弟が殺され、俺は彼らを助けた」
「なるほど。それであいつらは、あんたの頼みで、この里から手を引いてくれたってわけか」
「そういうことだ」
「あんた、いったい何者だ。どこから来た?」
「逆に訊きたいが……」スサノヲはイタケルを見た。「お前は自分が何者なのか、答えられるのか」
「え? お、俺か? 俺はこのトリカミのイタケルよ。いずれワの島国を一色(ひといろ)に染め上げる男よ」
「国を一色に……」スサノヲは空を仰いだ。「なかなか野心的だな。つまりそれはエステルやオロチと同じことをやろうとしているということだな」
「あたりめーだ。いつまでもいつまでも、やられてばかりじゃねえ。俺はあのオロチの奴らを、いつか滅ぼしてやる……」イタケルの眼に剣呑な光がぎらついた。口の端から、憎しみがこぼれ出ていた。
「オロチに恨みがあるのか」
「オロチには何人も殺された……」
スサノヲは新しい衣を身に着け終えた。ほかの里人が身に着けていたようなシンプルな麻の貫頭衣ではなく、おそらく大陸から渡来したものだろう。金糸の刺繍があった。
「このところ、ワの国は争いばかりだ。どこでもかしこでも戦(いくさ)ばかりやって、悲しい思いをしている人間が大勢いる」
「それでお前は、自分が支配者になって、争いをなくしたいと?」
「その通りだ。なあ、あんた――」イタケルの口調は、だんだん馴れなれしくなってきた。「その剣、一本、俺にくれないか」
スサノヲはカナンの兵士から奪い取った剣とエステルから与えられた剣の二本を持っていた。エステルから与えられた剣を手にし、もう一本は、そのままイタケルの衣類のそばに置いた。そして、その場から離れた。
「すまねえ! ありがとうよ! 恩に着る!」
背後に聞くイタケルの声には、本当に感謝があふれていた。それだけ、これまでに悔しい思いを繰り返してきたという証明だろう。
クロガネ。
この島国は今、その力によって翻弄されているのだった。
この、おそらくはもとは静かで平和だった国が。
里の中心に戻っていくにつれ、あるリズムを持ったヒビキが大きく聴こえるようになった。鐘の音、太鼓の音、そして笛の調べ。
スサノヲは目を奪われた。夕闇が濃くなりつつある時刻、四方に炊かれた篝火(かがりび)の中、人々が里の中心に聳える大きな柱のまわりを取り囲み、ゆっくりとある所作を繰り返していた。ひざまずいて両手を空へ捧げ上げるような動作を繰り返し、そして立ち上がる。ゆっくりと柱を中心に、所作を変えながら弧を描いて歩を進める。
里の中心が打ち立てられた柱であるのは明白だった。三重円の環状路が出来上がっていたのは、このためだったのかもしれない。里人たちはこぞって外に出て、三重の円になって柱のまわりを回っている。ある時は反転して逆回転になり、ゆったりとした動きから、にわかに打ち寄せる波のように足早に回ったりもする。
不思議な踊りだった。単調なようでして、強弱もリズムもある。難しい所作は何もない。
中心には八人の乙女たちがいた。彼女らは柱のすぐそばで同じように舞っている。
その中の一人にクシナーダがいた。
神々(こうごう)しかった。
自分がそのような感想を抱くことに、スサノヲは激しい動揺を覚えた。ほかの乙女たちともクシナーダは格段に違っていた。一人だけ目に見えるがごとくオーラを放ち、彼女の周囲には違った空気が流れていた。ものみな浄化するような、澄んだ清流のごとき〝気〟だ。
それは舞いと共に周辺に広がっていく。柱に一番近い円へ、その外側へ、さらにその外側へ。その波動は、スサノヲの立っている場所にも届き、彼はみずからが洗い清められるのを感じた。
息を呑んだ。
いまだ曇天であったはずの空が割れ、星空が顔を見せた。最初は月光かと思われたが、空に月はない。そうではなく、柱の上空から光の粉が降って来るのだ。
「なんだ、これは……」思わずつぶやいた。
「巫女様が亡くなった人を霊(たま)送りしてるんだよ」
いつの間にか、スクナがそばに来ていた。顔や身体をきれいにして、着替えを済ませているため、少女らしくなっていた。
「霊送り?」
「あたしも初めて見た。あたしの国の巫女様は、ここまですごいことはできなかった」
空から降りて来る光はどんどん強くなった。錯覚ではない。はっきりと肉眼で見えるような神々しい光は、白というのか白金のような輝きを帯びて、柱を中心にふわっと広がって行った。
ぽつ、ぽつ、と新たに地上から光が出現した。それは里人数人が役目として抱え持っていたようだ。彼らの手を離れた光は鈍い光で、まるで自信なさそうな浮揚の仕方をした。
降りてきている光の中から、もっと明瞭な光の珠が出現し、その鈍い光たちを迎えた。
――人?
そう。目を凝らすと、なぜかその光はいずれも人の形にも見えた。
天から降りてきた光は人形(ひとがた)となり、そして鈍い光もまた人形となった。鈍い光はさきほどカナンの兵たちによって殺害された者たちだとわかる。それを迎えに来たのが、まばゆい光たちなのだった。
クシナーダが鈴を鳴らした。
シャンシャンシャン!
里人たちが地から天へ送るようなしぐさを繰り返す。
それからは素早かった。鈍かった光たちはたちまち輝きを増し、迎えに来たまばゆい光たちと一体となり、柱の上空へと駆け上って行った。
そして、不思議な光は消えた。
スサノヲは唖然としていた。多くの国、民族を見てきたが、このような鎮魂の儀式を執り行っている民にはお目にかかったことがなかった。しかもただの形式的な儀式ではなく、圧倒的な霊的リアリティを持っていた。
まるで魔術だ。しかし、魔術というには、この場の雰囲気はあまりにも神聖で清らかだった。
里人たちが役目を終え、散開し始める。クシナーダが柱の立つ高台から降りてくる。
「湯浴みはいかがでしたか」と、笑顔で言う。
「ああ、いい湯だった」
「お似合いですよ」とも笑う。着替えのことを言っているのだ。
「こんないい服を、いいのか」
「それはアシナヅチ様がお若い時、大陸の……ええと、なんとかという皇帝から頂いたものだそうです」
「ということは、アシナヅチもずいぶんと高貴なお方なのだな」
「アシナヅチ様のお力は知れ渡っておりますから。さあさ、こちらへ」
篝火が集められ、宴が用意された。里人たちは共同作業に長けていて、なんでも自然に連携できるようだった。子供から老人まで、自分ができることは率先してやっている。基本的に年寄りは敬われ、大切にされていた。しかし、元気な者は老人でもよく動いた。
クシナーダはそんな中でも、よくくるくると動いた。ほかの里人は、若くともクシナーダに格別の崇敬をやはり抱いているようだった。この点は一緒に舞っていた他の乙女たちも同じで、彼女たちも「クシナーダ様」と呼んでいる。同じような巫女としても、すでに備わった格の違いは、権威としてではなく静かな物腰の中に自然体でにじみ出るようだ。だが、クシナーダ自身にはお高く留まったところはまったくなく、自分にできることはなんでもやっていて、焚火に入れる薪を大量に抱えて歩いてきて、他の者を逆に慌てさせたりしていた。
その頃にはイタケルも戻って来ていて準備を手伝っていた。
「スサノヲ様、さあ、こちらへ」
「どうぞどうぞ!」
乙女たちがスサノヲを席に案内した。異国から到来した若い男に、好奇心で輝く眼を隠そうともしない。
やがてあたりには根菜やキジ肉を入れた鍋や焼けた魚の食欲をそそる香りが立ち込めはじめ、どこが始まりなのか分からないような流れで宴になっていた。
酒がふるまわれ、笑い声も弾けた。
「さあ、どうぞ。召し上がってくださいな」クシナーダが鍋の中身をよそった土器とお酒の入った竹のコップを持ってきた。「ミツハ、スクナにも」
もう一人、ミツハと呼ばれた娘がスクナにも食事を運んでくる。
「さっきはありがとうね」と、ミツハがスクナに言った。
なんのことかと見ていると、クシナーダが説明した。「さきほど、怪我をした者のために、薬草を集めてきたりしてくれたのです。おかげできっと、傷の治りも早いでしょう」
ああ、とスサノヲは納得した。
「この子はすごく賢い子です」ミツハが感嘆する。「本当になんでもよく知っています」
「坊主……じゃなかった。女の子だったな」イタケルがそばに腰を下ろして言った。「おめー、ナの国の人間なんだよな。どうする? 落ち着いたらナの国へ戻るか?」
スクナは食べようとした鍋の器を膝の上に置いた。
「どうした? 戻るなら、俺が送ってってやるぞ」
「戻っても……誰もいない」
「先ほどちょっとこの子から聞いたのですが」クシナーダが言った。「ご両親と三人で、しばらく大陸を旅されていたようです。ワの国に戻るのも三年ぶりとか。ナの国に戻っても、頼れる人がいないのでしょう」
「なら、ここで暮らすか? おめー、頭がいいし、役に立つ。みんな、喜ぶぜ」
「ほんとう……?」スクナはイタケルやクシナーダの顔を見た。
「もちろんですよ。ここでお暮しなさいな」
スクナはスサノヲのことも見、そして表情を明るくした。
「よかったな、スクナ」と、スサノヲは言った。
歌声が湧いた。男たちが歌い、女たちが踊る。先ほどまでの神聖な雰囲気とは違い、ぐっと砕けた調子で、男と女の恋歌が物語調に語られる。引き裂かれた男女の悲しい物語だったが、どこかユーモラスだ。ひょうきんな動きの男が踊りに加わり、笑い声がどっと弾ける。
陽気な民だった。
゚・*:.。..。.:*・゚遠く離れてしまった
゚・*:.。..。.:*・゚愛しい人よ
゚・*:.。..。.:*・゚空のかなたに昇って
゚・*:.。..。.:*・゚二人隔てる天の川
゚・*:.。..。.:*・゚涙が流れを深くする
゚・*:.。..。.:*・゚想いの笹船流す日々
゚・*:.。..。.:*・゚一年(ひととせ)に一夜だけ
゚・*:.。..。.:*・゚川を渡るほうき星
゚・*:.。..。.:*・゚たった一夜の逢瀬の時……
「古くから伝わる歌です」クシナーダが説明する。「天の川をはさんで輝く二つの星の物語です」
「天の川……」
空を仰ぐ。気が付くと、上空はすっかり晴れていた。そこには空を渡る、大きな星々の流れが広がっていた。
「引き離される悲しみは、恋だけではありません。天と地に引き離される、死の別れもあります。だから、いつも霊送りをした後は、こうやってこの歌を歌って宴をするのです。今日はスサノヲ様の歓迎もありますが」
「霊送りと言っても、送ったのはあのオロチとかの連中の魂だろう」
「そうですね。さいわい里人には亡くなった人はいませんから」
「オロチの連中の霊送りなんて、してやらなくていいんだよ」イタケルはぶすっとしている。
なるほど、それで湯浴みで時間をつぶしていたのかと思えた。
「あら、亡くなれば、みな、同じです。帰るところも同じ」
「身内が亡くなっても、こんなふうに騒ぐのか」と、スサノヲは訊いた。
「はい。もちろん泣きもしますよ。でも、わたくしたちは知っているのです」
「知っている? なにを?」
「この地の者と天の者は、本当は離ればなれになるのではありません。この歌の隔てられた男女のように、悲しくもあり寂しくもありますが、いつでも想えば通じ、本当は会うこともできます。わたくしたちは皆、さきほど見た、あのような光です。それはオロチの者とて、例外ではありません」
「俺は嫌だね」イタケルは酒をがぶりと呑む。「死んであいつらと同じところなんか行きたくねえ」
「イタケル……」
「クシナーダはなぜ奴らを許せる? アワジは奴らに殺されたんだぞ。イヨもオキも。ツクシ、サデヨリ、イキ、サド――みんな」
そのとき初めて、クシナーダの表情は深く陰ったのをスサノヲは見た。悲しみ、憂悶。そんな色がありありと浮かんでいた。巫女として精神性の非常に高いところに上り詰めたであろう、そんな彼女でさえ、やはり人間的な葛藤は残しているのだ。
「アワジはクシナーダの実の姉だ」イタケルはスサノヲにも分かるように言った。「守ろうとしたクシナーダの両親もその時に殺された。俺は絶対に奴らを許さねえ」
「オロチはなぜそんなことを?」スサノヲは訊いた。
「わたくしたちはこのワの島国でも、もっとも古くからの民です。わたくしたちは特別な役目を持って、このトリカミの地を守っております」
「お、おい、クシナーダ」イタケルが慌てた。
「いいのです、イタケル。すぐにお耳にも入りましょう。それに、この方には知っておいてもらいたいのです」
「特別な役目というのは?」
「それはスサノヲ様、あなたがこの地を訪れた目的にも関わっています」
そのとき笑いで湧いていた宴の席が静まった。首長のアシナヅチが、近くの家屋から出てきたところだった。アシナヅチは身振りで他の者に宴を続けるように示し、再び歌声が響きはじめる。
クシナーダは立ち上がって席を空けようとしたが、アシナヅチはそれも手で制して、自分はスサノヲの隣ではなく、顔を見やすい場所へ腰かけた。
「まずは礼を言わねばならん。そなたがいなければ、あのカナンという者どもに、このトリカミは支配されてしまっただろう」
ありがとう、とアシナヅチは頭を下げた。
「いや……」
「クシナーダから聞いておる。そなたはヨミの国へ行きたいのだそうだな」
ぶーっと、イタケルが口にした酒を吹き出した。「な、なんだってぇ?」
信じがたいという眼差しを向けてくる。正気を疑うと言わんばかりだ。
「ああ。ヨミへ至る道、ヨモツヒラサカをクシナーダは知っていると言っていた。教えてもらいたい」
「その身のままでヨミへ行けば、もはや生きて戻れぬやもしれん」
「覚悟の上だ」
「なぜ、ヨミへ行きたがる?」
「…………」
「愛する者がそこにおるのか」
スサノヲは少なからず動揺した。
「まあ、驚くようなことではない。古来、ヨミへ下った者は多くいる。その動機はほとんど同じ一つの理由じゃ」
「じつはスサノヲ様」クシナーダが言った。「わたくしたちがこの地を守っているのは、そのヨモツヒラサカにも関わっているのです」
「どういうことだ」
「この地には神聖なる岩戸があるのじゃ。我らは代々、長きにわたりそれを守ってきた」
アシナヅチとクシナーダは意を一つにしていた。そのことについてスサノヲに語るというのは、すでに彼らの間では取り決められていたものだったようだ。
「その岩戸は天にもヨミにも通じておる。定められた時、それを開けば、ヨミへ至ることができる」
「つまり……それがヨモツヒラサカ」
「そういうことじゃ。ただし、開けることはわれらにしかできぬ。その場所を知ったところで、そなたが単独で扉を開けることはできぬ。いかに天界より下った者であってもな」
「!」
「まあ、そう驚くでない。そなたがやって来ることは、以前よりわかっておった」
「て、天界より下った?」
驚いているのはイタケルとスクナだった。クシナーダにとっては周知の事実だったようだし、近くに同席していたミツハという巫女も、なんらかの事前の知識があったに違いなく、さして驚いてはいなかった。
「魂は、人を介し、母の胎(はら)を通じてこの地に生まれる……。しかし、ごくまれにそなたのような存在が、地に現れることがある。そう、何千年かに一度のことではあろうが」
「驚いたな……」スサノヲは動揺を静めながら、苦笑を浮かべた。「とんでもない爺さんだ」
「伊達に長生きはしておらぬゆえにな。それにわしの眼には過去未来、あるいは遠くのあの輝く星の様子でさえ映る」アシナヅチは杖を持ち上げ、天を示した。「星々の多くはまあるい玉の形をしておる。わしらが住むこの星も、あれらと同様。海よりさらに大きな、果てのない世界の中に、われらの星がある。われらはこの星の片隅で、命を与えられて、束の間の時を過ごしておる」
心底、驚嘆すべき老人だった。スサノヲは多少の通力を得た人間には出会ってきていた。しかし、アシナヅチのように正確な世界観を持つ人間には、まったく出会ったことがなかった。彼はこの時代の人類が持つ認識を、はるかに超えた知恵を持っていた。
「この星の寿命から見たら、人の命などはかないもの。それはカゲロウほどの長さもあるまい。しかしな、人の命のつながり、想いのつながりは、この星空にも匹敵する。なかなか馬鹿にはできぬものじゃ。人はやがて星の海へも旅立つ時が来る。しかし、その前に荒々しい時代に終止符を打ち、真のワとならねばならぬ……。そなたがここへ遣わされたのは、そのためかもしれぬな」
イタケルもスクナも、息を呑むように会話を聞いていた。スサノヲは酒を呑んだ。
「――そんな遠い未来のことはどうでもいい。それはあんたらだって同じじゃないのか。未来がどうであれ、今ここにある問題を片づけることが大事だ。そうじゃないか」
「いかにも」
「あんたらは岩戸を守る民で、それはオロチの連中のやっていることとも関係しているのだな?」
「このトリカミの岩戸を守るわしら、そして何よりも巫女は、このワの国の中でももっとも貴ばれておる。それは古くからこのワの国に住む民なら、皆、知っておる」
「オロチの奴らはこの島国全体を支配しようとしている。次々にいろんな土地を奪い取って支配を広げるやり方に反発する者も多い」イタケルが鋭い目を焚火の炎に向けて言った。「だから、ワの民全部にとって大事なこのトリカミの巫女を、毎年一人ずつ略奪し、見せしめに殺した……」
彼の記憶の中では、これまで奪われていった巫女たち、その死の様がよみがえっているのだろう。
「オロチがここを直接支配せず、放っておくのは、ここが特別な聖地だからです。ここを略奪したら、ワの民すべての反感を買い、支配するのは難しくなります。そのかわり、わたくしたちは人質として残されているのです」
「つまりあんた――クシナーダも狙われているということか」
「きっとこの冬のうちに今度はわたくしが連れて行かれるでしょう」
覚悟を決めているかのような、あきらめのような静かな様子だった。
「そこでじゃ。スサノヲよ、交換条件じゃ」
「交換条件?」
「この地を守ってもらいたい」
「このトリカミの地をか」
「むろんそれもあるが、違う。このワの国を守ってもらいたい」
「な……」
「約束してもらえるかのぉ」アシナヅチはにっと笑った。「さすれば、ヨミへの岩戸を開こう」
「ずいぶんと足元を見た条件だな」
「おや、そなたならできよう」
ワの国を守るというのは身一つに課せられるには、あまりにも広大な要求だ。いかにスサノヲでも。
大陸に比べれば島国は小さなものだ。とはいえ、決して狭くはないだろう。その端々まで守るという約定は、ほとんど実行不可能なものに思えた。
「そもそも、そなたには選択権などない」
「なに?」
「もうこのトリカミには岩戸を開けるほどの霊力を持つ巫女はクシナーダしかおらん。この娘(こ)が連れて行かれたなら、もはやそなたがヨミへ行くことはかなわなくなる」
「それなら、なぜ約束などと……」
「そりゃ、わしがしてもらいたいからじゃ。約束を」
アシナヅチはにたにた笑っていた。恐ろしく根深い魂胆を秘めた、悪戯好きの老人といった感じだった。老人には、スサノヲがワの国全体を守るなど現実的には難しいとわかっているはずだった。彼の言葉の意味には、もっと深いものが隠されているような気がした。
スサノヲはその深いところにあるものに対して答えを告げた。
「わかった。約束しよう」
「この約束を守るためには、そなたはかりにヨミへ行っても、かならず生きて帰ってこなければならん」
「もとより死にに行くつもりなどない」
「よかろう。それならば、そなたはふた月ほど待たねばならぬ」
「ふた月?」
「ちょうど今日は朔の日じゃ」
新月ということだ。
「この次、さらにその次の朔の日。月がなくなる日の夜が、もっとも昼が短い季節の朔の日じゃ。その日でなければ、ヨミへ通じるヨモツヒラサカは開かれぬ」よっこらしょ、とアシナヅチは立ち上がった。「それまで、この地でゆるりと過ごされることじゃ」
そう言って、彼は背を向けて自分の家屋へ戻って行った。
燃え上がる焚火の中で、何かが爆ぜた。その音で正気に返ったように、スクナがスサノヲの腕に触れてきた。スサノヲは少女の頭に手を置いた。
見るとクシナーダは珍しく硬い表情の横顔を見せていた。焚火の炎はその大きな瞳と頬を、あかあかと照らしていた。
 小説 ブログランキングへ
小説 ブログランキングへ